「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質 [原器を目指した「最終アンプ」]


<写真1:電源ON時の突入電流により不良MT管の下部が1・2秒光る様子>


上段はラッシュカレントでピカーと光る不良MT管(記事は当ページ)。
下段は私が20年以上前に、交流点火やスイッチング・レギュレーター点火など、散々いじり倒したWE300Bsアンプです(記事は(7の2))。
不良MT管「ピカ球」
交流点火ラッシュカレント(突入電流)の実演
私が名付けた「ピカ球」を挿して電源ON!(上の写真1)。
トランスのヒーター巻線直結の最も過酷なラッシュカレントの直撃を喰らって管内下部が1・2秒明るく光る。
この光る原因と、その不良個所の写真は、この後の写真3。

<写真2: 1・2秒後には光は消え、しばらくして全球のヒーターが灯る>
* *その後は何事もなかったように正常動作し、健全な球との区別はつかない**
不良「ピカ球」の原因や、不良個所の写真等の詳細は、この後の本文をご覧いただきたい。
10数年~20年ほど前に購入した各種のMT管(数10本)の中に、このような球が少なからず混じるようになった。
この球の欧州ブランドのロゴ印の信憑性や、中身との整合性について、私は興味がない。
一流メーカーの正規生産が終了した後に作られた球であろう。
定電流点火と突入電流
交流点火も定電圧点火も、ラッシュカレント(突入電流)の実害なし
逆に定電流点火はフィラメントやヒーターに過酷な負担を強いる
言い得て妙「オームの法則無視しちゃダメ」
「最終アンプ」は、「「3端子レギュレーター」による「直流・定電圧点火」である。
「最終アンプ」に関する私と円通寺坂工房とのやり取りは、今から20年以上も昔の話である。
その当時から、私も円通寺坂の工房も、「交流点火」には音響的にプラスの要素はなく、むしろマイナス要素しかないことを「常識」としていた。
また「定電流点火」などは、その「常識」以前の話しであり、考えられないことであった。
円通寺坂工房での熱すぎるコーヒーの話はバックナンバーにあるが、その茶飲み話に、フィラメント点火法式の話も話題に上らなかったわけではない。
正面から議論する問題ではなかったが、世間話しには出た。
この話にかぎらず、いわゆる「風説」の話になると円通寺坂工房のKさんの口癖は、「オームの法則無視しちゃダメだよ」であった。
これは「言い得て妙」な名言である。
「オームの法則」とは、その法則そのもののことを指すのではなく、エレキ全般の法則・原理・用法のことを象徴した言葉である。
オームの法則無視の典型「定電流点火」の非情
「定電流点火」を是とするなど、これこそ正にオームの法則そのものを無視した典型である。
この問題はズバリ、「オームの法則」そのものが是否の答えになる。
ただし、定電圧点火における電源ON時の突入電流の影響についての指摘は、もっともな話しである。
もっともではあるが、私が使ってきた真空管の20年~30年ほどの実績から、実害はなかった。
ただし、冒頭写真1の「ピカ球」のような、ヒーターに不良個所がある真空管にとっては、電源ON時の突入電流はダメージを与える可能性がある。
ただし、そのような不良球の救済のための「定電流点火」であれば、それは本末転倒である。
電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るMT管は不良品
ここ20年ほど前あたりからか、購入したMT管の中に、電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るものが混じるようになった。
今現在はどうなのかは知らない。
昔は、そのような球は市場には出なかった。
品質管理の過程でハネたのだろう。
不良品である。
昨今はそのような球も売りさばくようになったのだと思う。
「光る球でも問題ない」と言っている人もいるが、残念ながら問題のある不良品である。
数百回も「ピカー」を繰り返せば、遅かれ早かれヒーター断となる。
手っ取り早く実験するには、その「ピカ球」を、「ピカー」と同じ程度の明るさになるような電圧で点火すれば、数分を待たず、ご臨終となる。
私は以前、それを試してみた。
あっけないくらい、短時間で切れる。
いつまでも点灯を続ける白熱電球を連想してはいけない。
電源ON時のピカーの持続時間を1秒とすると、100回で100秒、つまり1分40秒である。
だから「耐用回数」は数百回程度だろうと思う。
ただしその寿命は、ピカーっと光る時の光り具合、つまり温度に依存する。
金属の蒸発なので、ある温度を境に、急激に短寿命になる可能性がある。
その逆のことも言えるので、暗い光なら、ダメージは少ないかもしれない。
光る原因はむき出しの発熱線
光る原因は、その部分を観察すればすぐに分かる。
「ピカ球」のヒーター線と、足のピンとの接続部分(溶接部分)を、ルーペ等でよく見ると、発熱線が数mmむき出しになっている。
絶縁コーティング部や、カソードスリーブに収まっている部分は熱慣性が大きいが、むき出し部分はそれがなく、電源ONのラッシュカレントで白熱する。
足ピンとの溶接部分は当然むき出しであるが、熱は足ピンに逃げて白熱しない。
私の推論であるが正解だと思う。
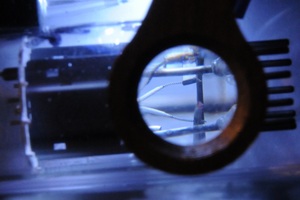
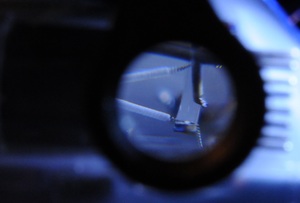
<写真3:電源ON時にピカーっと光るMT管の原因個所>
**左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが生産現場で定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りも雑、品質管理も雑になってきたのだろう。写真の球はいずれも欧州ブランド印のECC82**
不良球の「ピカ球」には定電流の効果あり
光るのは、電源ONのラッシュカレントの、ほんの1・2秒のことなので、安定時の電流値(つまりヒーター電流の規格値付近)で定電流点火すれば、光らないのではないかと思う。
確かに定電流点火は、「ピカ球」の光ることによる消耗に対しては有効だろう。
ただし、不良球に有効でも、正常球にメリットがなければ意味はない。
正常な真空管に対してはメリットなし 逆に過酷な「定電流」
突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。
そのような不良球相手の対策などは本末転倒であり、議論の俎上にはない。
結局、「突入電流」の問題は、定電圧点火であれ交流点火であれ、存在しないことになる。
稼動20年実証済 突入電流の実害なし
定電流点火は電源ON時の突入電流がないのでヒーターが長持ちする、という指摘がある。
これについては、先の「不良ピカ球」の段でお話ししたが、この球のような不良品については効果があると思う。
しかし健全な球については逆である、という指摘をした。
20年以上にわたる「最終アンプ」の稼動実績から、健全なヒーターにおける突入電流の影響について断言しておきたい。
801Aや10、それに211類のトリエーテッド・タングステン・フィラメント(トリタン)を定電圧点火した場合の話である。
電圧印加時の突入電流(ラッシュカレント)による、フィラメントへの悪影響は、この20年間みられなかった。
悪影響はなかった、と考えられる。
本機「最終アンプ」は、3端子レギュレーターの一般的用法により直流・定電圧点火している。
その回路図が図1、実物写真が写真4である。
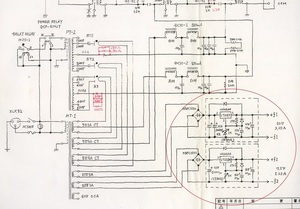
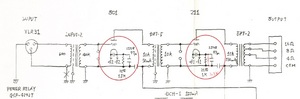
<図1:「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図>
**3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない**
a.jpg)
<写真4:3端子レギュレーター部のクローズアップ>
**左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用**
本機はこのような3端子レギュレーターを使用しているため、突入電流など、レギュレーターの電流容量を超える過大電流が流れた場合は、自動的に電流制限を受け、突入電流のピークが、多少は押さえられるのかもしれない。
さて本機の稼動状況であるが、日常の使用回数を、1日2時間、週に3日使うと仮定した場合、1年で156日、つまり156回電源を入れたことになる。
実際は1日に2・3回電源をON/OFFすることがあるので、まあざっくり1年に200回電源を入れたとしよう。
本機で使うお気に入りの211系の愛球は数本あるので、20年間で登板した日数は、おそらくその1本が通算5年以上にはなると思われる。
とすると、5年×200回=1000回になる。
「最終アンプ」稼動の実績として、個々の211や801Aに、少なくとも1000発の突撃電流を喰らわせたことになる。
801Aはほとんど交換しないので、2000発以上になるだろう。
ところがまだ、ラッシュカレントそのものによる異常な兆候や、健康被害の兆候を経験したことはない。
この経験から、もともと健全な状態のトリエーテッドタングステン・フィラメントであれば、突入電流の害について、神経質になる必要はまったくないと思う。
本機では、フィラメントの突入電流を緩和する仕掛けはいっさい設けていない。
真空管のフィラメントは、その材質が何であれ、冷えている時の抵抗値は低い。
そのため、定電圧点火のフィラメントの電源ON時には、大きな突入電流(ラッシュカレント)が流れる。
しかしラッシュカレントの先頭のもっとも過大電流が流れる短時間に、フィラメントのヒーターが過度に赤熱したり白熱することはない。
昔のトランスレス・ラジオのように、数本の真空管のヒーター(つまり熱慣性が異なるものを)をシリーズに接続するなどの、変則的なことをしないかぎり、先の不良MT管のように、瞬間的に高温になるような現象は起こらない。
金属が多少なりと蒸発するほどの温度に達する前に、全体の温度が上がり、ラッシュカレントの過大先頭部が過ぎ去るためではないかと思う。
もう一つ経験話をすると、211とは過去通算30年間ぐらい付き合っているが、フィラメントが切れた、切った、ということは一度もない。
専門書によれば、元来、211のような送信管規格の球における、トリエーテッドタングステン・フィラメントの寿命は、酸化皮膜フィラメントにくらべ格段に長い、ということになっている。
801Aのフィラメントが切れたのは、今までに3度ある。
当然ながらステレオなので、それぞれの球は2本ずつ稼動している。
音を出している途中で、静かに、本当に静かに息をひきとった。
少しの間、片チャンネルから音が出ていないことに気付かなかったほどである。どちらも電源ON時に切れたのではない。
寿命を心配して買い込み、屋根裏部屋に隠匿してある予備球の数は、私がこの世に何回生まれ変わっても使い切れないほどである。
傍熱管に突入電流の影響さらになし
突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。
これは直熱管だけではなく傍熱管も同じである。
傍熱管はスリーブの熱慣性があるため、直熱管よりずっと強い。
MT管のような小さい球も、KT-88のような大きな球も同じである。

<写真5: 初代のGECのKT-88は20年ほど使用して全球交換した。これは2代目>
**交換した古い球もゲッターは少なくなっているが、全球、まだまだ十分に健全であった**
たとえばGECのKT-88
普通この球は、ヒータートランスの2次巻線から直接点火されるため、電源インピーダンスが低い最も過酷なラッシュカレントが流れる。
しかしこの球は、長期間使い込んでゲッターがなくなっても、ヒーターはビクともしない。
私のAIRTIGHT ATM-2(写真5)のGECKT-88も、ゲッターがほとんどなくなるほど使い込み、今の球は二代目である。
このことは当ブログの「STAX ELS-8X」のバックナンバーのどこかに書いた覚えがある。
ゲッターはほとんどなくなったが、エミッションはまだまだ十分あり、つまりヒーターは健全である。
多くのKT-88ユーザーが、同じような経験をしている。
要するに、最も過酷な突入電流が発生するヒータートランス直結の交流点火でも、生涯、ラッシュカレントの影響などはない。
これが事実であり、現実である。
突入電流の警告はまず交流点火にこそ
トランスのヒーター巻線のインピーダンスは大変低い。
そのため、交流点火は他のどの点火法式よりも突入電流が大きい。
その意味から、突入電流の害の警鐘を鳴らすのであれば、直流点火における定電圧点火より先に、交流点火にこそ向けるべきである。
ただし私の見解は上記のように、いずれの点火方式も、元が健全な球であれば、突入電流に関する不都合は発生しない。
そのお節介は必要ないだろう。
破滅に向かってアクセルを踏む定電流点火
初期状態が健全であるヒーターを前提に、直熱管・傍熱管ともに、定電流点火は、稼動時間が増すに従い、ヒーターの寿命を縮める方向に作用する。
先の「オームの法則無視しちゃダメ」の最たる事例である。
「定電流点火」のエネルギー源は、ヒーターの健康ライフにやさしくない。
このエネルギー源は、歳をとればとるほど身(発熱体)を細らせる。
さらに、細った部分を狙ってエネルギーが集中する。
オームの法則、「エネルギーW=Iの2乗×R」。
寄る年波に痩せてくる体に、この「電流値Iの2乗×抵抗値R」がボデーブローのように効いてくる。
与えられるI(電流値)は常に一定であり手加減はない。
細った発熱体の部位には、健全な部位より高いエネルギーが集中して温度が上がり、発熱体の蒸発が加速される。
一段と細った部分のR(抵抗値)はさらに上がる。
そしてこの悪循環により、破滅に向かって容赦なく加速のアクセルが踏まれる。
そしてついには断線・ご臨終となる。
ヒーターは全長にわたって完全均一ではないため、全体が平均して蒸発するわけではない。
不純物や材料のムラ、傷などがあると、その部分の抵抗値が高くなり、発熱温度が高くなる。
その部分は他の部分よりも早く発熱体の蒸発が進むため、さらに細くなって抵抗値が上がる。
オームの法則「I=V/R」。
電流値Iが一定ということは、抵抗値Rが高くなれば、点火電圧Vが比例して上がることになる。
この動作を自動的に行うのが「定電流点火」である。
そうでないものは、定電流点火とは呼ばない。
たとえば801A
いま、定電流点火中であったとしよう。
そのとき、801A(健全時)のヒーター電圧は7.5Vであったとする(このときの電流は設定された所定の値)。
さて、そのヒーターが経時消耗により抵抗値が10%増加したとする。
そうなった場合、定電流点火回路は、801Aのヒーター電圧を自動的に8.25Vに上昇させる。
当たり前の「オームの法則」であり、ヒーター電圧を8.25Vに上げなければ、所定の電流値を保つことはできない(ヒーターの電気抵抗の高温時の温度係数の変化を考慮した厳密な話は無視する)。
定電流点火回路にどのような仕掛けがあっても一切関係なく、801Aのヒーター電圧は自動的に8.25Vに上昇する。
逆に、自動的に8.25Vに上昇しなければ、それは「定電流点火」とは呼ばない。
801Aのヒーターに流れる電流と、ヒーターの両端子(ピン)にかかる電圧、それとヒーターの両端子間の抵抗、の3つのパラメーターのみで決まる「オームの法則」である。
リニアに変化しなければ「定電流点火」とは呼ばない
「ヒーターの抵抗が高くなっても、どんどん危険な状態へと進行することは定電流回路が抑制する」といったような記事も見受けられるが意味不明である。
もし、何らかの電圧制限や電流制限を自動的に行うような回路のことを指しているのであれば、過大電流や過大電圧の制限なら理解できるが、そうでなければ「定電流点火」という呼称そのものが不適当で紛らわしい。
電流・電圧の変化の実体を表す適当な呼称を考えるべきである。
その前に、そういった直流電源の、電流・電圧がどのように変化するのか、また、そのような特性を持たせた直流電源回路がなぜ必要なのか、その点を説明することが先決だろう。
元来真空管のヒーター規格は「電圧」指定
定電流点火では、ヒーターの抵抗値が10%増加すれば、健全時の10Vは11Vに、健全時の7.5Vは8.25Vに自動的に上昇する。
ほとんどの管球アンプ愛好家は、真空管をいたわる気持ちを持っている。
そういったファンが、「だいぶ使い込んだ球だから」という理由で、たとえば211を11Vで、また801Aを8.25Vのフィラメント電圧で点火するだろうか?
これが「定電流点火」では自動的にそうなる。
たとえば、そろそろ寿命が近づいてエミッションが低下した球があるとする。
その球のヒーター電圧を上げてエミッションを稼いだら、音が大きくなり音質もよくなった(以前の状態に戻った)、ということはある。
戦前のラジオ受信機などでは、とりあえずの延命策として、電源トランスのタップを100Vから90Vに切り替えて、出力電圧を上昇させるなどの無茶をやっていた。
当ブログ内のカテゴリー「いとし子」の「爺様の古ラジオ」のラジオも、最初に蓋を開けたらヒューズが90Vタップに入っていた。
それを見て、思わずニヤッとしたものである。


<写真6:「爺様の古ラジオ」のシャーシと電源トランスのAC電圧切り替え用ヒューズホルダー>
**修復前の状態。真空管トップの配線の被覆が破れている**
そもそも真空管のフィラメントやヒータ―の規格は、「印加電圧」によって定められている。
801A(VT-62)のフィラメントには7.5Vを印加せよ、である。
そして「7.5V供給時のフィラメント電流は(代表値として)1.25Aである」との規格である。
801A(VT-62)のフィラメントには1.25Aを流せ、といっているわけではない。
定電流点火、すなわち常に「1.25A」を流す電源を使い、R社の801Aと、H社の801Aと、T社の801Aとを、順に挿し換えたとしよう。
この3本すべてのフィラメントの両端電圧が7.5Vを指す、と考えている方がおられるかもしれないが、各社揃って、それほどの品質管理をやることは不可能だろう。
7.5V時には1.25A、逆の1.25A時には7.5V?
直熱管であれ傍熱管であれ、なるべく少ない電力で、カソードから十分なエミッションを得るのは容易ではなかった。
各メーカーは、その材料の開発に鎬を削ってきた。
真空管開発史は、優秀なエミッションが得られるカソード材料の開発史でもあった。
タングステン、トリエーテッド・タングステン、酸化皮膜等々。
合金材料や化学物質など、金属や化学の技術を総動員してカソードは作られている。
要するにカソードの材料や製造法は、当時の各メーカーの企業秘密であり、トップシークレットであったはずである。
定電流点火の最適電流値はどこにある
私たちが使う真空管は、メーカーも違えば時代も違う。
7.5V印加時には1.25Aきっかり、逆に1.25Aを流せば7.5Vきっかり、などはあり得ないだろう。
1.25Aの定電流点火によるR社の801Aのフィラメント電圧は8.0Vであり、H社は7.0Vであるかもしれない。
8.0Vなどの電圧で点火させるのは勘弁願いたいが、定電流点火にこだわるならしかたがない。
それが「オームの法則」である。
(ここは大変重要なことです)
真空管製造メーカーは、規定の「電圧」をヒーターに印加した時に、規定のエミッションが得られるよう、ヒーターの作りを調整しているはずである。 (規定の「エミッション」が得られるよう、であり、規定の「電流」が得られるよう、ではないことが重要ポイント)
さて、このことから、定電流点火における個々の真空管の最適電流値を決定すること自体が不可能であることが分かると思う。
「定電流点火は音がよい」は「真」か
定電流点火は、フィラメントには非情である。
この方式がフィラメントの寿命を延ばすことなどあり得ない。
それでも音響的な優位性があるのであれば、説として納得もできるが、その論拠も仮説も聞かれない。
説明がないのは当然だと思う。
フィラメント点火の意味は、フィラメントを熱電子が盛んに飛び出す温度に加熱するための単純な電気加熱である。
定電圧点火すれば、たとえ電灯線のAC100Vが大幅に変動したとしても、フィラメントの電圧は一定に保たれる。
それはすなわち、フィラメントの電流も常に一定に保たれることを意味する。
健全なフィラメントを、定電圧で加熱するのである。
フィラメントが健全であるかぎり、その電流が一定であるのは当然である。
つまり定電圧点火においても、フィラメントには定電流が流れる。
1日、1週間、1ヶ月・・・、フィラメントが健全であるかぎり、それを定電圧で加熱しているかぎり、フィラメントには常に一定の定電流が流れ続ける。
これも当たり前の話である。
電流が変動する要素など、フィラメントに異常が起こらないかぎりはない。
逆に定電流を流せばフィラメントの両端には定電圧が発生する。
この場合は「逆も真なり」、である。
定電圧点火と定電流点火。
正常なフィラメントであるかぎり、フィラメントにはどちらの方式でも同じ定電圧が発生し、定電流が流れる。
このように考えてもなお、両者に音の違いが出るのだろうか。
あるいは信号増幅の動作の影響で、定電圧点火の場合は、フィラメント電流が変化するとでもいうのだろうか。
直流電源部の作り方によっては、ノイズが出るとかノイズを拾うとか、また直流の質が悪いとかにより、音質に影響を与えることもあるだろう。
しかしここでは音響的にハイエンドの領域の話しをしている。
ノイズや低品質による影響が出る電源装置などは俎上に無く、論外である。
直流電源装置の「作り」に起因するものでなく、定電圧と定電流そのものの違いにより、果たして音に違いが生じるか?
両方式による真空管内の電子の流れや、フィラメントを加熱する電流そのものに、どのような違いがあるのか私には理解できない。
当然ながら両者の直流電源装置には、必ず回路や構造、作りなどの違いがあり、そこには音に何らかの影響を与えるファクターがあってもおかしくはない。
その定電圧/定電流に関係ない部分の影響を、いい音・悪い音、人によって様々に感じるのかもしれない。
どちらにせよ「最終アンプ」には、「フィラメントはこれで安心」の3端子レギュレーターを採用している。
そのご利益なのか20余年、今も毎日「いい音」で、「ご長寿フィラメント」が元気に輝いている。
(「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質」 おわり)
最終アンプ(6)ヒーター点火の良し悪し話し [原器を目指した「最終アンプ」]
お知らせ
当ページへのご訪問、まことにありがとうございます。
申し訳ございませんが、当ページはリニューアルして、下記の2つに分割いたしました。
①:「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)
http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13
②:「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)
http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14
元の「最終アンプ」(6)のページが、かなりの長文になってしまったため、全体を整理した上で2つに分け、加筆再構成いたしました。
まことに申し訳ございませんが、当ページをご訪問の方は、上記①②のページを、再度ご訪問くださるよう、お願い申し上げます。
お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------------------------------------------------------------
参考までに上記、『「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質』 と、『「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火』 に掲載した写真のいくつかを、ここに転載しておきます。


<電源ONのラッシュカレントで光る不良MT管「ピカ球」と、昔、各種点火法などを試みて、いじり倒したWE300Bsアンプ>
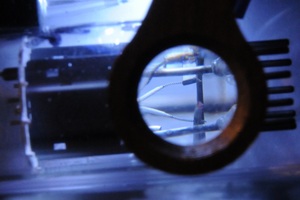
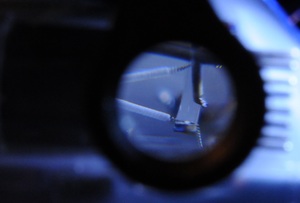
<電源ON時にピカーっと光るMT管の不良部分。左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りが雑になってきたのだろう。球はいずれも欧州ブランド印のECC82>


<「最終アンプ」の俯瞰とシャシー内部。シャシー内部の右側面に、厚めのアルミ板を設けて、ドライバー管と出力管それぞれのフィラメント点火電源部が組まれている。茶色の電解コンデンサーの辺りが3端子レギュレータ部で、タイマーリレーの右下がブリッジ整流部である>
a.jpg)
<3端子レギュレーター部のクローズアップ。左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用>
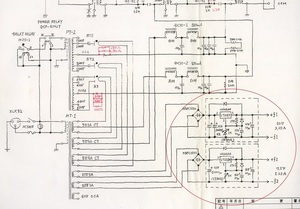
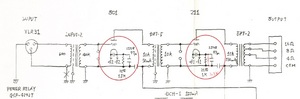
<「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図。3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない。この電源部のみに電解コンデンサーが使われている。他はすべてフィルム系コンデンサーである>
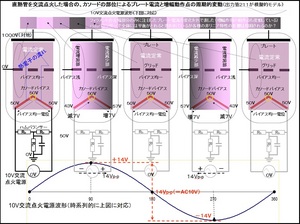
<直熱管を交流点火した場合の電子流の変動の状況。フィラメントの長さ方向の電位の傾きに注目し、交流波形の時間軸を追って、順に電子の流れの変化を見る。思考実験のための図>
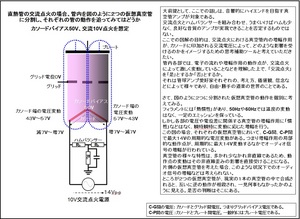
<中央に仮想の仕切り板を入れ、2つの仮想真空管に分割する。管内の電子流の動きを考え易くするため、模式図上、フィラメントの中央から左右対称の位置で2つの仮想真空管に分割したと考える。思考実験のための図>

<真空管は生まれながらに「直流っ子」。1925年製 米国Atwater Kent社の高級ラジオModel 20C。使われている真空管はトリエーテッド・タングステン・フィラメントの01系。フィラメント電圧は直流4V~6Vあたりをレオスタットで調整しながら使う。受信感度や受信調整、音量などの調整は真空管のフィラメントの電圧を上げ下げして行う豪快で大胆な方法>
これらの記事の本文につきましては、申し訳ございませんが、
「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)
http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13
および
「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)
http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14
のページをご訪問くださるよう、お願い申し上げます。
--------------------------------------------------------------------------
口伝(2-1)補足ルビジウム原子発振器もどんどんズレる [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]
前回の日記、「口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力」の補足を、ここにしるしておきます。
その前にちょっと余談を
前回の日記について、このようなお話を頂きました。
この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。
またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。
まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。
こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。
『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。
高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』
頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。
『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』
と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。
さて今日の日記の本題、前回の補足
前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。
以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。
――――――――――――――――――――――――――――――――
・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。
富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。
私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。
一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。
なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199
――――――――――――――――――――――――――――――――
さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。
その図10はこのようなデーターである。
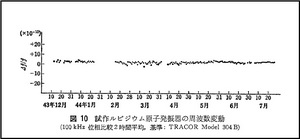
<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>
**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**
奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。
「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。
論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。
「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」
つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。
比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ
そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。
このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。
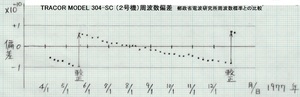
<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>
この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。
図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。
図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。
ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。
テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。
ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない
この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。
ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。
ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。
そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。
昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。
ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく
それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。
そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。
この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。
参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが
テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。
304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。
ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。
304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。
Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。
このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。
この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。
TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。
そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。
今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。
(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)
その前にちょっと余談を
前回の日記について、このようなお話を頂きました。
この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。
またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。
まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。
こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。
『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。
高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』
頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。
『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』
と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。
さて今日の日記の本題、前回の補足
前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。
以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。
――――――――――――――――――――――――――――――――
・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。
富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。
私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。
一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。
なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199
――――――――――――――――――――――――――――――――
さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。
その図10はこのようなデーターである。
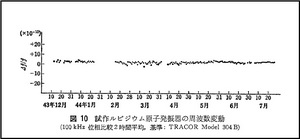
<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>
**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**
奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。
「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。
論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。
「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」
つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。
比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ
そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。
このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。
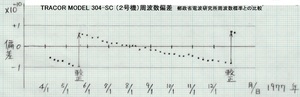
<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>
この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。
図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。
図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。
ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。
テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。
ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない
この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。
ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。
ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。
そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。
昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。
ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく
それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。
そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。
この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。
参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが
テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。
304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。
ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。
304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。
Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。
このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。
この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。
TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。
そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。
今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。
(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)
口伝(2)ルビジウム原子発振器 ~されどジッターには無力 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]
口伝 オーディオ 萬之事
( くでん オーディオ よろずのこと )
マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」
ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。
細かな周波数変動も常に発生している(図6)。
デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。
音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。
この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。
そういった部分に余計なコストをかける必要はない。
この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。
実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。
これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。
ルビジウム原子発振器神話
以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。
しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。
いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。
「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。
そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。
前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。
そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。
驚異的周波数安定度も「平均」しての話
「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。
短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。
従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。
ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。
区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。
ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。
それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。
この「平均」という点をスルーしてはいけない。
ルビジウム原子の法力もジッターには無力
さらには、時間的にもっと細かい変動もある。
「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。
この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。
昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。
つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。
マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。
まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。
特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。
米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書
日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。
すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。
「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。
このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。
そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。
だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。
それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。
4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる
TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。
RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。
今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。
その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。
この図で納得-ルビジウムにロックオン!
「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。
そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。
取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。
もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。
しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。
では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。
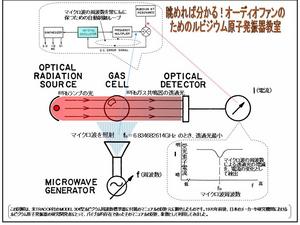
<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>
**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**
いきなりRbOscの核心に迫る
細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。
この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。
次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。
①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。
②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。
③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。
④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。
⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。
ここが最重要
さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。
この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。
⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。
foにロックオン
核心部の秘密に到達した。
次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。
⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。
⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。
⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。
⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。
⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。
⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。
崩れた神話
さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。
ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。
さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。
それだからこそ、今日の日記の冒頭の、
「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」
と考えるわけである。
水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。
冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。
ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面
TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。
先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。
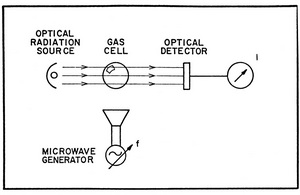
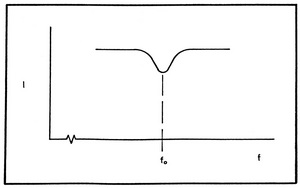

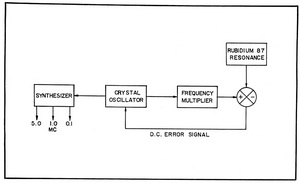
<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>
**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**
foにロックオンする仕掛け
先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。
どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。
つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。
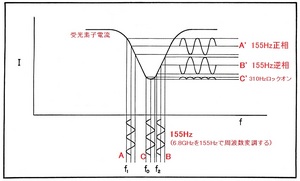
<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>
**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**
その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。
項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。
イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。
ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。
ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。
ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。
「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。
この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。
図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。
追補-ルビジウム原子の「法力」を解く
「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。
RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。
容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。
実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。
私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。
なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。
最高に分かり易いRbOscの教科書あり
この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。
テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。
富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。
私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。
一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。
なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199
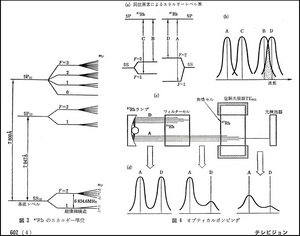
<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>
**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**
以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。
自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。
図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。
エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。
原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。
ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。
励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。
これの繰り返しとなる。
図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。
そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。
さて、いよいよ「法力」の核心部分である。
「法力」のキーワードは2つ。
「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。
それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。
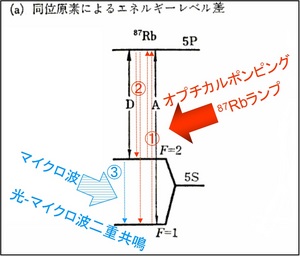
<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>
**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**
a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。
b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。
その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。
そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。
c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。
これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。
d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。
e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。
f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。
g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。
RbOscにはいくつかの変動要素がある
ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。
水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。
地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。
それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。
ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。
安定度の質は装置によってピンキリ
昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。
大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。
Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。
そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。
名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。
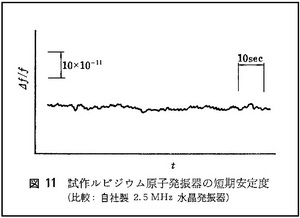
<図6:RbOscの短期変動の実測データ>
**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**
図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。
この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。
「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。
経年周波数ドリフト
たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。
世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。
たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。
そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。
現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。
その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。
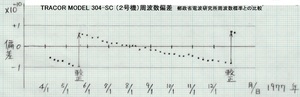 <図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**
<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**
古い装置であるが、その実測データが図7である。
この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。
図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。
広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。
そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。
私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)
デジタル分野にも風説はある
アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。
ところがデジタルにもそれがある。
一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。
ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力
RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。
水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。
家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。
さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。
その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。
簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。
当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。
メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。
つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)
ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。
少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。
このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。
とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。
手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。
ルビジウムより水晶?
今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。
しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。
このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。
おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。
その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。
RbOscの思い出
RbOscについては、いろいろな思い出がある。
出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。
米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。
現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。
日本初である。
その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。
分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。
そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。
また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。
いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。
あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。
(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルオーディオの風説第1号はなに?
CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。
その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。
一般の人にとって、この話には説得力がある。
「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。
それがデジタル方式の優れた特長である。」
私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。
このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。
どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。
繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。
しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。
ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。
もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。
その結果を知りたいところである。
アナログ・アナクロ親父の夢
ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。
この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。
この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。
部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。
が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。
近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。
(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)
( くでん オーディオ よろずのこと )
マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」
ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。
細かな周波数変動も常に発生している(図6)。
デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。
音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。
この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。
そういった部分に余計なコストをかける必要はない。
この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。
実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。
これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。
ルビジウム原子発振器神話
以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。
しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。
いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。
「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。
そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。
前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。
そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。
驚異的周波数安定度も「平均」しての話
「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。
短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。
従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。
ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。
区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。
ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。
それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。
この「平均」という点をスルーしてはいけない。
ルビジウム原子の法力もジッターには無力
さらには、時間的にもっと細かい変動もある。
「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。
この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。
昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。
つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。
マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。
まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。
特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。
米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書
日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。
すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。
「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。
このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。
そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。
だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。
それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。
4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる
TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。
RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。
今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。
その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。
この図で納得-ルビジウムにロックオン!
「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。
そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。
取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。
もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。
しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。
では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。
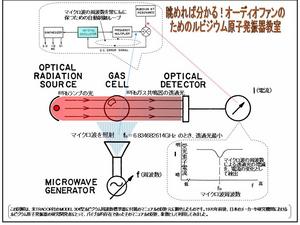
<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>
**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**
いきなりRbOscの核心に迫る
細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。
この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。
次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。
①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。
②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。
③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。
④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。
⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。
ここが最重要
さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。
この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。
⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。
foにロックオン
核心部の秘密に到達した。
次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。
⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。
⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。
⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。
⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。
⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。
⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。
崩れた神話
さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。
ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。
さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。
それだからこそ、今日の日記の冒頭の、
「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」
と考えるわけである。
水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。
冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。
ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面
TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。
先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。
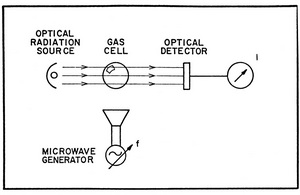
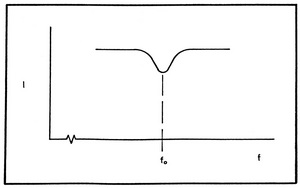

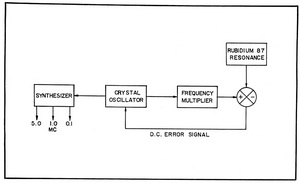
<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>
**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**
foにロックオンする仕掛け
先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。
どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。
つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。
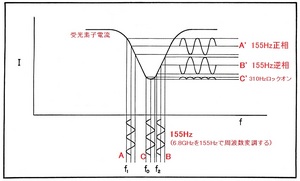
<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>
**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**
その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。
項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。
イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。
ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。
ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。
ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。
「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。
この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。
図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。
追補-ルビジウム原子の「法力」を解く
「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。
RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。
容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。
実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。
私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。
なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。
最高に分かり易いRbOscの教科書あり
この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。
テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。
富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。
私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。
一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。
なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199
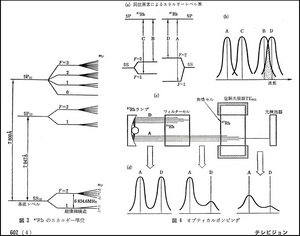
<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>
**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**
以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。
自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。
図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。
エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。
原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。
ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。
励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。
これの繰り返しとなる。
図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。
そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。
さて、いよいよ「法力」の核心部分である。
「法力」のキーワードは2つ。
「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。
それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。
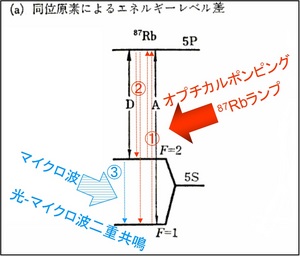
<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>
**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**
a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。
b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。
その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。
そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。
c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。
これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。
d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。
e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。
f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。
g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。
RbOscにはいくつかの変動要素がある
ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。
水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。
地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。
それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。
ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。
安定度の質は装置によってピンキリ
昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。
大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。
Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。
そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。
名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。
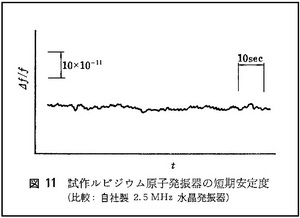
<図6:RbOscの短期変動の実測データ>
**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**
図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。
この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。
「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。
経年周波数ドリフト
たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。
世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。
たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。
そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。
現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。
その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。
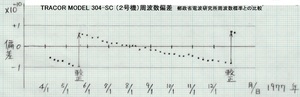 <図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**
<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**古い装置であるが、その実測データが図7である。
この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。
図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。
広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。
そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。
私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)
デジタル分野にも風説はある
アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。
ところがデジタルにもそれがある。
一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。
ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力
RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。
水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。
家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。
さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。
その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。
簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。
当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。
メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。
つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)
ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。
少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。
このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。
とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。
手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。
ルビジウムより水晶?
今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。
しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。
このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。
おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。
その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。
RbOscの思い出
RbOscについては、いろいろな思い出がある。
出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。
米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。
現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。
日本初である。
その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。
分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。
そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。
また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。
いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。
あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。
(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルオーディオの風説第1号はなに?
CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。
その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。
一般の人にとって、この話には説得力がある。
「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。
それがデジタル方式の優れた特長である。」
私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。
このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。
どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。
繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。
しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。
ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。
もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。
その結果を知りたいところである。
アナログ・アナクロ親父の夢
ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。
この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。
この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。
部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。
が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。
近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。
(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)
口伝(1)オーディオ事始 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]
口伝 オーディオ 萬之事
( くでん オーディオ よろずのこと )
この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。
蛙の卵
社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。
理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。
元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。
最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。
STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。
一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>
**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**
最良の選択STAXイヤースピーカー
彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。
一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。
イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。
コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。
この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>
**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**
音源はパソコンのみ
音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。
もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。
目覚め
息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。
彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。
何枚かを聴かせた。
また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。
当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。
聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。
まあ、そう思うのが普通だろう。
原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。
息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。
しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。
そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。
口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。
かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。
初めてのレコードプレーヤー
アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。
調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。
そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。
とりあえずどこにも問題はなさそうである。
カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>
**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**
もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。
KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。
眠ってしまいそうなときは、これに限る。
KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。
KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>
**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>
**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**
初めてのカートリッジDL-103
彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。
カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。
その能書きとは。
DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。
父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。
といったような話である。
さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。
口伝
口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。
秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。
昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。
ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。
当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。
ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。
レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと
おそらく初体験のレコードプレーヤー。
オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。
が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。
まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。
オーディオ道楽は一生もの
音楽が好きでオーディオにも興味を持った。
そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。
そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。
山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。
若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。
歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。
そこが面白い。
それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。
オーディオは感性・感受性に依存する
また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。
「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。
また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。
要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。
これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。
「いい音」の普遍的部分は9割超か
要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。
念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。
古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。
試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。
その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。
オーディオ諸説の取捨選択
さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。
ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。
そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。
オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。
あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。
こういった話を鵜呑みにしてはいけない。
デジタル分野にも風説はある
アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。
ところがデジタルにもそれがある。
一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。
ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力
RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。
水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。
家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。
さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。
その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。
簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。
当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。
メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。
つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)
ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。
少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。
このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。
とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。
手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。
ルビジウムより水晶?
今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。
しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。
このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。
おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。
その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。
RbOscの思い出
RbOscについては、いろいろな思い出がある。
出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。
米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。
現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。
日本初である。
その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。
分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。
そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。
また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。
いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。
あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。
「音のいいケーブル」?
さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。
たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。
この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。
この話はつぎのように言い替えなければならない。
「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。
このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。
つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。
自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。
ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。
また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。
いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。
オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは
オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。
「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。
「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。
「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。
[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。
この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。
簡単な一例を図1に書いてみた。
先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。
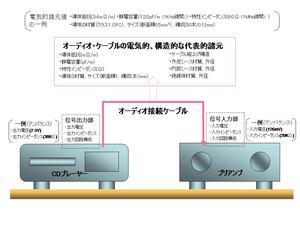
<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>
**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**
ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり
CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。
信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。
「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。
図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。
それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。
ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。
なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。
・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)
・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け
ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?
「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。
たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。
「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。
しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。
①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω
②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω
ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。
これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。
また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。
以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。
ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。
各コンポーネントの選択
意味あり一点豪華主義
さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。
そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。
最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。
それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。
「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。
日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。
富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。
だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。
新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。
C-280Vいま生産すれば価格は?
Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。
1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。
私は今現在、その一代前のC-280を使っている。
過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。
なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。
さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。
私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。
事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。
「一生もの」を中古でget
その後彼らはこのC-280Vをgetすることになるが、これをシステムのセンターに据えれば、後々まで長く、全幅の信頼を寄せる「不動のセンター」として愛用することができるだろう。
そして数年後、「卵」から「おたまじゃくし」の期間を経て、「子がえる」になったかえるの子は、口伝の教示に沿うようなコンポーネントをgetしていった。
その結果、現在はこのような状況になっている。
すべては中古品であるが、幸い、怪しそうなコンポーネントはないようだ。
中古品にはリスクがある。
それを承知の上で、「目利き」の能力も必要であり、事前のチェックも十分しておかねばならない。
入門者にはとても難しいところであり、経験者の助言・助力が必要だろう。

<写真6:KP-9010に慣れた後にgetしたTechnicsのターンテーブル>
**これも親父に似ているが、総合的に見て、コスト/パフォーマンス上、これ以上のものを探し出すのはむつかしい。彼もKP-9010は、居眠り対策に欠かせないらしく、反対側に置いてあるとのこと**

<写真7:かえるの子が数年間で構築した主要システム>
**同じ歳頃の私の時代とは隔世の感がある。どれも古い中古であるが、第一級の名機であり、末永い使用に耐えるだろう。またデジタル機器を除けば、買い換える必要性も起こらないだろう**
スピーカーは父と同じ「実証済」のALTEC MODEL19である。
入手した価格で、これ以上のスピーカーは簡単には見つけられないため、「まねしてる」と思われてもやむを得ない。
REVOX B77は4トラックであり、私の貸し出しである。
デジタル機器はまだまだ発展途上
だいたい一通り揃ったようであるが、「一生もの」を選択できないコンポーネントがあることに注意しておく必要がある。
デジタル機器である。
デジタル処理のデバイスも、それらのデバイスの応用技術も、今後の進化は計り知れない。
サンプリング周波数44.1KHz、量子化ビット数16bitの普通のCDの再生装置でさえ油断はできない。
CDが市場に登場したのは1982年である。
30年以上も経っているが、それを再生するための手法は、新しいアプローチがまだまだ残されている。
ということから、「デジタル機器は発展途上」との認識のもと、コンポーネントの選択をしなければならない。
さてさて、オーディオの「よろずの事」を口伝しようにも、あまりにも範囲が広く、奥も深いため、途方にくれる思いである。
とても「体系的に」など、きちんと順序だてた話はできないが、思いつくまま、ぼつぼつとやっていきたい。
えっ、ケーブルの接続はバランスかアンバランスかって?
そうかそうか、C-280Vはバランス入出力が充実してるからね。
この問題は簡単明瞭だけど、今日の最後の話として、はっきりさせておこう。
バランス接続できる個所はバランス接続。
バランス接続できない個所はアンバランス接続。
このことは当たり前の話であり、オーディオ信号の「信号伝送」は、バランス伝送が基本中の基本。
RCAタイプのピンジャックなどのアンバランス入出力は、短い距離の伝送など、バランス伝送でなくても、あまり問題が発生しない場合の「簡易伝送法」である。
だから状況に応じて、よかれと思うやり方で接続すればいい。
えっ、なぜバランス伝送が基本中の基本なのか、って?
これも理屈は簡単だけれど、続きはまた、ということにして、なにか一曲聴かせてほしいな。
(口伝(1)オーディオ事始 おわり)
( くでん オーディオ よろずのこと )
この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。
蛙の卵
社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。
理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。
元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。
最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。
STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。
一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>
**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**
最良の選択STAXイヤースピーカー
彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。
一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。
イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。
コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。
この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>
**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**
音源はパソコンのみ
音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。
もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。
目覚め
息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。
彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。
何枚かを聴かせた。
また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。
当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。
聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。
まあ、そう思うのが普通だろう。
原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。
息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。
しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。
そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。
口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。
かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。
初めてのレコードプレーヤー
アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。
調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。
そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。
とりあえずどこにも問題はなさそうである。
カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>
**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**
もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。
KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。
眠ってしまいそうなときは、これに限る。
KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。
KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>
**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>
**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**
初めてのカートリッジDL-103
彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。
カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。
その能書きとは。
DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。
父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。
といったような話である。
さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。
口伝
口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。
秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。
昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。
ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。
当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。
ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。
レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと
おそらく初体験のレコードプレーヤー。
オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。
が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。
まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。
オーディオ道楽は一生もの
音楽が好きでオーディオにも興味を持った。
そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。
そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。
山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。
若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。
歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。
そこが面白い。
それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。
オーディオは感性・感受性に依存する
また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。
「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。
また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。
要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。
これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。
「いい音」の普遍的部分は9割超か
要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。
念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。
古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。
試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。
その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。
オーディオ諸説の取捨選択
さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。
ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。
そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。
オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。
あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。
こういった話を鵜呑みにしてはいけない。
デジタル分野にも風説はある
アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。
ところがデジタルにもそれがある。
一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。
ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力
RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。
水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。
家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。
さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。
その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。
簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。
当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。
メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。
つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)
ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。
少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。
このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。
とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。
手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。
ルビジウムより水晶?
今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。
しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。
このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。
おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。
その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。
RbOscの思い出
RbOscについては、いろいろな思い出がある。
出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。
米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。
現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。
日本初である。
その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。
分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。
そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。
また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。
いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。
あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。
「音のいいケーブル」?
さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。
たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。
この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。
この話はつぎのように言い替えなければならない。
「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。
このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。
つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。
自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。
ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。
また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。
いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。
オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは
オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。
「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。
「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。
「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。
[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。
この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。
簡単な一例を図1に書いてみた。
先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。
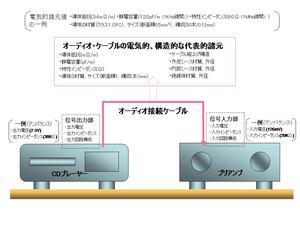
<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>
**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**
ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり
CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。
信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。
「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。
図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。
それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。
ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。
なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。
・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)
・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け
ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?
「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。
たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。
「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。
しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。
①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω
②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω
ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。
これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。
また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。
以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。
ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。
各コンポーネントの選択
意味あり一点豪華主義
さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。
そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。
最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。
それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。
「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。
日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。
富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。
だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。
新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。
C-280Vいま生産すれば価格は?
Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。
1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。
私は今現在、その一代前のC-280を使っている。
過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。
なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。
さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。
私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。
事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。
「一生もの」を中古でget
その後彼らはこのC-280Vをgetすることになるが、これをシステムのセンターに据えれば、後々まで長く、全幅の信頼を寄せる「不動のセンター」として愛用することができるだろう。
そして数年後、「卵」から「おたまじゃくし」の期間を経て、「子がえる」になったかえるの子は、口伝の教示に沿うようなコンポーネントをgetしていった。
その結果、現在はこのような状況になっている。
すべては中古品であるが、幸い、怪しそうなコンポーネントはないようだ。
中古品にはリスクがある。
それを承知の上で、「目利き」の能力も必要であり、事前のチェックも十分しておかねばならない。
入門者にはとても難しいところであり、経験者の助言・助力が必要だろう。

<写真6:KP-9010に慣れた後にgetしたTechnicsのターンテーブル>
**これも親父に似ているが、総合的に見て、コスト/パフォーマンス上、これ以上のものを探し出すのはむつかしい。彼もKP-9010は、居眠り対策に欠かせないらしく、反対側に置いてあるとのこと**

<写真7:かえるの子が数年間で構築した主要システム>
**同じ歳頃の私の時代とは隔世の感がある。どれも古い中古であるが、第一級の名機であり、末永い使用に耐えるだろう。またデジタル機器を除けば、買い換える必要性も起こらないだろう**
スピーカーは父と同じ「実証済」のALTEC MODEL19である。
入手した価格で、これ以上のスピーカーは簡単には見つけられないため、「まねしてる」と思われてもやむを得ない。
REVOX B77は4トラックであり、私の貸し出しである。
デジタル機器はまだまだ発展途上
だいたい一通り揃ったようであるが、「一生もの」を選択できないコンポーネントがあることに注意しておく必要がある。
デジタル機器である。
デジタル処理のデバイスも、それらのデバイスの応用技術も、今後の進化は計り知れない。
サンプリング周波数44.1KHz、量子化ビット数16bitの普通のCDの再生装置でさえ油断はできない。
CDが市場に登場したのは1982年である。
30年以上も経っているが、それを再生するための手法は、新しいアプローチがまだまだ残されている。
ということから、「デジタル機器は発展途上」との認識のもと、コンポーネントの選択をしなければならない。
さてさて、オーディオの「よろずの事」を口伝しようにも、あまりにも範囲が広く、奥も深いため、途方にくれる思いである。
とても「体系的に」など、きちんと順序だてた話はできないが、思いつくまま、ぼつぼつとやっていきたい。
えっ、ケーブルの接続はバランスかアンバランスかって?
そうかそうか、C-280Vはバランス入出力が充実してるからね。
この問題は簡単明瞭だけど、今日の最後の話として、はっきりさせておこう。
バランス接続できる個所はバランス接続。
バランス接続できない個所はアンバランス接続。
このことは当たり前の話であり、オーディオ信号の「信号伝送」は、バランス伝送が基本中の基本。
RCAタイプのピンジャックなどのアンバランス入出力は、短い距離の伝送など、バランス伝送でなくても、あまり問題が発生しない場合の「簡易伝送法」である。
だから状況に応じて、よかれと思うやり方で接続すればいい。
えっ、なぜバランス伝送が基本中の基本なのか、って?
これも理屈は簡単だけれど、続きはまた、ということにして、なにか一曲聴かせてほしいな。
(口伝(1)オーディオ事始 おわり)
いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ [オーディオのいとし子たち]
新春ブログ綴り初め
メーカーは違うが左右2つのラジオ、35年の歳月を隔てて、同じ男が設計し商品化した。
この2つに共通するもの、デザイン、音作り、設計のポリシー、製品作りの理念まで、オーディオ界激動の時代を越え、また彼の生涯を通して少しも揺るぎがない。
男の名はHenry Kloss(ヘンリー・クロース)。
1929年米国 Altoona、Pennsylvaniaで生まれ、2002年Cambridge、Massachusettsで没。
エミー賞の最初の受賞者の一人であり、CEA(全米家電協会)の殿堂入りを果たしたオーディオ界の巨人である。
形に惹かれてgetした2つのラジオ
姿格好に強く惹かれるものがあり、早速手に入れたFMラジオ。
入手当時は、そのラジオからオーディオの歴史の表紙を飾るに相応しい、巨人のドラマを聞けるなど、知る由もなかった。
左側のラジオ、KLH Model 21の裏側の写真4、5には、キャビネットに小さな枕のようなものが詰め込まれている(枕の中身はグラスウール)。
これを見て、AR社(Acoustic Research社)のアコースティック・サスペンション方式による小型スピーカーシステムを連想された方は、かなり年季の入ったオーディオ愛好家とお見受けする。
実はそのはず、彼はAR社設立のメンバーであり、そこで独創的なスピーカーシステムの開発を行っている。

<写真1:KLH Model 21(左)とTivoli Model One(右)>
**オーディオ界の巨人ヘンリー・クロースが作った卓上ラジオの一例。KLH Model 21は1965年、Tivoli Model Oneは2000年の発売。バックのSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーとも関連がある**
オーディオの開拓者ヘンリー・クロース
写真1の左は、「KLH社 Model Twenty-One」という1965年に発売された卓上FMラジオである。
私はこのラジオが、オーディオ界の巨人によって作られたことなど、何一つ知らなかった。
この姿を何かの写真で見た瞬間、強く惹かれるものがあり、すぐさまeBayで探しあてた。
もう忘れてしまった十何年も前のことであるが、このラジオの音の心地よさに驚いたものである。
この手のものでは初めて耳にするような、中低音を効かせた余裕たっぷりの鳴りっぷりは、日本の卓上ラジオでは決して聞くことができない。
家電の大型量販店を見て回れば分かるが、そもそも「音質を重視した、きちんとした作りの卓上ラジオ」など、ここ10年や20年来、国産品で見かけたことはない。
ましてや、木製キャビネットを使ってアコースティック・サスペンション方式や、バスレフ方式を採用するなど(たとえ真似事であっても)、望むべくもない。
また写真の背景に置いたSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーは、ダテに置いてあるわけではなく、なんと驚いたことに、このFMラジオと関連があったのだ。

<写真2:KLH Model 21 FM卓上ラジオ>
**キャビネットは14mm厚ほどのウオルナットベニア材+チップ圧縮材で、がっちり作られている。FM専用機。高域と低域のトーンコントロールが可能**
Henry Klossはヘンリー・クロスと記される場合が多いが、「クロース」と「o」を伸ばすのが正しいそうである。
KLH Model 21の前面パネル、水色のバーのすぐ下には、「MODEL TWENTY-ONE・CAMBRIDGE MASSACHUSETTS」と書かれている。
このことは、晩年に至るまでの長い期間、活躍の本拠地がケンブリッジであったことを物語っている。
写真右の卓上AM-FMラジオ「Tivoli社 Model One」は、Tivoli社を共同で設立した彼が、晩年近くの70歳になった2000年の作である。
KLH Model 21から35年、私にはこのModel Oneの姿にも、21の場合と同じ、私を惹きつけるオーラが見えた。

<写真3:Tivoli社 Model One FM-AMラジオ>
**Tivoli社の設立に参画したヘンリー・クロース70歳の第一作。今現在も市場流通機種。Tivoli社の製品群には、彼流の品質とデザインの、各種卓上オーディオ機器がラインアップされている**
巨人の偉業AR社時代
オーディオ時代到来の序曲
ヘンリー・クロースの数ある業績のなかで、日本のオーディオ愛好家にもっとも馴染み深いのは、「AR」、Acoustic Research社時代に開発した「アコースティック・サスペンション方式」による小型スピーカーシステムだと思われる。
1950年代、ヘンリー・クロースはマサチューセッツ工科大学(MIT)の学生であった。
オーディオに興味を持ったのはその頃で、学生仲間とスピーカーの研究や製作を行ったと伝えられている。
そして大学の仲間や、エドウィン・アームストロング(*注)などの協力もあり、MITの先輩であったE.Villchur(エドガー・ウィルシャー)を中心に、1954年、AR社を共同で設立した。
小型(ブックシェルフ型)でも豊かな低音を響かせるARの初代のスピーカーは、完全密閉型エアサスペンション方式のAR-1(1956年)であった。
56年は、米RCAビクターが45-45方式のステレオレコードの発表とデモを行った年である(商品化は1958年)。
ただし同方式の最初の考案者はRCAではなく、1931年に英EMIが英国特許を取得している。
時はそういった時代背景にあり、まさにオーディオ時代到来の序曲が鳴り始めていた。
そして、アコースティック・サスペンション方式を採用したAR-3a(1966年発売)は、日本でも多くのファンを獲得し、ジャズトランペッターのマイルズ・デイビスも愛用、とのうたい文句などもあって大ヒット作となった。
*注) エドウィン・アームストロング
エドウィン・アームストロング(1890-1954)。
この男も、とんでもない巨人である。
残した業績は多岐多数にわたるが、身近で分かり易い例にはつぎのようなものがある。
・再生検波回路の発明(戦前のほとんどのラジオ受信機に採用)。
・スーパーヘテロダイン方式の発明(戦後から現在までのすべてのラジオ受信機に採用)。
・周波数変調方式の発明(すべてのFM放送、FM受信機、アナログ時代のテレビ放送と受像機の音声に採用)。
この3つだけでも、今もなお、社会に文化に、計り知れない恩恵を与え続けている。
しかしこのような、現代社会の形を創り出したといえるほど重要な公共インフラを発明した彼の晩年は、幸せではなかった。
大メーカーとの特許紛争に疲れ果て、たいへん不幸な最後であった。
ともかく偉大な巨人が、KLH Model 21を作った男と出会い、力を貸したのである。
ブックシェルフ型スピーカーを実現したアコースティック・サスペンション方式の動作原理
アコースティック・サスペンションの大まかな原理は、まず第一にfo(エフゼロ:最低共振周波数)の低いスピーカーユニットを使う。
そしてスピーカー・キャビネットを気密性の高い密閉構造にして、空気の弾性をサスペンション(スピーカーのダンパー)として利用し、さらに内部を吸音材で充填することによりスピーカーのfoの上昇を抑える、というものである。
エアサスペンション型 / アコースティック・サスペンション型
話を整理すると、foの低いスピーカーユニットを小型密閉箱に入れ、空気の弾性を低域の制動(ダンパー)に利用したスピーカーシステムを「エアサスペンション型」と呼ぶ(その「副作用」としてfoが上昇する)。
また、その内部に吸音材を詰め込んで、foの上昇を抑える効果を加えたものを「アコースティック・サスペンション型」と呼んでいる。
ちなみにAR-3aの、特に中・高音ユニットの背面には、吸音材がぎっしり詰め込まれており、写真4、5の「枕」の詰め込みは、その音作りの手法をKLH Model 21に適用した例である。

<写真4:KLH Model 21の裏ぶたを外した様子>
**キャビネット上部の空間に、吸音材がぎゅうぎゅう詰めに押し込まれている**

<写真5:取り出した吸音材>
**枕カバーのような袋に、グラスウールが詰め込まれている。おそらく経年変化で変色しており、元の色は分からない**

<写真6:キャビネット上部の空間からスピーカーを覗く>
**マグネットは四角い形状のフェライトのようである。キャビネット前面パネルは木製ではなくアルミ板である**
KLH Model 9 は世界初フルレンジ・コンデンサースピーカー!
ARを退いたヘンリー・クロースは1957年、KLH社を設立した。
オーディオ愛好家向けの、Model6(スピーカー)。
Model8(卓上FMラジオ。真空管式)。
Model 11(ポータブル・ステレオレコードプレーヤー。「スーツケース・レコードプレーヤー」とも言われ、ケースから分離して設置できる2つの音質のよいスピーカーが収納されている。1962年発売)。
この後にも次々と高品質の製品を送り出していった。
さて彼は、この期間に驚くべきスピーカーを商品化している。
「KLH Model Nine」(1960年発売)。
味も素っ気もない一連の番号だけのモデル名からは考えも及ばないが、この「9」こそ、世界初のフルレンジ・コンデンサースピーカーであった。
QUAD ESL(ESL-57)は3年ほど先行した1957年の発売であるが、本物の低音が出る、再生帯域40Hz~20KHzの全帯域型としてはModel9が世界初である。
その大きさは、STAX ELS-8Xより多少小さいが、低域(ウーハー)の発音ユニットは、片側10枚あった。
初めて目にするフルレンジ・コンデンサースピーカーの面積の大きさに、当時の人はとても驚いたに違いない。
STAX ELS-8Xの低域発音ユニットは、全域とも合わせて6枚である(発音ユニットのサイズがMolel9より大きい)。
KLHでは1960年当時、いろいろな研究や試作の結果、コンデンサースピーカーで本当の低音を再生するには、その程度の面積が必要であることが分かっていたのだと思う。
そして、スピーカーに低域の豊かさを求める彼は、QUADの後追いではなく、全帯域を実現すべく大面積型を採ったのである。
日本にもModel Nineのユーザーは存在した
「KLH Model Nine」は、当時、日本のオーディオファイルにも知れており、少なくとも2桁の台数が輸入されたのではないかと推察する。
私がまだ青年の頃であったが、そのオーナーの記事などをオーディオ誌で読んだ記憶がある。
年配のオーディオファンには、このModel9の話をご存知の方も多いのではないだろうか。
1960年にKLHが大型コンデンサースピーカーを発売した4年後、日本のオーディオ業界が世界に誇る、在りし日のSTAX工業株式会社がついにフルレンジのコンデンサースピーカーを完成し、発売した。
STAX ESS-3Aと、6Aである。
当時青年であった私は、その6Aを「STAXの館」で聴いたわけである(当ブログ「甦れSTAX ELS-8X」)。
当時のSTAXの開発・設計スタッフは、このKLH Model Nineをしっかりと研究したに違いない。
私の推測では、おそらく細部ではその「おおらかな作り」に呆気にとられたのではないかと思う。
しかしフルレンジ・コンデンサースピーカーとしての先見性や基本設計には、彼らの学ぶとことが多々あったに違いない。
私のもとで鳴っているSTAX ELS-8Xにも、KLH Model Nineを作ったヘンリー・クロースの開拓者魂の痕跡が、どこかに残されているような気がする。
オーディオ/ビジュアルの先駆者
ヘンリー・クロースの才能は、オーディオだけに留まらなかった。
テレビを大画面で観る手段がなかった時代、彼は1967年にAdvent社を設立し、3管式のプロジェクションTV「VideoBeam 1000」を開発・発売した。
この功績で彼はエミー賞の最初の受賞者の一人に輝いている。
また、Dolby Bタイプのノイズリダクション・システムの開発に貢献し、それを搭載した最初のカセットデッキを開発・発売するなど、その後のカセットデッキ全盛時代の先鞭をつけたのも彼であった。
ヘンリー・クロースはその後もいくつかの会社を立ち上げ、多岐にわたる活躍をして、その時その時に、魅力ある製品を世に送り出している。
そして2000年。
最後となるTivoli Audioの設立に参画し、数々の製品を設計・製品化することになる。
これもヘンリー・クロースの設計だった
写真3のTivoli Model One AM-FM卓上ラジオの姿格好を改めてご覧いただきたい。
これも何かの写真を見て一目惚れしてgetしたものである。
一目惚れの相手の素性を調べて、ヘンリー・クロースの作であることを知り、驚くとともに納得した。
KLH時代の全製品のデザインに共通した魅力が、50年近く経てもなお、一層洗練された形で継承されている。
今まで意識したことはなかったが、写真7の背面のシリアルNo.や、製造年月「11-00」をよく見ると、発売されてまもなくの時期に購入したらしい。
(注:米国仕様のものは、日本のFM放送周波数帯域に合わせるため、内部の調整が必要になることに留意)

<写真7:Tivoli Model Oneの背面と各端子の様子>
*シリアルNo.の上方に記されている会社の住所にご注目いただきたい。なんと「Cambridge、Massachusetts」とある。35年前のKLH Model 21の前面パネルにも「Cambridge、Massachusetts」の文字がデザインされている。この時を超えた一貫性は、なんとしたことだろう**

<写真8:Model Onの内部とバスレフ用の共鳴ダクト>
**左側に黒いパイプが見える。取り扱い説明書には、「低域は、ダクト中にティッシュペーパーを詰め込んで自分好みに調整できる」とある。おもしろい**
格好はいいが、ただのラジオである。
が、そのラジオを粗末に扱ってはいけない。
頭より高い所に置かなければバチがあたる。
それほどの「オーディオの歴史」をこのラジオは包み込んでいる。
オーディオファンの私には、大変に意義深く、中低音もそこそこ深く、実にいい気持ちになるラジオである。
偶然にもこの2台にめぐり合えて、本当に幸せだと思う。

<写真9:ネタバレの私作「電池管AMラジオ」>
**当ブログ「いとし子(4)6BQ5ブースター付電池管ラジオ」から転載。「洗練度」に難点大アリであるが、これ、KLHデザインの影響大であることを分かってもらえるだろうか??**
「無人島と電話帳」の話
もしラジオが聞こえる島であれば、電話帳の代わりにヘンリー・クロースのラジオがいいな。
電源は太陽電池と充電バッテリー。
やはり何でもいいから音楽が聴けなくちゃあね。
中低音も少しは効かせて・・・。
(いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ おわり)
メーカーは違うが左右2つのラジオ、35年の歳月を隔てて、同じ男が設計し商品化した。
この2つに共通するもの、デザイン、音作り、設計のポリシー、製品作りの理念まで、オーディオ界激動の時代を越え、また彼の生涯を通して少しも揺るぎがない。
男の名はHenry Kloss(ヘンリー・クロース)。
1929年米国 Altoona、Pennsylvaniaで生まれ、2002年Cambridge、Massachusettsで没。
エミー賞の最初の受賞者の一人であり、CEA(全米家電協会)の殿堂入りを果たしたオーディオ界の巨人である。
形に惹かれてgetした2つのラジオ
姿格好に強く惹かれるものがあり、早速手に入れたFMラジオ。
入手当時は、そのラジオからオーディオの歴史の表紙を飾るに相応しい、巨人のドラマを聞けるなど、知る由もなかった。
左側のラジオ、KLH Model 21の裏側の写真4、5には、キャビネットに小さな枕のようなものが詰め込まれている(枕の中身はグラスウール)。
これを見て、AR社(Acoustic Research社)のアコースティック・サスペンション方式による小型スピーカーシステムを連想された方は、かなり年季の入ったオーディオ愛好家とお見受けする。
実はそのはず、彼はAR社設立のメンバーであり、そこで独創的なスピーカーシステムの開発を行っている。

<写真1:KLH Model 21(左)とTivoli Model One(右)>
**オーディオ界の巨人ヘンリー・クロースが作った卓上ラジオの一例。KLH Model 21は1965年、Tivoli Model Oneは2000年の発売。バックのSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーとも関連がある**
オーディオの開拓者ヘンリー・クロース
写真1の左は、「KLH社 Model Twenty-One」という1965年に発売された卓上FMラジオである。
私はこのラジオが、オーディオ界の巨人によって作られたことなど、何一つ知らなかった。
この姿を何かの写真で見た瞬間、強く惹かれるものがあり、すぐさまeBayで探しあてた。
もう忘れてしまった十何年も前のことであるが、このラジオの音の心地よさに驚いたものである。
この手のものでは初めて耳にするような、中低音を効かせた余裕たっぷりの鳴りっぷりは、日本の卓上ラジオでは決して聞くことができない。
家電の大型量販店を見て回れば分かるが、そもそも「音質を重視した、きちんとした作りの卓上ラジオ」など、ここ10年や20年来、国産品で見かけたことはない。
ましてや、木製キャビネットを使ってアコースティック・サスペンション方式や、バスレフ方式を採用するなど(たとえ真似事であっても)、望むべくもない。
また写真の背景に置いたSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーは、ダテに置いてあるわけではなく、なんと驚いたことに、このFMラジオと関連があったのだ。

<写真2:KLH Model 21 FM卓上ラジオ>
**キャビネットは14mm厚ほどのウオルナットベニア材+チップ圧縮材で、がっちり作られている。FM専用機。高域と低域のトーンコントロールが可能**
Henry Klossはヘンリー・クロスと記される場合が多いが、「クロース」と「o」を伸ばすのが正しいそうである。
KLH Model 21の前面パネル、水色のバーのすぐ下には、「MODEL TWENTY-ONE・CAMBRIDGE MASSACHUSETTS」と書かれている。
このことは、晩年に至るまでの長い期間、活躍の本拠地がケンブリッジであったことを物語っている。
写真右の卓上AM-FMラジオ「Tivoli社 Model One」は、Tivoli社を共同で設立した彼が、晩年近くの70歳になった2000年の作である。
KLH Model 21から35年、私にはこのModel Oneの姿にも、21の場合と同じ、私を惹きつけるオーラが見えた。

<写真3:Tivoli社 Model One FM-AMラジオ>
**Tivoli社の設立に参画したヘンリー・クロース70歳の第一作。今現在も市場流通機種。Tivoli社の製品群には、彼流の品質とデザインの、各種卓上オーディオ機器がラインアップされている**
巨人の偉業AR社時代
オーディオ時代到来の序曲
ヘンリー・クロースの数ある業績のなかで、日本のオーディオ愛好家にもっとも馴染み深いのは、「AR」、Acoustic Research社時代に開発した「アコースティック・サスペンション方式」による小型スピーカーシステムだと思われる。
1950年代、ヘンリー・クロースはマサチューセッツ工科大学(MIT)の学生であった。
オーディオに興味を持ったのはその頃で、学生仲間とスピーカーの研究や製作を行ったと伝えられている。
そして大学の仲間や、エドウィン・アームストロング(*注)などの協力もあり、MITの先輩であったE.Villchur(エドガー・ウィルシャー)を中心に、1954年、AR社を共同で設立した。
小型(ブックシェルフ型)でも豊かな低音を響かせるARの初代のスピーカーは、完全密閉型エアサスペンション方式のAR-1(1956年)であった。
56年は、米RCAビクターが45-45方式のステレオレコードの発表とデモを行った年である(商品化は1958年)。
ただし同方式の最初の考案者はRCAではなく、1931年に英EMIが英国特許を取得している。
時はそういった時代背景にあり、まさにオーディオ時代到来の序曲が鳴り始めていた。
そして、アコースティック・サスペンション方式を採用したAR-3a(1966年発売)は、日本でも多くのファンを獲得し、ジャズトランペッターのマイルズ・デイビスも愛用、とのうたい文句などもあって大ヒット作となった。
*注) エドウィン・アームストロング
エドウィン・アームストロング(1890-1954)。
この男も、とんでもない巨人である。
残した業績は多岐多数にわたるが、身近で分かり易い例にはつぎのようなものがある。
・再生検波回路の発明(戦前のほとんどのラジオ受信機に採用)。
・スーパーヘテロダイン方式の発明(戦後から現在までのすべてのラジオ受信機に採用)。
・周波数変調方式の発明(すべてのFM放送、FM受信機、アナログ時代のテレビ放送と受像機の音声に採用)。
この3つだけでも、今もなお、社会に文化に、計り知れない恩恵を与え続けている。
しかしこのような、現代社会の形を創り出したといえるほど重要な公共インフラを発明した彼の晩年は、幸せではなかった。
大メーカーとの特許紛争に疲れ果て、たいへん不幸な最後であった。
ともかく偉大な巨人が、KLH Model 21を作った男と出会い、力を貸したのである。
ブックシェルフ型スピーカーを実現したアコースティック・サスペンション方式の動作原理
アコースティック・サスペンションの大まかな原理は、まず第一にfo(エフゼロ:最低共振周波数)の低いスピーカーユニットを使う。
そしてスピーカー・キャビネットを気密性の高い密閉構造にして、空気の弾性をサスペンション(スピーカーのダンパー)として利用し、さらに内部を吸音材で充填することによりスピーカーのfoの上昇を抑える、というものである。
エアサスペンション型 / アコースティック・サスペンション型
話を整理すると、foの低いスピーカーユニットを小型密閉箱に入れ、空気の弾性を低域の制動(ダンパー)に利用したスピーカーシステムを「エアサスペンション型」と呼ぶ(その「副作用」としてfoが上昇する)。
また、その内部に吸音材を詰め込んで、foの上昇を抑える効果を加えたものを「アコースティック・サスペンション型」と呼んでいる。
ちなみにAR-3aの、特に中・高音ユニットの背面には、吸音材がぎっしり詰め込まれており、写真4、5の「枕」の詰め込みは、その音作りの手法をKLH Model 21に適用した例である。

<写真4:KLH Model 21の裏ぶたを外した様子>
**キャビネット上部の空間に、吸音材がぎゅうぎゅう詰めに押し込まれている**

<写真5:取り出した吸音材>
**枕カバーのような袋に、グラスウールが詰め込まれている。おそらく経年変化で変色しており、元の色は分からない**

<写真6:キャビネット上部の空間からスピーカーを覗く>
**マグネットは四角い形状のフェライトのようである。キャビネット前面パネルは木製ではなくアルミ板である**
KLH Model 9 は世界初フルレンジ・コンデンサースピーカー!
ARを退いたヘンリー・クロースは1957年、KLH社を設立した。
オーディオ愛好家向けの、Model6(スピーカー)。
Model8(卓上FMラジオ。真空管式)。
Model 11(ポータブル・ステレオレコードプレーヤー。「スーツケース・レコードプレーヤー」とも言われ、ケースから分離して設置できる2つの音質のよいスピーカーが収納されている。1962年発売)。
この後にも次々と高品質の製品を送り出していった。
さて彼は、この期間に驚くべきスピーカーを商品化している。
「KLH Model Nine」(1960年発売)。
味も素っ気もない一連の番号だけのモデル名からは考えも及ばないが、この「9」こそ、世界初のフルレンジ・コンデンサースピーカーであった。
QUAD ESL(ESL-57)は3年ほど先行した1957年の発売であるが、本物の低音が出る、再生帯域40Hz~20KHzの全帯域型としてはModel9が世界初である。
その大きさは、STAX ELS-8Xより多少小さいが、低域(ウーハー)の発音ユニットは、片側10枚あった。
初めて目にするフルレンジ・コンデンサースピーカーの面積の大きさに、当時の人はとても驚いたに違いない。
STAX ELS-8Xの低域発音ユニットは、全域とも合わせて6枚である(発音ユニットのサイズがMolel9より大きい)。
KLHでは1960年当時、いろいろな研究や試作の結果、コンデンサースピーカーで本当の低音を再生するには、その程度の面積が必要であることが分かっていたのだと思う。
そして、スピーカーに低域の豊かさを求める彼は、QUADの後追いではなく、全帯域を実現すべく大面積型を採ったのである。
日本にもModel Nineのユーザーは存在した
「KLH Model Nine」は、当時、日本のオーディオファイルにも知れており、少なくとも2桁の台数が輸入されたのではないかと推察する。
私がまだ青年の頃であったが、そのオーナーの記事などをオーディオ誌で読んだ記憶がある。
年配のオーディオファンには、このModel9の話をご存知の方も多いのではないだろうか。
1960年にKLHが大型コンデンサースピーカーを発売した4年後、日本のオーディオ業界が世界に誇る、在りし日のSTAX工業株式会社がついにフルレンジのコンデンサースピーカーを完成し、発売した。
STAX ESS-3Aと、6Aである。
当時青年であった私は、その6Aを「STAXの館」で聴いたわけである(当ブログ「甦れSTAX ELS-8X」)。
当時のSTAXの開発・設計スタッフは、このKLH Model Nineをしっかりと研究したに違いない。
私の推測では、おそらく細部ではその「おおらかな作り」に呆気にとられたのではないかと思う。
しかしフルレンジ・コンデンサースピーカーとしての先見性や基本設計には、彼らの学ぶとことが多々あったに違いない。
私のもとで鳴っているSTAX ELS-8Xにも、KLH Model Nineを作ったヘンリー・クロースの開拓者魂の痕跡が、どこかに残されているような気がする。
オーディオ/ビジュアルの先駆者
ヘンリー・クロースの才能は、オーディオだけに留まらなかった。
テレビを大画面で観る手段がなかった時代、彼は1967年にAdvent社を設立し、3管式のプロジェクションTV「VideoBeam 1000」を開発・発売した。
この功績で彼はエミー賞の最初の受賞者の一人に輝いている。
また、Dolby Bタイプのノイズリダクション・システムの開発に貢献し、それを搭載した最初のカセットデッキを開発・発売するなど、その後のカセットデッキ全盛時代の先鞭をつけたのも彼であった。
ヘンリー・クロースはその後もいくつかの会社を立ち上げ、多岐にわたる活躍をして、その時その時に、魅力ある製品を世に送り出している。
そして2000年。
最後となるTivoli Audioの設立に参画し、数々の製品を設計・製品化することになる。
これもヘンリー・クロースの設計だった
写真3のTivoli Model One AM-FM卓上ラジオの姿格好を改めてご覧いただきたい。
これも何かの写真を見て一目惚れしてgetしたものである。
一目惚れの相手の素性を調べて、ヘンリー・クロースの作であることを知り、驚くとともに納得した。
KLH時代の全製品のデザインに共通した魅力が、50年近く経てもなお、一層洗練された形で継承されている。
今まで意識したことはなかったが、写真7の背面のシリアルNo.や、製造年月「11-00」をよく見ると、発売されてまもなくの時期に購入したらしい。
(注:米国仕様のものは、日本のFM放送周波数帯域に合わせるため、内部の調整が必要になることに留意)

<写真7:Tivoli Model Oneの背面と各端子の様子>
*シリアルNo.の上方に記されている会社の住所にご注目いただきたい。なんと「Cambridge、Massachusetts」とある。35年前のKLH Model 21の前面パネルにも「Cambridge、Massachusetts」の文字がデザインされている。この時を超えた一貫性は、なんとしたことだろう**

<写真8:Model Onの内部とバスレフ用の共鳴ダクト>
**左側に黒いパイプが見える。取り扱い説明書には、「低域は、ダクト中にティッシュペーパーを詰め込んで自分好みに調整できる」とある。おもしろい**
格好はいいが、ただのラジオである。
が、そのラジオを粗末に扱ってはいけない。
頭より高い所に置かなければバチがあたる。
それほどの「オーディオの歴史」をこのラジオは包み込んでいる。
オーディオファンの私には、大変に意義深く、中低音もそこそこ深く、実にいい気持ちになるラジオである。
偶然にもこの2台にめぐり合えて、本当に幸せだと思う。

<写真9:ネタバレの私作「電池管AMラジオ」>
**当ブログ「いとし子(4)6BQ5ブースター付電池管ラジオ」から転載。「洗練度」に難点大アリであるが、これ、KLHデザインの影響大であることを分かってもらえるだろうか??**
「無人島と電話帳」の話
もしラジオが聞こえる島であれば、電話帳の代わりにヘンリー・クロースのラジオがいいな。
電源は太陽電池と充電バッテリー。
やはり何でもいいから音楽が聴けなくちゃあね。
中低音も少しは効かせて・・・。
(いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ おわり)
いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 [オーディオのいとし子たち]
CD30周年を失念
まったく気付かなかった。
CD(コンパクトディスク)の登場は1982年である。
「30周年」に当たる2012年は過ぎてしまった。
人生における30歳は「而立(じりつ)」とされ、「自分の立場ができる」歳だそうだ。
人の成長に比べると、どうやらCDの方がずっと早かったようである。
いやいやまことに申し訳ない。
私自身、CDなくして日々の生活を送れないほどお世話になりながら、失念してワイン一杯のお祝いもしなかったとは・・。
ラジオ80周年とか、テレビ60周年とか騒いでいたのに、それらにも匹敵するCDの30周年はどうしたんだ。
と憤っても、誰も相手にしてくれそうもない。
「CD」登場の意義はたいへん大きかった。
それはオーディオの世界だけの話ではなく、21世紀の世界における「歴史に残る大革命」ベスト10に入るであろうエポックメイキングな出来事である。
CDの、音質を含めた性能やそのデジタル理論、一般ユーザー向けに大きく改善された取り扱いの利便性は、まさに画期的であった。
さらにCDは、来たるべきデジタル時代の幕開けを宣言しただけでなく、その新時代の象徴として、今でも虹のような輝きを放っている。
CD(デジタル技術の象徴)は生まれながらに、やがて来るデジタル時代、ネット時代における「音源の媒体」の概念を、根底から変えてしまうほどの可能性を内包していたのである。
一方、それまで半世紀に渡って、音楽ファンやオーディオファンはもちろん、お父さんやお母さん、その子供たちにまで広く親しまれてきたアナログレコードの絶滅は、時間の問題であった。
アナログレコードの絶滅
「CD」後、30年を越えた昨今、アナログレコードは生産・製造において、ほぼ絶滅した、かに見える。
ところが今日でも、国内、海外とも、ごく一部で限定的な生産が行なわれている。
CDの総生産枚数と比較すれば0%のコンマ以下、ゼロをいくつ並べても追いつかないものの、それでもなお、様々な企画による新プレスのアナログレコードがリリースされている。
中古レコードショップや通販店は、まだあちこちで見かけるが、新規のレコード盤が、ごく少数ではあるが、いまだにリリースされているなど、ちょっと意外な状況である。
要するに今もなお、昔の中古盤を探すだけでなく、新しくプレスされた盤を熱望するレコードファンが、ある程度の数、存在しているわけである。
この事実は今現在も、レコードプレーヤーでレコード盤を愛聴している「レコードファン」が健在であり、CD以降30年が経過した今も、レコード盤にはまだまだ「捨てられない魅力」があることの証である。
レコード盤の魅力
その魅力とは何か。
昔からレコードを聴いていて、それが今も続いているからか(至極当然)。
レコード盤の音か。
レコードの大きなジャケットか。
ターンテーブル、トーンアーム、カートリッジといったメカか。
それとも「レコードをかけるという一連の行為」そのものか。
おそらくこれらのどの部分にも、CDにはない、CDでは失われてしまった魅力があるに違いない。
が、しかし、それらがノスタルジックな魅力であれば、消滅するのに何十年もの時間はかからないはずだ。
30年も経てば完全絶滅していてもおかしくはない。
やはりレコード盤やレコードプレーヤーには、何か世界共通の普遍的な魅力があるに違いない。
現用のレコードプレーヤー
アナログレコードを聴くための私のメインプレーヤーは、当ブログの「コンポ」シリーズ(第1回)で紹介した「OTARI BPL-10」である。
その姿も気に入っているが、使いやすさ抜群、そして音は申し分ない。
Technics SP-10MKⅡAの性能をほとんどフルに引き出していると思われる。
ターンテーブルの音に、これ以上の「何か」を求めるとなると、部屋の床構造から、プレイヤーシステムのすべてを根本的に見直さなければならなくなるのでは、と感じている。
ガラスのターンテーブル
今日の日記は、メインターンテーブルBPL-10の傍らに寄り添う、世にも稀な美形プレーヤーである。
当ブログの「甦れ8X」(第3話)の写真2に、その遠くの姿が写っていたので、ターンテーブル愛好家諸兄の中には、気付かれた方もおられたかもしれない。
見るも眩しく窓の光を跳ね返しているそれは、Marantz Tt1000。
8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにして、無共振ベースを実現した稀有の構造を持つターンテーブルである。
私はこのTt1000をOTARIと同じぐらいの頻度で使っている(現在は別部屋の新入りSTAX ELS-8X用に移動)。
これを回すとき、なぜかとても清々しく、いい気持ちになれる。
姿・形が心に反映するのではないかと思う。
また、ボタンに指先を触れるだけて操作ができるフィーリングは「快感」といっていい。

<写真1:Marantz Tt1000 レコードプレーヤー・システム>
**後ろのカーテンの下から漏れる光が、ガラスの板の背面から入り、中を通り抜けて手前の面が輝いている。8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにした構造に注目願いたい。1980年発売**
このターンテーブルは見た目が美形であるためか、性能よりも「格好優先モノ」と思われがちであるが、それはとんでもない誤解である。
だいたい「格好優先」(性能そこそこ)などで、15mm厚のガラス版を、カットし、削りだし、大小の穴を穿ち、溝を彫り、研磨するなどの、おそろしく困難な細工(=手間・時間・コストがかかる)ができるはずもない。
このターンテーブルのベースになっているガラス板の部分をよく観察すれば、よくぞまあ、このような大小込み入った加工をやっつけてしまったものだ、と感嘆する。
どこのガラス加工工場を、どのように口説いて作らせたのか、その経緯を知りたいものである。
性能を追求したら「美麗」がついてきた
信頼ある企業の、コンシューマ相手の市販製品である以上、総合的に見た採算を無視してまでの「暴挙」はあり得ない。
そもそもこれほどのガラス加工を行うともなれば、よほどの信念と覚悟がなければできるものではない。
そこには、ガラスとアルミの積層構造による防振・制振効果を「設計の基本」とした、高性能・高音質のターンテーブル開発計画があったに違いない。
そして素材に見合った形をデザイナーがイメージするなかで、必然的にこのような美麗なフォームに収斂したのだろう。
再度繰り返したい。
最初に「美麗」があったのではなく、防振・制振の目的上、まずガラスとアルミ素材の積層構造があり、高性能・高音質を追求していったら、必然的に(勝手に)美形になったのである。

<写真2:数年前にリリースされた往年の名盤の高音質復刻盤と昔の原盤>
手持ちの一例であるが、上段より、エソテリック(株)がリリースした「英DECCA復刻名盤シリーズ」のLPとCDの一枚。
アンセルメ、スイスロマンドの「三角帽子」の復刻盤のLPとCD(2009年発売)である。
中央の踊る女性のジャケットは、その原盤の日本プレス盤(1962年)とDECCA原盤(これは一つ前の録音でモノラル盤)。
下段の4トラックテープは米国プリント(このテープは保存性の悪いアセテートベース。大事なお気に入りのテープなのでハブが太いリールに巻いて養生している)。
Marantz Tt1000
何事も「盛ん」な時代は「こわい」ものだ。
このような製品が出現するから面白い。
これほど美しく、音響的にも本格的な作りのターンテーブルは、内外とも、他にはない。
ガラスを主構造に用い、まるで美術工芸品のような製品は、もう決して作られることはないだろう。
このMarantz Tt1000は、時代が味方すれば、このような生産合理性のない製品も、時として生まれるという、オーディオ業界の「よき時代」の忘れ形見のようなものだと思う。

<写真3:Tt1000の斜め横の全景>
**15mm厚のこれだけの量のガラス板は大変な重量になる。全重量は26Kgであるが、これは大人の男が、腰を入れて踏ん張らないと持ち上がらない。この写真から、インシュレーターの足の穴、操作ボタンの穴、2つのトーンアームの取り付け穴、モーターの据付穴、それに四隅のカット、すべての縁の面取りと研磨などなど、いかに困難なガラスの加工が必要かを推測していただきたい**

<写真4:Tt1000のブランド・ロゴとモデル名>
**1980年当時、marantzは「ESOTECシリーズ」として、高級メインアンプやプリアンプなどを展開していた**

<写真5:タッチセンサーによる操作ボタン>
**操作はすべて、指先でボタンに軽く触れることによって行う。いわゆるタッチセンサーである。ターンテーブルは重量級であるが立ち上がりは早くストレス感はない**
無共振構造とスペック
Tt1000の構造は、2つの材質を重ねることによる防振・制振理論に基づいている。
質量の異なる2つの材料を重ねると、内部摩擦により振動エネルギーが熱に変換されるため、振動が減衰し、高い防振・制振効果が得られるという理論である。
ターンテーブルベースは、8mm厚のアルミ板を15mm厚のガラスで挟み込んだ三重構造。
ターンテーブルは、5mm厚の硬質ガラスシートを含め、重量3.4Kg。
モーターは電磁ブレーキ付きハイトルク・ブラシレスDCモーターで、起動トルクは1.6Kg・cm。
全重量26Kg。
Tt1000の主なスペックはこのようなものである。

<写真6:主トーンアームdynavector DV505>
**主トーンアームはdynavectorのDV505が付けてある。このDV505はOTARIのBPL-10にも付けているが、トレース能力は比肩するものなし(後継機を除き)。使い勝手も非常によい**

<写真7:DV505の水平回転方向の電磁ダンパー部>
**丸い2つの強力な磁石に挟まれた間隙を、アルミの円弧状のバーが動く(出入りする)際に発生する渦電流により、水平回転のダンパーとして機能する**

<写真8:副トーンアーム SAEC WE-407/23の背面view>
**とても精密かつ堅牢に作られ、ナイフエッジ等のガタなど曖昧なところが一切ない。信頼性が高く、安心して使える。アームスタビライザーのAS-500Eは、ベース底面の穴の関係から残念ながら取り付けられない(ベースがきわめて強固なので、その必要性はないと思うが)。**

<写真9:副トーンアーム SAEC WE-407/23の操作側view>
**見ているだけで気持ちがよくなるほどの、すばらしい精度の工作**
レコードプレーヤーの魅力
身近にあるものでは、レコードプレーヤーほど、気持ちを落ち着かせるものはない。
逆に、心が安定しているときでなければ、レコードプレーヤーに盤を乗せることができないのかもしれない。
まずジャケットから注意深く盤を取り出し、その盤の中心穴を通してターンテーブルのスピンドルを見る。
ミサイル誘導装置のロックオンのようなものだ。
穴から見えるスピンドルの目線がガイドになり、一発でターンテーブルに乗せることができる。
レコード盤の心得の「イ」
一発で落とし込むことができずにあちこち探し、穴の周囲のレーベル面に、醜いヒゲなどをつけてはいけない。
そんなことは神経質すぎるとか、どうとかの話ではない。
この程度のことは、レコード盤愛好家の心得の「イロハのイ」である。
こういった心遣いができないようでは、いくつかのメカの非常に微妙な組み合わせで構成されるレコードプレーヤーを、最良の状態に整備し、最良の音を引き出すことなど、どだい無理な話である。
その微妙なことの組み合わせを追い込んでいくことが面白いところでもあり、また時代に取り残された要因の一つでもある。

<写真10:レコード盤に針を下ろす>
**DV505にはアームリフターが装備されていないので、ちょっと熟練を要する。演奏が始まる前のいい感じの「針音のプロローグ」で、耳の肥えた人であれば、Tt1000の力量が計れるかもしれない**
針をおろす
ターンテーブルを回し、盤面に慎重に針を下ろす。
針が盤の表面を滑走する音に続いて、針が溝に落ち込む音。
そして軽快でダンピングの効いた針音のプロローグとともに、聴きなれた、もう何十回となく繰り返された演奏が、また新しく眼前に広がる。
さあ暫くの時間、お気に入りの演奏に浸ろう。
今日は割合いい感じに聴こえる。
抵抗なく聴く心に溶け込むようなグッドバランスの音が出たときは(生理的にそのように聞こえたとき、かもしれないが)、演奏に興奮することがあっても、精神的には大変リラックスしているのだろう。

<写真11:全体の印象は「クール」>
**ガラスなので冷たい印象が強いが、改めて見ると飾りっけなし。メカニカルな機能美に全体が包まれているように感じられる*

<写真12:お気に入りのヘッドシェルとカートリッジ>
**ヘッドシェルはORSONICのAV-101。なぜかこれがいい具合。この写真のカートリッジはHighponicのMC-A3が付いている。SAECのアームにも同じヘッドシェルの黒が付いている**
再生音は、そのつど違って聞こえる
同じ盤、同じ再生装置であっても、そのつど、音や演奏に対する感じ方が違う。
その時の気分、体調、室温、湿度、気圧、室外の騒音や暗騒音、AC100Vの商用電源の電圧や波形の良し悪し。
まだまだ気付かないパラメータがあるかもしれない。
おそらくそれらの変動要素が、聴く人と、入り口から出口までのすべての装置に何らかの影響を与えているものと思う。
それらがたまたま、うまくいっている時のアナログレコードの再生音は、本当に素晴らしい。
音質などを表現する際によく使われる「オーディオ用語」、解像度、粒立ち、ダンピング、スピード、音離れ等々を持ち出すことがためらわれる「たいへん良好な」音の世界が展開される。

<写真13:背後から小さなライトで照らした様子>
**この清涼な「透明感」は、ガラスでなければ演出できない**
レコード盤は磨り減るか
「擦り切れるほど聴いたレコード」という言い方がある。
しかし、レコード盤を大切に扱っている人が、整備されたレコードプレーヤーで再生するかぎり、好きな盤を繰り返し繰り返し何回も聴くという行為であれば、レコード盤が磨り減ってダメになることは、普通はない。
ビニール盤 vs ダイアモンド針。
硬さでは、蒟蒻(こんにゃく) vs 鉄ほどの違いがあるのに、ダイアモンド針が磨耗して使えなくなっても、ビニール盤はほとんど無傷である。
まことに興味深い現象が、ビニール盤のグルーヴ(groove:溝)と、その溝をトレースするダイアモンド針との接触面に生じているようだ。
おそらく溝にかかる針先の単位面積当たりの強大な圧力と、柔らかいビニールの変形と復元の関係に、その秘密があるのだろう。
モーター部を取り外してみる
この美麗Tt1000が、どの程度気合を入れて作られているのか、ちょっと見てみたい。
まずターンテーブル(回転台)を垂直に持ち上げ、スピンドルから抜いて取り外す。

<写真14:「回転台」を取り外した本体の様子>
**モーターアッセンブリーは、6本の長いビスで、ベース中央のアルミ板に固定されている**

<写真15:取り外した「回転台」の構成部品>
**回転台は、回転台本体と、5mm厚ガラスのターンテーブルシート、それに中央キャップで構成される。裏返しのアルミダイキャストの回転台周辺部の厚みと縦幅を見れば、かなり「イケ」そうに思う。500円玉が小さく見える。この回転台にガラスシートを置くと、本当に魔法のように「鳴き」がなくなる(ベースの防振・制振理論と同じ)。**
DDモーター
ダイレクト・ドライブ・モーターについては、その昔、いろいろとネガティブな論評があった。
初期段階あたりでは、ものによってはいろいろ問題があってもおかしくはない。
ポジであれネガであれ、信頼できる記事、できない記事、様々あるのが評論の世界である。
特にDDターンテーブルに関しては、その後もなぜか首を傾げる批評が目についたが、実績による評価も定まっている今となっては、どうでもいいことだろう。
大事なことは「自分の耳で検証してみる」ことだと思う。
とはいっても残念ながら、今後は未来永劫、ダイレクト・ドライブのターンテーブルが新たに作られることはないだろう(本格的な高級DDターンテーブルのことを話題にしている)。
作りたくても、ターンテーブル自体が絶滅危惧種であるかぎり、採算の見通しは立たない。
DDターンテーブルの開発には、高い技術力と、会社の体力が必要である。
DDは大変リッチなメカを必要とする。
そのコストがかかるDDメカの対極が、ベルトドライブ・メカである。
わが国有数の大企業であり、DDターンテーブルの開発元であり、世界中のプロの現場で使われたDDターンテーブルの傑作機SP-10mkⅡを生み出し、常にDD方式の旗手であった松下のTechnicsブランドでさえ、2010年にターンテーブルの生産を終了している。
私の選択は、やはり抜群に静粛、ひっそりと静まり返って回転するDDである。
それ以外の方式は、モーターの振動や、アイドラの転がり音を免れることが極めて難しい。
それらの僅かな振動やノイズの抑制など、私には難しくて手に負えない。
メカの整備が完璧状態であっても、カートリッジは極微の振動も容赦なく拾う。
それが彼らの仕事である。
ただし、低速回転のモーターと、ターンテーブルとを完全にアイソレートした糸ドライブ(ある程度長めの)には、とても興味がある。
この方式をしっかり試してみないことには、ターンテーブルは語れないのかもしれない。
確かな根拠はないが、見たり聞いたりしたなかでは、長周期のワウさえコントロールできれば、糸ドライブ方式が「再生音」の面では最良ではないかと想像する。
糸の長さとモーターの振動の伝達は逆比例するが、長くなれば長周期の回転変動が発生するらしい。
ターンテーブル大好き、の気力があるうちに、試してみたいものである。
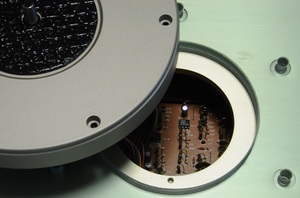
<写真16:写真14の6本の長ビスを抜き、DDモーターアセンブリーをベースから外す>
**ガラスベースの床下にはDDモーターの制御基板を収めた金属ケースが取り付けられている**

<写真17:取り外したDDモーターアセンブリーを横から見た図>
**写真16を横から見た様子。上部の縦棒がスピンドル。DDモーターはアルミダイキャストのケースに収められている**
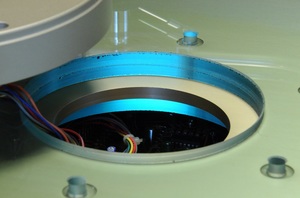
<写真18:モーターアセンブリーの取り付け穴>
* *ベース背面に光を当て、モーター取り付け穴の様子を分かりやすくした。防振・制振のガラス/アルミのサンドイッチ三重構造や、ガラスの穴あけ加工などが観察できる**

<写真18:DDモーターアセンブリーを分解した様子>
**写真17のDDモーターアセンブリーの大きな円盤部と帽子部は、3本の長ビスで合体されている。そのビスを抜いて分離した状態。DDモーターの基台円盤も、固定極を収容した帽子部も、相当しっかりした作りのアルミダイキャストであることが分かる。スピンドルも軸受けも、必要十分の太さと強度が確保されていると思われる。回転速度検出用の緑のリング状のプリントパターンが見える**
さてさて、Marantz Tt1000
こうやって各部や細部をよく見ていくと、単なる美麗ターンテーブルではなく、「これはけっこうタダモノではないな」と感じて頂けたのではないかと思います。
出てくる音も、この力作・苦労作の開発に携わった方々の期待を裏切らず、かなりまともであり、不満なく演奏に没入することができます。
ターンテーブル。
レコードプレーヤー。
それを回してレコード盤をかける「おもしろさ」。
その再生音の気持ちよさ。
この魅力は、興味のない他人にはなかなか理解できない、微妙な感覚や感受性に起因するところが多いのではないかと思います。
この魅力を、続く世代に伝承しなければ、とは思うのですが・・・。
年末年始は、このTt1000をオーディオ部屋に戻し、この時期恒例の「あれら」を、大音量で聴こうと思います。
(いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 おわり)
まったく気付かなかった。
CD(コンパクトディスク)の登場は1982年である。
「30周年」に当たる2012年は過ぎてしまった。
人生における30歳は「而立(じりつ)」とされ、「自分の立場ができる」歳だそうだ。
人の成長に比べると、どうやらCDの方がずっと早かったようである。
いやいやまことに申し訳ない。
私自身、CDなくして日々の生活を送れないほどお世話になりながら、失念してワイン一杯のお祝いもしなかったとは・・。
ラジオ80周年とか、テレビ60周年とか騒いでいたのに、それらにも匹敵するCDの30周年はどうしたんだ。
と憤っても、誰も相手にしてくれそうもない。
「CD」登場の意義はたいへん大きかった。
それはオーディオの世界だけの話ではなく、21世紀の世界における「歴史に残る大革命」ベスト10に入るであろうエポックメイキングな出来事である。
CDの、音質を含めた性能やそのデジタル理論、一般ユーザー向けに大きく改善された取り扱いの利便性は、まさに画期的であった。
さらにCDは、来たるべきデジタル時代の幕開けを宣言しただけでなく、その新時代の象徴として、今でも虹のような輝きを放っている。
CD(デジタル技術の象徴)は生まれながらに、やがて来るデジタル時代、ネット時代における「音源の媒体」の概念を、根底から変えてしまうほどの可能性を内包していたのである。
一方、それまで半世紀に渡って、音楽ファンやオーディオファンはもちろん、お父さんやお母さん、その子供たちにまで広く親しまれてきたアナログレコードの絶滅は、時間の問題であった。
アナログレコードの絶滅
「CD」後、30年を越えた昨今、アナログレコードは生産・製造において、ほぼ絶滅した、かに見える。
ところが今日でも、国内、海外とも、ごく一部で限定的な生産が行なわれている。
CDの総生産枚数と比較すれば0%のコンマ以下、ゼロをいくつ並べても追いつかないものの、それでもなお、様々な企画による新プレスのアナログレコードがリリースされている。
中古レコードショップや通販店は、まだあちこちで見かけるが、新規のレコード盤が、ごく少数ではあるが、いまだにリリースされているなど、ちょっと意外な状況である。
要するに今もなお、昔の中古盤を探すだけでなく、新しくプレスされた盤を熱望するレコードファンが、ある程度の数、存在しているわけである。
この事実は今現在も、レコードプレーヤーでレコード盤を愛聴している「レコードファン」が健在であり、CD以降30年が経過した今も、レコード盤にはまだまだ「捨てられない魅力」があることの証である。
レコード盤の魅力
その魅力とは何か。
昔からレコードを聴いていて、それが今も続いているからか(至極当然)。
レコード盤の音か。
レコードの大きなジャケットか。
ターンテーブル、トーンアーム、カートリッジといったメカか。
それとも「レコードをかけるという一連の行為」そのものか。
おそらくこれらのどの部分にも、CDにはない、CDでは失われてしまった魅力があるに違いない。
が、しかし、それらがノスタルジックな魅力であれば、消滅するのに何十年もの時間はかからないはずだ。
30年も経てば完全絶滅していてもおかしくはない。
やはりレコード盤やレコードプレーヤーには、何か世界共通の普遍的な魅力があるに違いない。
現用のレコードプレーヤー
アナログレコードを聴くための私のメインプレーヤーは、当ブログの「コンポ」シリーズ(第1回)で紹介した「OTARI BPL-10」である。
その姿も気に入っているが、使いやすさ抜群、そして音は申し分ない。
Technics SP-10MKⅡAの性能をほとんどフルに引き出していると思われる。
ターンテーブルの音に、これ以上の「何か」を求めるとなると、部屋の床構造から、プレイヤーシステムのすべてを根本的に見直さなければならなくなるのでは、と感じている。
ガラスのターンテーブル
今日の日記は、メインターンテーブルBPL-10の傍らに寄り添う、世にも稀な美形プレーヤーである。
当ブログの「甦れ8X」(第3話)の写真2に、その遠くの姿が写っていたので、ターンテーブル愛好家諸兄の中には、気付かれた方もおられたかもしれない。
見るも眩しく窓の光を跳ね返しているそれは、Marantz Tt1000。
8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにして、無共振ベースを実現した稀有の構造を持つターンテーブルである。
私はこのTt1000をOTARIと同じぐらいの頻度で使っている(現在は別部屋の新入りSTAX ELS-8X用に移動)。
これを回すとき、なぜかとても清々しく、いい気持ちになれる。
姿・形が心に反映するのではないかと思う。
また、ボタンに指先を触れるだけて操作ができるフィーリングは「快感」といっていい。

<写真1:Marantz Tt1000 レコードプレーヤー・システム>
**後ろのカーテンの下から漏れる光が、ガラスの板の背面から入り、中を通り抜けて手前の面が輝いている。8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにした構造に注目願いたい。1980年発売**
このターンテーブルは見た目が美形であるためか、性能よりも「格好優先モノ」と思われがちであるが、それはとんでもない誤解である。
だいたい「格好優先」(性能そこそこ)などで、15mm厚のガラス版を、カットし、削りだし、大小の穴を穿ち、溝を彫り、研磨するなどの、おそろしく困難な細工(=手間・時間・コストがかかる)ができるはずもない。
このターンテーブルのベースになっているガラス板の部分をよく観察すれば、よくぞまあ、このような大小込み入った加工をやっつけてしまったものだ、と感嘆する。
どこのガラス加工工場を、どのように口説いて作らせたのか、その経緯を知りたいものである。
性能を追求したら「美麗」がついてきた
信頼ある企業の、コンシューマ相手の市販製品である以上、総合的に見た採算を無視してまでの「暴挙」はあり得ない。
そもそもこれほどのガラス加工を行うともなれば、よほどの信念と覚悟がなければできるものではない。
そこには、ガラスとアルミの積層構造による防振・制振効果を「設計の基本」とした、高性能・高音質のターンテーブル開発計画があったに違いない。
そして素材に見合った形をデザイナーがイメージするなかで、必然的にこのような美麗なフォームに収斂したのだろう。
再度繰り返したい。
最初に「美麗」があったのではなく、防振・制振の目的上、まずガラスとアルミ素材の積層構造があり、高性能・高音質を追求していったら、必然的に(勝手に)美形になったのである。

<写真2:数年前にリリースされた往年の名盤の高音質復刻盤と昔の原盤>
手持ちの一例であるが、上段より、エソテリック(株)がリリースした「英DECCA復刻名盤シリーズ」のLPとCDの一枚。
アンセルメ、スイスロマンドの「三角帽子」の復刻盤のLPとCD(2009年発売)である。
中央の踊る女性のジャケットは、その原盤の日本プレス盤(1962年)とDECCA原盤(これは一つ前の録音でモノラル盤)。
下段の4トラックテープは米国プリント(このテープは保存性の悪いアセテートベース。大事なお気に入りのテープなのでハブが太いリールに巻いて養生している)。
Marantz Tt1000
何事も「盛ん」な時代は「こわい」ものだ。
このような製品が出現するから面白い。
これほど美しく、音響的にも本格的な作りのターンテーブルは、内外とも、他にはない。
ガラスを主構造に用い、まるで美術工芸品のような製品は、もう決して作られることはないだろう。
このMarantz Tt1000は、時代が味方すれば、このような生産合理性のない製品も、時として生まれるという、オーディオ業界の「よき時代」の忘れ形見のようなものだと思う。

<写真3:Tt1000の斜め横の全景>
**15mm厚のこれだけの量のガラス板は大変な重量になる。全重量は26Kgであるが、これは大人の男が、腰を入れて踏ん張らないと持ち上がらない。この写真から、インシュレーターの足の穴、操作ボタンの穴、2つのトーンアームの取り付け穴、モーターの据付穴、それに四隅のカット、すべての縁の面取りと研磨などなど、いかに困難なガラスの加工が必要かを推測していただきたい**

<写真4:Tt1000のブランド・ロゴとモデル名>
**1980年当時、marantzは「ESOTECシリーズ」として、高級メインアンプやプリアンプなどを展開していた**

<写真5:タッチセンサーによる操作ボタン>
**操作はすべて、指先でボタンに軽く触れることによって行う。いわゆるタッチセンサーである。ターンテーブルは重量級であるが立ち上がりは早くストレス感はない**
無共振構造とスペック
Tt1000の構造は、2つの材質を重ねることによる防振・制振理論に基づいている。
質量の異なる2つの材料を重ねると、内部摩擦により振動エネルギーが熱に変換されるため、振動が減衰し、高い防振・制振効果が得られるという理論である。
ターンテーブルベースは、8mm厚のアルミ板を15mm厚のガラスで挟み込んだ三重構造。
ターンテーブルは、5mm厚の硬質ガラスシートを含め、重量3.4Kg。
モーターは電磁ブレーキ付きハイトルク・ブラシレスDCモーターで、起動トルクは1.6Kg・cm。
全重量26Kg。
Tt1000の主なスペックはこのようなものである。

<写真6:主トーンアームdynavector DV505>
**主トーンアームはdynavectorのDV505が付けてある。このDV505はOTARIのBPL-10にも付けているが、トレース能力は比肩するものなし(後継機を除き)。使い勝手も非常によい**

<写真7:DV505の水平回転方向の電磁ダンパー部>
**丸い2つの強力な磁石に挟まれた間隙を、アルミの円弧状のバーが動く(出入りする)際に発生する渦電流により、水平回転のダンパーとして機能する**

<写真8:副トーンアーム SAEC WE-407/23の背面view>
**とても精密かつ堅牢に作られ、ナイフエッジ等のガタなど曖昧なところが一切ない。信頼性が高く、安心して使える。アームスタビライザーのAS-500Eは、ベース底面の穴の関係から残念ながら取り付けられない(ベースがきわめて強固なので、その必要性はないと思うが)。**

<写真9:副トーンアーム SAEC WE-407/23の操作側view>
**見ているだけで気持ちがよくなるほどの、すばらしい精度の工作**
レコードプレーヤーの魅力
身近にあるものでは、レコードプレーヤーほど、気持ちを落ち着かせるものはない。
逆に、心が安定しているときでなければ、レコードプレーヤーに盤を乗せることができないのかもしれない。
まずジャケットから注意深く盤を取り出し、その盤の中心穴を通してターンテーブルのスピンドルを見る。
ミサイル誘導装置のロックオンのようなものだ。
穴から見えるスピンドルの目線がガイドになり、一発でターンテーブルに乗せることができる。
レコード盤の心得の「イ」
一発で落とし込むことができずにあちこち探し、穴の周囲のレーベル面に、醜いヒゲなどをつけてはいけない。
そんなことは神経質すぎるとか、どうとかの話ではない。
この程度のことは、レコード盤愛好家の心得の「イロハのイ」である。
こういった心遣いができないようでは、いくつかのメカの非常に微妙な組み合わせで構成されるレコードプレーヤーを、最良の状態に整備し、最良の音を引き出すことなど、どだい無理な話である。
その微妙なことの組み合わせを追い込んでいくことが面白いところでもあり、また時代に取り残された要因の一つでもある。

<写真10:レコード盤に針を下ろす>
**DV505にはアームリフターが装備されていないので、ちょっと熟練を要する。演奏が始まる前のいい感じの「針音のプロローグ」で、耳の肥えた人であれば、Tt1000の力量が計れるかもしれない**
針をおろす
ターンテーブルを回し、盤面に慎重に針を下ろす。
針が盤の表面を滑走する音に続いて、針が溝に落ち込む音。
そして軽快でダンピングの効いた針音のプロローグとともに、聴きなれた、もう何十回となく繰り返された演奏が、また新しく眼前に広がる。
さあ暫くの時間、お気に入りの演奏に浸ろう。
今日は割合いい感じに聴こえる。
抵抗なく聴く心に溶け込むようなグッドバランスの音が出たときは(生理的にそのように聞こえたとき、かもしれないが)、演奏に興奮することがあっても、精神的には大変リラックスしているのだろう。

<写真11:全体の印象は「クール」>
**ガラスなので冷たい印象が強いが、改めて見ると飾りっけなし。メカニカルな機能美に全体が包まれているように感じられる*

<写真12:お気に入りのヘッドシェルとカートリッジ>
**ヘッドシェルはORSONICのAV-101。なぜかこれがいい具合。この写真のカートリッジはHighponicのMC-A3が付いている。SAECのアームにも同じヘッドシェルの黒が付いている**
再生音は、そのつど違って聞こえる
同じ盤、同じ再生装置であっても、そのつど、音や演奏に対する感じ方が違う。
その時の気分、体調、室温、湿度、気圧、室外の騒音や暗騒音、AC100Vの商用電源の電圧や波形の良し悪し。
まだまだ気付かないパラメータがあるかもしれない。
おそらくそれらの変動要素が、聴く人と、入り口から出口までのすべての装置に何らかの影響を与えているものと思う。
それらがたまたま、うまくいっている時のアナログレコードの再生音は、本当に素晴らしい。
音質などを表現する際によく使われる「オーディオ用語」、解像度、粒立ち、ダンピング、スピード、音離れ等々を持ち出すことがためらわれる「たいへん良好な」音の世界が展開される。

<写真13:背後から小さなライトで照らした様子>
**この清涼な「透明感」は、ガラスでなければ演出できない**
レコード盤は磨り減るか
「擦り切れるほど聴いたレコード」という言い方がある。
しかし、レコード盤を大切に扱っている人が、整備されたレコードプレーヤーで再生するかぎり、好きな盤を繰り返し繰り返し何回も聴くという行為であれば、レコード盤が磨り減ってダメになることは、普通はない。
ビニール盤 vs ダイアモンド針。
硬さでは、蒟蒻(こんにゃく) vs 鉄ほどの違いがあるのに、ダイアモンド針が磨耗して使えなくなっても、ビニール盤はほとんど無傷である。
まことに興味深い現象が、ビニール盤のグルーヴ(groove:溝)と、その溝をトレースするダイアモンド針との接触面に生じているようだ。
おそらく溝にかかる針先の単位面積当たりの強大な圧力と、柔らかいビニールの変形と復元の関係に、その秘密があるのだろう。
モーター部を取り外してみる
この美麗Tt1000が、どの程度気合を入れて作られているのか、ちょっと見てみたい。
まずターンテーブル(回転台)を垂直に持ち上げ、スピンドルから抜いて取り外す。

<写真14:「回転台」を取り外した本体の様子>
**モーターアッセンブリーは、6本の長いビスで、ベース中央のアルミ板に固定されている**

<写真15:取り外した「回転台」の構成部品>
**回転台は、回転台本体と、5mm厚ガラスのターンテーブルシート、それに中央キャップで構成される。裏返しのアルミダイキャストの回転台周辺部の厚みと縦幅を見れば、かなり「イケ」そうに思う。500円玉が小さく見える。この回転台にガラスシートを置くと、本当に魔法のように「鳴き」がなくなる(ベースの防振・制振理論と同じ)。**
DDモーター
ダイレクト・ドライブ・モーターについては、その昔、いろいろとネガティブな論評があった。
初期段階あたりでは、ものによってはいろいろ問題があってもおかしくはない。
ポジであれネガであれ、信頼できる記事、できない記事、様々あるのが評論の世界である。
特にDDターンテーブルに関しては、その後もなぜか首を傾げる批評が目についたが、実績による評価も定まっている今となっては、どうでもいいことだろう。
大事なことは「自分の耳で検証してみる」ことだと思う。
とはいっても残念ながら、今後は未来永劫、ダイレクト・ドライブのターンテーブルが新たに作られることはないだろう(本格的な高級DDターンテーブルのことを話題にしている)。
作りたくても、ターンテーブル自体が絶滅危惧種であるかぎり、採算の見通しは立たない。
DDターンテーブルの開発には、高い技術力と、会社の体力が必要である。
DDは大変リッチなメカを必要とする。
そのコストがかかるDDメカの対極が、ベルトドライブ・メカである。
わが国有数の大企業であり、DDターンテーブルの開発元であり、世界中のプロの現場で使われたDDターンテーブルの傑作機SP-10mkⅡを生み出し、常にDD方式の旗手であった松下のTechnicsブランドでさえ、2010年にターンテーブルの生産を終了している。
私の選択は、やはり抜群に静粛、ひっそりと静まり返って回転するDDである。
それ以外の方式は、モーターの振動や、アイドラの転がり音を免れることが極めて難しい。
それらの僅かな振動やノイズの抑制など、私には難しくて手に負えない。
メカの整備が完璧状態であっても、カートリッジは極微の振動も容赦なく拾う。
それが彼らの仕事である。
ただし、低速回転のモーターと、ターンテーブルとを完全にアイソレートした糸ドライブ(ある程度長めの)には、とても興味がある。
この方式をしっかり試してみないことには、ターンテーブルは語れないのかもしれない。
確かな根拠はないが、見たり聞いたりしたなかでは、長周期のワウさえコントロールできれば、糸ドライブ方式が「再生音」の面では最良ではないかと想像する。
糸の長さとモーターの振動の伝達は逆比例するが、長くなれば長周期の回転変動が発生するらしい。
ターンテーブル大好き、の気力があるうちに、試してみたいものである。
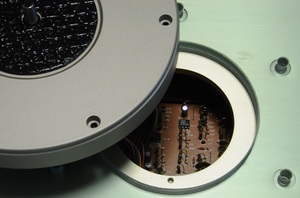
<写真16:写真14の6本の長ビスを抜き、DDモーターアセンブリーをベースから外す>
**ガラスベースの床下にはDDモーターの制御基板を収めた金属ケースが取り付けられている**

<写真17:取り外したDDモーターアセンブリーを横から見た図>
**写真16を横から見た様子。上部の縦棒がスピンドル。DDモーターはアルミダイキャストのケースに収められている**
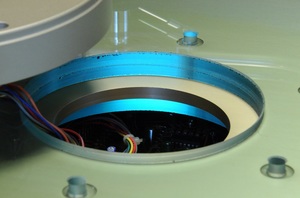
<写真18:モーターアセンブリーの取り付け穴>
* *ベース背面に光を当て、モーター取り付け穴の様子を分かりやすくした。防振・制振のガラス/アルミのサンドイッチ三重構造や、ガラスの穴あけ加工などが観察できる**

<写真18:DDモーターアセンブリーを分解した様子>
**写真17のDDモーターアセンブリーの大きな円盤部と帽子部は、3本の長ビスで合体されている。そのビスを抜いて分離した状態。DDモーターの基台円盤も、固定極を収容した帽子部も、相当しっかりした作りのアルミダイキャストであることが分かる。スピンドルも軸受けも、必要十分の太さと強度が確保されていると思われる。回転速度検出用の緑のリング状のプリントパターンが見える**
さてさて、Marantz Tt1000
こうやって各部や細部をよく見ていくと、単なる美麗ターンテーブルではなく、「これはけっこうタダモノではないな」と感じて頂けたのではないかと思います。
出てくる音も、この力作・苦労作の開発に携わった方々の期待を裏切らず、かなりまともであり、不満なく演奏に没入することができます。
ターンテーブル。
レコードプレーヤー。
それを回してレコード盤をかける「おもしろさ」。
その再生音の気持ちよさ。
この魅力は、興味のない他人にはなかなか理解できない、微妙な感覚や感受性に起因するところが多いのではないかと思います。
この魅力を、続く世代に伝承しなければ、とは思うのですが・・・。
年末年始は、このTt1000をオーディオ部屋に戻し、この時期恒例の「あれら」を、大音量で聴こうと思います。
(いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 おわり)
最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) [原器を目指した「最終アンプ」]
原子が直接放出する光には、人を魅了する神秘的なものがいくつかある。
大は天空を舞うオーロラ。
小は83のプレートの中のグロー。
本機「最終アンプ」のドライバー管801Aの電源には、水銀蒸気整流管83が使われている。
83は、高真空型の整流管では得られない音質が期待できるため、昔から管球アンプ愛好家に根強い人気があり、それが今日まで続いている。
1990年前後ごろであったか、機会あるごとに買い集めたRCA83の中の数本に、茶色に変色したマニュアルシートが巻かれて入っていた。
古い時代の大きめの赤い元箱に入っていたもので、1940年頃に印刷されたRCA83のオリジナルのマニュアルシートである。
その記述の中に「発光」に関する、ちょっと文学的な薫りが漂う箇所があった。
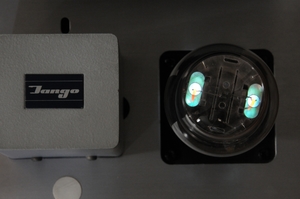
<写真1:動作状態のRCA83を真上から見た状況>
**英文にあるように、プレートの(筒の)中がグローで満たされている。良好な83が発するグローは、ゆらぎや、まばたくような不安定さはなく、極めて安定した発光が持続する。私の経験からは、入手したRCA83の10本に数本の割合で、グローが不安定な「半不良品」が混じる。現状ではむしろ、完璧な状態の83に当たる方がラッキーなのかもしれない**
Under operating conditions, the 83 has bluish-white glow filling the space within the plates and extending to some degree into the surrounding space outside the plates.
(私の訳:動作状態にあるとき、83のプレートの内側は青白色の輝きで満たされ、またその光はプレートの外周にも幾分の広がりを見せる)かな。
今日の日記
さてこの英文の一節は、私が83のグローを見た時の感覚にとてもよく似ています。
このテクニカルシートの一文を発見したときは、執筆者に親近感を覚えたものです。
このように水銀蒸気整流管は、人を魅了する発光現象とともに、「余人をもって代えがたい」音質面での大きな期待と可能性を秘めています。
その反面、この手の整流管を使うには、昔も今も変わらぬ、ちょっと厳しい掟(おきて)と作法があります。
今日の日記は、本機「最終アンプ」の電源部を、少し詳しく観察してみます。
使用されている水銀蒸気整流管の「掟」と「作法」の実際とともに、本機の電源部の仕様などについて綴ろうと思います。
801Aシングルアンプ起動時の整流管の様子
本機「最終アンプ」の話に入る前に、参考までに、前回の「最終アンプ」(4)に登場した801Aシングルアンプの電源を投入し、水銀蒸気整流管83の起動時の様子を観察してみます。
水銀蒸気整流管の第一の掟は「プリヒート」(予熱)です。
まずフィラメントのみに通電し、その熱で水銀を蒸発させ、管内を飽和蒸気で満たすことが目的です。
電源ON直後から観察開始

<写真2:電源ON 直後の水銀蒸気整流管83の様子>
**電源ランプのLEDが点灯し、83のフィラメントが赤熱しているが、電源ON直後であるため、管壁はまだクリアな状態。整流管後方の電源トランスは、整流管の撮影のため、ティッシュペーパーをかけてある**

<写真3:電源ON 30秒後の様子>
**管壁内面全体が曇ってきた。フィラメントに熱せられて蒸発した水銀が、管壁で冷やされて凝縮したもの**
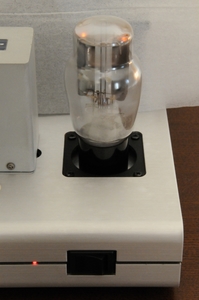
<写真4:電源ON 1分30秒後の様子>
**管壁がさらに曇ってきた。管内が水銀の飽和蒸気で満たされていることを示しており、83の場合はこの状態でスタンバイ完了、B電源投入が可能である**
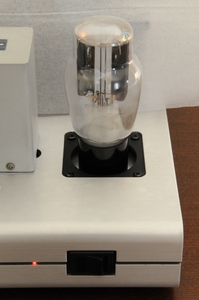
<写真5:電源ON 2分10秒後、B電源投入直後の様子>
**タイマーリレーによりB電源が投入された直後の様子。プレート内部にグローが見える(周囲が明るいため光は微か)。管壁上部の筒の部分がクリアになってきた。管壁も熱せられて温度が上がり、凝縮した水銀が再度蒸発したため**

<写真6:電源ON 5分30秒後、B電源投入3分20秒後の様子>
**管壁全体の温度が上がり、下部の黒いベース付近を残して、ほとんどがクリアになっている。この時点の真上からのViewが写真1**

<写真7:電源ON 数10分経過したアンプ全体の様子>
**83は全体がクリアになり、曇っている部分は最下部の一部分のみ**
そもそも今どきなぜ真空管アンプ
さてさて、そもそも「ダイオード」という高性能の整流素子が存在するのに、今さらなぜ「整流管」なのか。
さらには、昨今の半導体技術を利用せず、なぜ過去の遺物である「真空管アンプ」なのか。
ここでもう一度、この根源的な問題に対する私なりの答を「こじつけ」てみたい。
このことは同好のオーディオ仲間からも、たまに言われることがある。
もっともな疑念であると思うし、私自身も一般論としては、半導体アンプより真空管アンプの方が音質的に優れているとは思っていない。
しかし本機のように、能動素子2つだけで数10Wの出力を、それも最高クラスの音質で得られるアンプは、真空管式以外には求められないと思う。
増幅作用に関与する能動素子の数
昨今の半導体アンプは、数10、あるいは100以上の能動素子が使われていると思われる。
その中で、増幅作用に直接関与する能動素子の数の合計は幾つぐらいになるのだろうか。
その圧倒的多数 vs 2つ。
本機の場合、私はこの点に真空管アンプの優位性を見ている。
接続箇所の数
また半導体アンプの場合、能動素子の数に比例して、オーディオ信号が直接通る経路に、非常に多くの接続箇所が存在する。
はたして合計いくつの半田づけの箇所、あるいはコネクタ接続の箇所が介在するのだろうか。
オーディオ愛好家であれば、誰しも、ライン入出力の端子やスピーカーの端子、また各種の切り替えSWの接点などの信号の接続部には、神経質なほど注意を払う。
それは当然として、機器内部の回路には、それらの何10倍もの接続箇所が存在することを忘れてはならない。
その圧倒的多数 vs 少数。
本機の場合、私はこの点にも真空管アンプの優位性を見ている。
たった2つのA級増幅の能動素子。
真空管式の本機「最終アンプ」は、これらの点において、圧倒的な優位性があると確信している。
そこが本機を製作する大きな動機の一つであり、そして結果もそれを裏切らなかった。
なぜ整流管
水銀蒸気整流管の絶対的利点については、当日記「最終アンプ」シリーズで繰り返し紹介してきた。
水銀蒸気整流管は高真空整流管にくらべて、電圧降下が極めて小さく、かつ降下電圧が電流の増減によらずほぼ一定、という優れた特長がある。
そして音質面での期待と可能性も大きい。
83の場合、それらの実験は簡単にできる。
83は、ソケット互換性のある高真空型の整流管の数種類、たとえば5Z3などと挿し替えができるため、電圧降下や音質比較の検証は容易に可能である。
当然ながら、音の違いは個々の被試験アンプによって異なるが、時間をかけて(そこが大切)実験をやってみる価値は大いにあると思う。
それならダイオードでしょ
さて、管内の電圧降下を問題にするのであれば、水銀蒸気整流管の1/10以下の優れた性能のダイオードを使えばいいではないか、という意見にはどう答えるのか。
実は水銀蒸気整流管の83にも、872Aにも、ソケット互換性のある「ダイオード版83」、「ダイオード版872A」(アノードキャップはなく、足に接続されている)が実在する(eBayあたりで時々出品される)。
私は所持していないが、872Aのこれを使った実験には興味がある。
その「ダイオード版83」の「簡易手作り版」、UX4ピンソケットにダイオードを2個付けたものと置き換える実験は、過去にいろいろな種類のダイオードでやってみたことがある。
その結論は、メインアンプにおける83の場合、ダイオードによる置換後の音質は、決して悪くはなかった。
また、ダイオードのスイッチングノイズがどうこう、といった問題も特段の障害にはならなかった。
それでも「整流管」を使うのは、
「わざわざ真空管アンプを作るのに、その電源の整流素子に整流管を使わないという“アンバランス感”(私の美意識的尺度)を曲げてまで、ダイオードを採用するほどの優位性は確認できなかった」
ということに尽きる。
まず本機の発熱量
さて、本機の電源部に話を戻したい。
まずセットの発熱量であるが、出力管211の発熱は大きい。
フィラメント電力10V×3.25A=32.5W。
プレート損失1000V×60mA=60W。
合計でざっと100Wの発熱がある。
872Aも5V×7.5A=37.5Wのフィラメント電力が2本分、80Wほどの発熱がある。
水銀蒸気整流管は管壁温度の制約があり、特に放熱について十分考慮する必要がある。
さらにドライバー管801Aの発熱もあり、真空管だけで合計200Wほどの熱が発生する。
その上、211と801Aのフィラメント直流点火用レギュレータからの発熱も大きい。
ともかく十分な放熱対策をした構造設計をしなければならない。
本機は自然空冷で連続使用が可能なように設計されている。
強制空冷ファンに頼る手もあるが、この程度の規模であれば、自然空冷連続使用を基本仕様とすべきと思う。
実況解説 電源ONから定常状態まで
電源ON
では電源を入れよう。
電源スイッチに指を掛ける前に、まず本機全体を眺め、それぞれの球やアノードキャップの様子などに異常がないかを確認する。
電源ON。
電源スイッチは大昔から変わらない無骨で大きいトグルSWである。
少し重いが意外に感触はよい。
いかにも信頼感があって小気味いい。
冷えて抵抗値が低くなっている合計5本の真空管のフィラメントに一斉に突入電流が流れ、1・2秒の間、過電流によりトランスやフィラメントがブ~ンとうなる。
スイッチONと同時に211と801Aのトリエーテッドタングステン・フィラメントが明るく灯る。

<写真8:電源ONの前の様子>
**水銀蒸気整流管の83と872Aは、長年使用している球なので、管壁内部の汚れた部分がある**
10秒ほど経過
水銀蒸気整流管の872Aと83は、10秒ほど経過すると、早くもフィラメントの熱で蒸発した水銀が、冷えている管壁内面に蒸着し始め、内壁全体が雲ってくる。
もうしばらくすると、その曇りが徐々に鏡のようになり、管の壁面に周囲の景色が映り込む。

<写真9:電源ON後30秒経過>
**83は先の写真3・4などと同じ状況。872Aは管壁内部に凝縮した水銀蒸気が、蒸着された鏡のようになり、床の色が反射して橙色に見える。本当はクロームメッキのような鏡であるが、カメラのホワイトバランスの影響なのか、このような色になった。下手なカメラマンで申し訳ありません。**
実はその「鏡状態」(クロームメッキ状態)を撮りたくて、3度挑戦したが、どうやってもうまく写らなかった。
どうやら、鏡面をそれらしく撮るには、かなり撮影技術の研究が必要なようだ。
2分ほど経過
2分ほど経過すると、鏡になった管壁が、部分的に徐々に晴れて透明になってくる。
管壁の温度が高くなり蒸着した水銀が蒸発するためである。管壁がこの状態になれば、872Aのスタンバイができた目安である。

<写真10:電源ON後3分経過>
**83も872Aも、鏡面であった部分(橙色に見えていた部分)がだいぶ透明になってきた。872Aのフィラメントが見えるようになった。**

<写真11:電源ON後5分経過>
**タイマーリレーによるB電源ONの直前。管壁下部を除いて、ほとんどの部分がクリアになった。872Aの予熱もこれで十分**
5分経過 パシャン!
電源ONから5分後、タイマーリレーが作動してパワーリレーがONになり、B電源用トランスの1次側にAC100Vが供給される。
タイマーリレーの音はほとんど聞こえないが、パワーリレーの音は大きい。
この音の感じも、信頼感があってなかなかいい。
その一瞬、872Aの上部全体が青い光で充満し、すぐに小さくなって安定する。電源部の平滑コンデンサーを充電するための突入電流により、強く発光するためである。
管内電圧降下の少ない水銀蒸気整流管には、この突入電流を制限する意味からも、平滑部はチョークインプット方式であることが必須の条件となる(図1の③の部分)。
タイマーリレーの設定は、水銀蒸気整流管はもとより、211も801Aも、その他諸々の部分も含めて、多少とも熱的ストレスの緩和になるよう、できるだけ長い時間プリヒートした方がよい。
日常、気の向くままに使って20年、突入電流の攻撃も、少なくとも通算2000回を超えていると思う。
電源ON時に何かが壊れたことはまだ一度もないが、劣化したヒューズが断になることはたまにある。
B電源用トランスの2次巻線センターラインに低抵抗を入れるなど、本機のちょっとした安全設計が功を奏していると思っている(図1の②の箇所)。
音を出すまでしばらく放置
B電源が供給された時点で音は出る。しかし長年の習慣から、時間に余裕があるときはそのまま10分~15分以上は放っておく。
半導体アンプの場合もしかり、各種のプレーヤ、DAコンバータなど、すべて同じである。
オーディオ機器のほとんどは寝起きが悪い。目覚めた直後の眠そうな音を聞きたくないため、シャキッと目を覚ますまで待つことにしている。
B電源ON後20分~30分ほど経過すると、872Aの管壁温度の上昇も飽和点に達し、青色グローが鮮やかな色で輝くようになる。
グローは管壁温度が高いほど美しい。
冬よりも夏の方がきれいである。
さあ、もうそろそろ音を出してもいいだろう。
今日も第一声から、思わず身構えてしまうほどのリアル感のある音を期待したい。
水銀蒸気整流管872Aの管壁温度の管理
プリヒートと温度管理が適切でない場合のダメージ
水銀蒸気整流管872Aを使うためには、設計上および使用上の特別な注意が必要である。
まずは管壁の温度管理がある。
「872Aのガラス管最下部(金属ベースのすぐ上)の温度は、20℃~70℃の範囲でなければならない」と、RCA872Aの元箱に同梱されていたデータシートに書かれている。
この球が作られた遠い昔の時代に思いを馳せる茶色に変色した紙であり、折ればパリッと割れてしまうほど乾ききり、しなやかさが失われている。
70℃を超えると、水銀の蒸気圧が上がりすぎて逆耐電圧が下がり(逆電流が流れやすくなって)最悪の場合は内部でスパークが発生し、各部にダメージを与える危険性がある。
20℃~60℃におけるピークプレート逆耐電圧 10000V
20℃~70℃におけるピークプレート逆耐電圧 5000V
となっている。
逆に温度が低いと、十分な蒸気圧が得られないため電圧降下が増し、その結果、陽イオンがカソードへ衝突する速度が速くなり、カソード(=フィラメント)を損傷する危険性がある。
寒冷地では、フィラメントのプリヒート時間を10分以上にすべきだろう。
このように水銀蒸気整流管は、周囲温度と管壁冷却を十分考慮した機体設計をしなければならない。

<写真12:電源ON後30分ほど経過した872Aのガラス管最下部の様子>
**水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

<写真13:同じく電源ON後30分ほど経過した83のガラス管最下部の様子>
**隣の872Aと同様に、水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**
一般の家庭におけるオーディオ機器にとっての「住み心地」は、四季を通して快適な環境を与えられているとは限らない。
室温、つまり雰囲気は、冬は低く夏は高いとも限らない。
冬、各種の暖房機器の熱が直接機器にあたれば、機器の温度は夏よりも高温になる可能性がある。
夏、空調環境が良好な室内であっても、空気流の死角であったり、直射日光が差し込んだり、思わぬ高温になる可能性もある。
これらのことを考えると、本機の設置場所の想定上限の室温を、少なくても30℃以上に置かなくてはならない。30℃を上回る雰囲気において、200W超の発熱がある本機の連続運転の安全確保には、設計上たいへん厳しい対応を迫られる。
近年はパソコン用の「静音ファン」なるものが安価に入手できるので、強制空冷の導入も、高温時の補助としては有効である。
ただし冷却を、全面的にファンに頼る場合は、なんらかの原因でファンが停止したときの安全対策を講じておく必要がある。
家庭用のアンプであれば、ファンの停止を検知して、主電源をOFFにするだけでよい。
本機で体験したことであるが、20年の間には、真夏の熱帯夜に電源を切り忘れ、エアコンが止まった部屋で翌朝まで炎熱地獄を味わわせたことが何度もある。
熱帯夜に、そよ、とも空気のゆらぎがない雰囲気に置かれた本機の筐体は、怖いほどの温度に達したと思われるが、いままで一度も異常事態にはならなかった。
本機の場合、872Aの動作は、定格の、電圧は数分の1、電流にいたっては数10分の1程度の超軽作業しかしていない。
そのため、温度に関するマージンが多少は上がっているのかもしれないが、水銀の蒸気圧が規定の範囲を超えれば、必ずどこかに何らかのダメージを与えるだろう。
その被害がどのようなものになるのか私には分からない。

<写真14:本機の全景(再掲)>
**必要最小限の放熱は、それぞれの真空管まわりの空間の余裕によって確保される。また、発熱量が大きい出力管211と整流管872Aのソケット穴には、通気間隙を設けてある。また直流点火用の電源部の熱は、写真のシャシー右側面に逃がしているため、放熱フィンを取り付けた**
水銀蒸気整流管のプリヒートは長めに
872Aと83がもたらす、音質的に他の整流管では得られない効能を信じている以上、この整流管を安全無事に使い続けなければならない。
繰り返しになるが、水銀蒸気整流管の電源投入時に守らなければならない掟はプリヒートである。
フィラメントとB電源を同時に投入してはならない。
本機では電源ONにより、増幅部を含めて、すべての真空管のフィラメントのプリヒートが始まる。
プリヒート時間は5分ちょうどにセットしてある。
増幅管のフィラメントも同時に点火するため、すべての真空管の熱的ストレスの緩和にも役立っていると思う。
20年間、高圧を加える前の5分間の「準備運動」を、すべてのフィラメントにやらせてきた。
東京近郊の平野部では、冬場の木造家屋でも、5分間の予熱で必要十分だろう。
私の主観的な感覚では、5分以下ではプリヒート上の不安があり、5分以上は使い勝手の上から長すぎる、といったところか。
B電源がONになっても、すぐに音を出すわけではなく、普通はその後10分~15分以上は放っておくが、プリヒートは5分程度で終わってほしい、という意味である。
しかし寒冷地の冬の朝などは、冷え切ったまま電源を入れることを想定すると、10分間ほどのプリヒートが望ましいと思う。
RCA872Aのデータシートによると、周囲温度が10℃~20℃の場合、プリヒート時間は最短2分間、20℃以上の場合は最短1分間、と明記してある。
しかしこれらの記述は、いわゆるカタログデータと受け取り、その数倍のプリヒート時間を与えていただきたい。
RCAのデータシートのグラフによると、フィラメントのプリヒートを開始してから、凝結している水銀の温度が、周囲と熱的平衡に達するまでの時間は、代表例で約30分ほどかかる。
球の形が大きくて重いだけに、872A全体の熱慣性はかなり大きいことに留意されたい。
タイマーリレーとパワーリレー
プリヒート時間とB電源の投入は、タイマーリレーで制御する。
本機は、タイマーリレーの設定時間を5分にしている。
電源スイッチONにより全球のフィラメントが点火し、その5分後に作動するタイマーリレーの接点でパワーリレーを制御し、B電源用トランスの1次側に通電する。
当然のことであるが、タイマーリレー自身の接点をパワーラインのON/OFFに使ってはならない。
その接点の容量が、電圧・電流ともに満足していても使わない。
タイマーリレーは、いわゆる「接点渡し」と呼ばれる、被制御機器を制御するための接点を与えるためのものである。
つまり、相手側のリレーを制御したり、半導体スイッチのゲートを制御するなど、ごく軽い負荷を想定している。
誤った使い方をして、たとえば接点がスパークなどでONのまま貼り付いてしまった場合、次回の電源ONではフィラメントとB電源が同時にONになり、恐ろしいことになる。
タイマーリレーはパワーリレーに比べ、接点やバネが柔である。
「時計係り」には時間だけを計らせておけばよい。
当然であるが、パワーリレーは元来パワーラインをON/FFするためのものであり、電力の開閉に関する信頼性は非常に高い。
信頼性と安全性、それに長期安定性のための設計とはこういうものだ、とは、本機を製作した円通寺坂工房からの受け売りである。

<写真15:本機のタイマーリレーとパワーリレー付近の工作>
**左の白いのがタイマーリレー(定番のOMRON製)。右側の黒いのがパワーリレー。工作はプロ用機器のレベル**
水銀蒸気整流管のための電源部の仕様
水銀蒸気整流管に関連して、本機の電源部の仕様を簡単に紹介させていただきたい。
B電源用トランスは、フィラメント用トランスと分離独立。
またB電源用トランスの2次巻線は、初段用と出力段用と分離独立させている(私の要求は、トランスごと分離独立であったが、筐体の大きさと重量などから断念せざるを得なかった)。
B電源用トランスの仕様は、「AC100V 容量550W」。
初段801A用2次巻線「中点タップ付き450V・650V 80mA」。
出力段211用2次巻線「中点タップ付き1000V・1100V 200mA」。
こういった仕様のものを作ってもらった。
整流部、平滑部とも、初段用と出力段用とは分離独立である。
整流管は初段用に83を1本、出力段用に872Aを2本使う。
いずれも水銀蒸気整流管であり、内部電圧降下が大変小さく、電流の変化による変動も少ない。
平滑部はどちらもチョークインプットである(図1の③部分)。
水銀蒸気整流管を使う場合には必須の条件である。
チョークインプットはフィルターとしての性能が優れているとともに、整流管の耐逆電圧を低くしたり、B電源ON時の突入電流の抑制にも大きな効果がある。
使用するチョークの仕様は、初段801A用に「10H+10Hの50mA」、出力段211用に「10H+10Hの150mA」である。
どちらも可能なかぎり直流抵抗が低いものを作る必要がある。
平滑用のすべてのコンデンサーはフィルム系を採用し、電解コンデンサーは使っていない。
電解コンデンサーは、801Aと211のフィラメントの直流点火用電源に使っているだけである。
平滑用のすべてのコンデンサーをフィルム系としたのは、音質面と長期安定性からの選択である。
「パワーアンプの音質は、電源の音を聴いていると思うべし」。
また、真空管アンプにおける整流管を使った基本的な整流平滑回路の場合、平滑用コンデンサーの容量をむやみに大容量にすると、音質を損なう結果になる、との先達の教えも遵守しなければならない。
なぜそうなのか、私には明確に説明することができないが、電源ON時の突入電流をなるべく小さく短時間に抑え、整流管の過度的な過負荷を軽減する意味からも、容量は必要十分な範囲で最小限に止めておくべきである。

<図1:本機の電源部の全回路図(再掲)>
**①はタイマーリレー部。②は安全設計のための挿入抵抗。③はチョークインプット部分。フィルター入り口のコンデンサーの容量をむやみに大きくすることは厳禁。整流管の寿命に影響する**
家庭用機器として安全・安心・安定設計
本機のような1000Vを扱い、かつ大きな発熱を伴う機器を家庭に持ち込むには、十二分な安全設計を行うことが、すべてに優先される。
また、機器を扱う人には一定の知識が必要であり、家人にも必要最低限のことを話して教えておくべきである。
特に幼児や小さい子供がいる家庭では、絶対に手を触れることができないような対策を講じる必要がある。
本機を取り扱うための必要最低限の知識を持たない人にとって、本機は危険である。
家庭での1000Vの安全対策
温度の次は1000Vの電圧である。これはもっと怖い。事故の状況によっては命にかかわる可能性がある。
幸い私は、まだ1000Vの電撃を喰らったことはないが恐ろしい。
恐れなければならない。
そして少しでも安心できるよう、万全の手を打たねばならない。
特に幼児には厳重な注意が必要である。
いたずらは彼らの仕事であり、それを阻止できない。
彼らがどう知恵をまわしても絶対に手が(スプーンを持った手も)届かないようにすべきである。
872Aの光やアノードキャップなどが興味の対象になってしまった悪夢を考えると血の気が引く。
高圧部の配線の引き回しや線材、端子の処理、半田付けのノウハウなど、高圧を扱うにはかなり専門的な知識が必要になる。
高圧がかかる半田付けの箇所から、先の尖ったヒゲが出ていれば、どのような現象が起こるのか。
電線の被覆に関し、材質・厚み・耐圧の関係はどうなのか。
「プレート電圧1000V」の場合、回路各部の最大ピーク電圧は、どの部分に何ボルトかかるのか。
電源ON時(B電源ON時)、OFF時には、過渡現象によるどのような電圧が、どこに発生するのか。
その他にも、高電圧を取り扱うために必要な知識は種々あると思うが、私はこの方面の専門知識に詳しくなく、これ以上の話ができない。
とにかく使う人はもちろん、その家族も1000Vの怖さを知っておく必要がある。
本物の高圧を扱う人から見れば、1000V程度は高圧のうちに入らないが、ものが一般家庭用娯楽機器のオーディオアンプだけに、やはり1000Vは特別であり危険である。
電源部が要(かなめ)
信号増幅部のクオリティーが上がり、ピュアになればなるほど、聞こえてくるのは「電源の音」である。
つまりメインアンプから出てくる音の源は「電源部」にある。
言い換えれば、メインアンプの音質は「電源部」に支配されている。
このことから、信号増幅部に投入する物量(クオリティーの意味)以上のものを、まず電源部に投下すべきである。
このことは多分、間違ってはいないと思う。
おそらく正しい。
そのことは本機「最終アンプ」が20年、変わりなく元気に歌い続けて体現している。
(最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) おわり)
大は天空を舞うオーロラ。
小は83のプレートの中のグロー。
本機「最終アンプ」のドライバー管801Aの電源には、水銀蒸気整流管83が使われている。
83は、高真空型の整流管では得られない音質が期待できるため、昔から管球アンプ愛好家に根強い人気があり、それが今日まで続いている。
1990年前後ごろであったか、機会あるごとに買い集めたRCA83の中の数本に、茶色に変色したマニュアルシートが巻かれて入っていた。
古い時代の大きめの赤い元箱に入っていたもので、1940年頃に印刷されたRCA83のオリジナルのマニュアルシートである。
その記述の中に「発光」に関する、ちょっと文学的な薫りが漂う箇所があった。
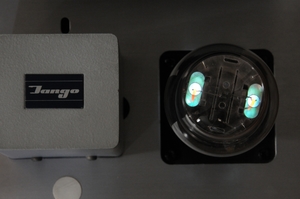
<写真1:動作状態のRCA83を真上から見た状況>
**英文にあるように、プレートの(筒の)中がグローで満たされている。良好な83が発するグローは、ゆらぎや、まばたくような不安定さはなく、極めて安定した発光が持続する。私の経験からは、入手したRCA83の10本に数本の割合で、グローが不安定な「半不良品」が混じる。現状ではむしろ、完璧な状態の83に当たる方がラッキーなのかもしれない**
Under operating conditions, the 83 has bluish-white glow filling the space within the plates and extending to some degree into the surrounding space outside the plates.
(私の訳:動作状態にあるとき、83のプレートの内側は青白色の輝きで満たされ、またその光はプレートの外周にも幾分の広がりを見せる)かな。
今日の日記
さてこの英文の一節は、私が83のグローを見た時の感覚にとてもよく似ています。
このテクニカルシートの一文を発見したときは、執筆者に親近感を覚えたものです。
このように水銀蒸気整流管は、人を魅了する発光現象とともに、「余人をもって代えがたい」音質面での大きな期待と可能性を秘めています。
その反面、この手の整流管を使うには、昔も今も変わらぬ、ちょっと厳しい掟(おきて)と作法があります。
今日の日記は、本機「最終アンプ」の電源部を、少し詳しく観察してみます。
使用されている水銀蒸気整流管の「掟」と「作法」の実際とともに、本機の電源部の仕様などについて綴ろうと思います。
801Aシングルアンプ起動時の整流管の様子
本機「最終アンプ」の話に入る前に、参考までに、前回の「最終アンプ」(4)に登場した801Aシングルアンプの電源を投入し、水銀蒸気整流管83の起動時の様子を観察してみます。
水銀蒸気整流管の第一の掟は「プリヒート」(予熱)です。
まずフィラメントのみに通電し、その熱で水銀を蒸発させ、管内を飽和蒸気で満たすことが目的です。
電源ON直後から観察開始

<写真2:電源ON 直後の水銀蒸気整流管83の様子>
**電源ランプのLEDが点灯し、83のフィラメントが赤熱しているが、電源ON直後であるため、管壁はまだクリアな状態。整流管後方の電源トランスは、整流管の撮影のため、ティッシュペーパーをかけてある**

<写真3:電源ON 30秒後の様子>
**管壁内面全体が曇ってきた。フィラメントに熱せられて蒸発した水銀が、管壁で冷やされて凝縮したもの**
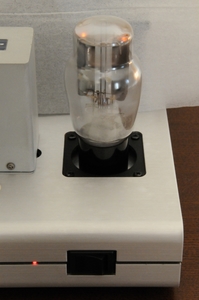
<写真4:電源ON 1分30秒後の様子>
**管壁がさらに曇ってきた。管内が水銀の飽和蒸気で満たされていることを示しており、83の場合はこの状態でスタンバイ完了、B電源投入が可能である**
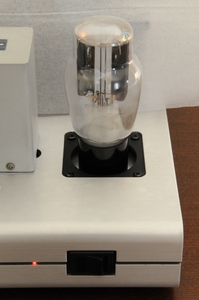
<写真5:電源ON 2分10秒後、B電源投入直後の様子>
**タイマーリレーによりB電源が投入された直後の様子。プレート内部にグローが見える(周囲が明るいため光は微か)。管壁上部の筒の部分がクリアになってきた。管壁も熱せられて温度が上がり、凝縮した水銀が再度蒸発したため**

<写真6:電源ON 5分30秒後、B電源投入3分20秒後の様子>
**管壁全体の温度が上がり、下部の黒いベース付近を残して、ほとんどがクリアになっている。この時点の真上からのViewが写真1**

<写真7:電源ON 数10分経過したアンプ全体の様子>
**83は全体がクリアになり、曇っている部分は最下部の一部分のみ**
そもそも今どきなぜ真空管アンプ
さてさて、そもそも「ダイオード」という高性能の整流素子が存在するのに、今さらなぜ「整流管」なのか。
さらには、昨今の半導体技術を利用せず、なぜ過去の遺物である「真空管アンプ」なのか。
ここでもう一度、この根源的な問題に対する私なりの答を「こじつけ」てみたい。
このことは同好のオーディオ仲間からも、たまに言われることがある。
もっともな疑念であると思うし、私自身も一般論としては、半導体アンプより真空管アンプの方が音質的に優れているとは思っていない。
しかし本機のように、能動素子2つだけで数10Wの出力を、それも最高クラスの音質で得られるアンプは、真空管式以外には求められないと思う。
増幅作用に関与する能動素子の数
昨今の半導体アンプは、数10、あるいは100以上の能動素子が使われていると思われる。
その中で、増幅作用に直接関与する能動素子の数の合計は幾つぐらいになるのだろうか。
その圧倒的多数 vs 2つ。
本機の場合、私はこの点に真空管アンプの優位性を見ている。
接続箇所の数
また半導体アンプの場合、能動素子の数に比例して、オーディオ信号が直接通る経路に、非常に多くの接続箇所が存在する。
はたして合計いくつの半田づけの箇所、あるいはコネクタ接続の箇所が介在するのだろうか。
オーディオ愛好家であれば、誰しも、ライン入出力の端子やスピーカーの端子、また各種の切り替えSWの接点などの信号の接続部には、神経質なほど注意を払う。
それは当然として、機器内部の回路には、それらの何10倍もの接続箇所が存在することを忘れてはならない。
その圧倒的多数 vs 少数。
本機の場合、私はこの点にも真空管アンプの優位性を見ている。
たった2つのA級増幅の能動素子。
真空管式の本機「最終アンプ」は、これらの点において、圧倒的な優位性があると確信している。
そこが本機を製作する大きな動機の一つであり、そして結果もそれを裏切らなかった。
なぜ整流管
水銀蒸気整流管の絶対的利点については、当日記「最終アンプ」シリーズで繰り返し紹介してきた。
水銀蒸気整流管は高真空整流管にくらべて、電圧降下が極めて小さく、かつ降下電圧が電流の増減によらずほぼ一定、という優れた特長がある。
そして音質面での期待と可能性も大きい。
83の場合、それらの実験は簡単にできる。
83は、ソケット互換性のある高真空型の整流管の数種類、たとえば5Z3などと挿し替えができるため、電圧降下や音質比較の検証は容易に可能である。
当然ながら、音の違いは個々の被試験アンプによって異なるが、時間をかけて(そこが大切)実験をやってみる価値は大いにあると思う。
それならダイオードでしょ
さて、管内の電圧降下を問題にするのであれば、水銀蒸気整流管の1/10以下の優れた性能のダイオードを使えばいいではないか、という意見にはどう答えるのか。
実は水銀蒸気整流管の83にも、872Aにも、ソケット互換性のある「ダイオード版83」、「ダイオード版872A」(アノードキャップはなく、足に接続されている)が実在する(eBayあたりで時々出品される)。
私は所持していないが、872Aのこれを使った実験には興味がある。
その「ダイオード版83」の「簡易手作り版」、UX4ピンソケットにダイオードを2個付けたものと置き換える実験は、過去にいろいろな種類のダイオードでやってみたことがある。
その結論は、メインアンプにおける83の場合、ダイオードによる置換後の音質は、決して悪くはなかった。
また、ダイオードのスイッチングノイズがどうこう、といった問題も特段の障害にはならなかった。
それでも「整流管」を使うのは、
「わざわざ真空管アンプを作るのに、その電源の整流素子に整流管を使わないという“アンバランス感”(私の美意識的尺度)を曲げてまで、ダイオードを採用するほどの優位性は確認できなかった」
ということに尽きる。
まず本機の発熱量
さて、本機の電源部に話を戻したい。
まずセットの発熱量であるが、出力管211の発熱は大きい。
フィラメント電力10V×3.25A=32.5W。
プレート損失1000V×60mA=60W。
合計でざっと100Wの発熱がある。
872Aも5V×7.5A=37.5Wのフィラメント電力が2本分、80Wほどの発熱がある。
水銀蒸気整流管は管壁温度の制約があり、特に放熱について十分考慮する必要がある。
さらにドライバー管801Aの発熱もあり、真空管だけで合計200Wほどの熱が発生する。
その上、211と801Aのフィラメント直流点火用レギュレータからの発熱も大きい。
ともかく十分な放熱対策をした構造設計をしなければならない。
本機は自然空冷で連続使用が可能なように設計されている。
強制空冷ファンに頼る手もあるが、この程度の規模であれば、自然空冷連続使用を基本仕様とすべきと思う。
実況解説 電源ONから定常状態まで
電源ON
では電源を入れよう。
電源スイッチに指を掛ける前に、まず本機全体を眺め、それぞれの球やアノードキャップの様子などに異常がないかを確認する。
電源ON。
電源スイッチは大昔から変わらない無骨で大きいトグルSWである。
少し重いが意外に感触はよい。
いかにも信頼感があって小気味いい。
冷えて抵抗値が低くなっている合計5本の真空管のフィラメントに一斉に突入電流が流れ、1・2秒の間、過電流によりトランスやフィラメントがブ~ンとうなる。
スイッチONと同時に211と801Aのトリエーテッドタングステン・フィラメントが明るく灯る。

<写真8:電源ONの前の様子>
**水銀蒸気整流管の83と872Aは、長年使用している球なので、管壁内部の汚れた部分がある**
10秒ほど経過
水銀蒸気整流管の872Aと83は、10秒ほど経過すると、早くもフィラメントの熱で蒸発した水銀が、冷えている管壁内面に蒸着し始め、内壁全体が雲ってくる。
もうしばらくすると、その曇りが徐々に鏡のようになり、管の壁面に周囲の景色が映り込む。

<写真9:電源ON後30秒経過>
**83は先の写真3・4などと同じ状況。872Aは管壁内部に凝縮した水銀蒸気が、蒸着された鏡のようになり、床の色が反射して橙色に見える。本当はクロームメッキのような鏡であるが、カメラのホワイトバランスの影響なのか、このような色になった。下手なカメラマンで申し訳ありません。**
実はその「鏡状態」(クロームメッキ状態)を撮りたくて、3度挑戦したが、どうやってもうまく写らなかった。
どうやら、鏡面をそれらしく撮るには、かなり撮影技術の研究が必要なようだ。
2分ほど経過
2分ほど経過すると、鏡になった管壁が、部分的に徐々に晴れて透明になってくる。
管壁の温度が高くなり蒸着した水銀が蒸発するためである。管壁がこの状態になれば、872Aのスタンバイができた目安である。

<写真10:電源ON後3分経過>
**83も872Aも、鏡面であった部分(橙色に見えていた部分)がだいぶ透明になってきた。872Aのフィラメントが見えるようになった。**

<写真11:電源ON後5分経過>
**タイマーリレーによるB電源ONの直前。管壁下部を除いて、ほとんどの部分がクリアになった。872Aの予熱もこれで十分**
5分経過 パシャン!
電源ONから5分後、タイマーリレーが作動してパワーリレーがONになり、B電源用トランスの1次側にAC100Vが供給される。
タイマーリレーの音はほとんど聞こえないが、パワーリレーの音は大きい。
この音の感じも、信頼感があってなかなかいい。
その一瞬、872Aの上部全体が青い光で充満し、すぐに小さくなって安定する。電源部の平滑コンデンサーを充電するための突入電流により、強く発光するためである。
管内電圧降下の少ない水銀蒸気整流管には、この突入電流を制限する意味からも、平滑部はチョークインプット方式であることが必須の条件となる(図1の③の部分)。
タイマーリレーの設定は、水銀蒸気整流管はもとより、211も801Aも、その他諸々の部分も含めて、多少とも熱的ストレスの緩和になるよう、できるだけ長い時間プリヒートした方がよい。
日常、気の向くままに使って20年、突入電流の攻撃も、少なくとも通算2000回を超えていると思う。
電源ON時に何かが壊れたことはまだ一度もないが、劣化したヒューズが断になることはたまにある。
B電源用トランスの2次巻線センターラインに低抵抗を入れるなど、本機のちょっとした安全設計が功を奏していると思っている(図1の②の箇所)。
音を出すまでしばらく放置
B電源が供給された時点で音は出る。しかし長年の習慣から、時間に余裕があるときはそのまま10分~15分以上は放っておく。
半導体アンプの場合もしかり、各種のプレーヤ、DAコンバータなど、すべて同じである。
オーディオ機器のほとんどは寝起きが悪い。目覚めた直後の眠そうな音を聞きたくないため、シャキッと目を覚ますまで待つことにしている。
B電源ON後20分~30分ほど経過すると、872Aの管壁温度の上昇も飽和点に達し、青色グローが鮮やかな色で輝くようになる。
グローは管壁温度が高いほど美しい。
冬よりも夏の方がきれいである。
さあ、もうそろそろ音を出してもいいだろう。
今日も第一声から、思わず身構えてしまうほどのリアル感のある音を期待したい。
水銀蒸気整流管872Aの管壁温度の管理
プリヒートと温度管理が適切でない場合のダメージ
水銀蒸気整流管872Aを使うためには、設計上および使用上の特別な注意が必要である。
まずは管壁の温度管理がある。
「872Aのガラス管最下部(金属ベースのすぐ上)の温度は、20℃~70℃の範囲でなければならない」と、RCA872Aの元箱に同梱されていたデータシートに書かれている。
この球が作られた遠い昔の時代に思いを馳せる茶色に変色した紙であり、折ればパリッと割れてしまうほど乾ききり、しなやかさが失われている。
70℃を超えると、水銀の蒸気圧が上がりすぎて逆耐電圧が下がり(逆電流が流れやすくなって)最悪の場合は内部でスパークが発生し、各部にダメージを与える危険性がある。
20℃~60℃におけるピークプレート逆耐電圧 10000V
20℃~70℃におけるピークプレート逆耐電圧 5000V
となっている。
逆に温度が低いと、十分な蒸気圧が得られないため電圧降下が増し、その結果、陽イオンがカソードへ衝突する速度が速くなり、カソード(=フィラメント)を損傷する危険性がある。
寒冷地では、フィラメントのプリヒート時間を10分以上にすべきだろう。
このように水銀蒸気整流管は、周囲温度と管壁冷却を十分考慮した機体設計をしなければならない。

<写真12:電源ON後30分ほど経過した872Aのガラス管最下部の様子>
**水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

<写真13:同じく電源ON後30分ほど経過した83のガラス管最下部の様子>
**隣の872Aと同様に、水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**
一般の家庭におけるオーディオ機器にとっての「住み心地」は、四季を通して快適な環境を与えられているとは限らない。
室温、つまり雰囲気は、冬は低く夏は高いとも限らない。
冬、各種の暖房機器の熱が直接機器にあたれば、機器の温度は夏よりも高温になる可能性がある。
夏、空調環境が良好な室内であっても、空気流の死角であったり、直射日光が差し込んだり、思わぬ高温になる可能性もある。
これらのことを考えると、本機の設置場所の想定上限の室温を、少なくても30℃以上に置かなくてはならない。30℃を上回る雰囲気において、200W超の発熱がある本機の連続運転の安全確保には、設計上たいへん厳しい対応を迫られる。
近年はパソコン用の「静音ファン」なるものが安価に入手できるので、強制空冷の導入も、高温時の補助としては有効である。
ただし冷却を、全面的にファンに頼る場合は、なんらかの原因でファンが停止したときの安全対策を講じておく必要がある。
家庭用のアンプであれば、ファンの停止を検知して、主電源をOFFにするだけでよい。
本機で体験したことであるが、20年の間には、真夏の熱帯夜に電源を切り忘れ、エアコンが止まった部屋で翌朝まで炎熱地獄を味わわせたことが何度もある。
熱帯夜に、そよ、とも空気のゆらぎがない雰囲気に置かれた本機の筐体は、怖いほどの温度に達したと思われるが、いままで一度も異常事態にはならなかった。
本機の場合、872Aの動作は、定格の、電圧は数分の1、電流にいたっては数10分の1程度の超軽作業しかしていない。
そのため、温度に関するマージンが多少は上がっているのかもしれないが、水銀の蒸気圧が規定の範囲を超えれば、必ずどこかに何らかのダメージを与えるだろう。
その被害がどのようなものになるのか私には分からない。

<写真14:本機の全景(再掲)>
**必要最小限の放熱は、それぞれの真空管まわりの空間の余裕によって確保される。また、発熱量が大きい出力管211と整流管872Aのソケット穴には、通気間隙を設けてある。また直流点火用の電源部の熱は、写真のシャシー右側面に逃がしているため、放熱フィンを取り付けた**
水銀蒸気整流管のプリヒートは長めに
872Aと83がもたらす、音質的に他の整流管では得られない効能を信じている以上、この整流管を安全無事に使い続けなければならない。
繰り返しになるが、水銀蒸気整流管の電源投入時に守らなければならない掟はプリヒートである。
フィラメントとB電源を同時に投入してはならない。
本機では電源ONにより、増幅部を含めて、すべての真空管のフィラメントのプリヒートが始まる。
プリヒート時間は5分ちょうどにセットしてある。
増幅管のフィラメントも同時に点火するため、すべての真空管の熱的ストレスの緩和にも役立っていると思う。
20年間、高圧を加える前の5分間の「準備運動」を、すべてのフィラメントにやらせてきた。
東京近郊の平野部では、冬場の木造家屋でも、5分間の予熱で必要十分だろう。
私の主観的な感覚では、5分以下ではプリヒート上の不安があり、5分以上は使い勝手の上から長すぎる、といったところか。
B電源がONになっても、すぐに音を出すわけではなく、普通はその後10分~15分以上は放っておくが、プリヒートは5分程度で終わってほしい、という意味である。
しかし寒冷地の冬の朝などは、冷え切ったまま電源を入れることを想定すると、10分間ほどのプリヒートが望ましいと思う。
RCA872Aのデータシートによると、周囲温度が10℃~20℃の場合、プリヒート時間は最短2分間、20℃以上の場合は最短1分間、と明記してある。
しかしこれらの記述は、いわゆるカタログデータと受け取り、その数倍のプリヒート時間を与えていただきたい。
RCAのデータシートのグラフによると、フィラメントのプリヒートを開始してから、凝結している水銀の温度が、周囲と熱的平衡に達するまでの時間は、代表例で約30分ほどかかる。
球の形が大きくて重いだけに、872A全体の熱慣性はかなり大きいことに留意されたい。
タイマーリレーとパワーリレー
プリヒート時間とB電源の投入は、タイマーリレーで制御する。
本機は、タイマーリレーの設定時間を5分にしている。
電源スイッチONにより全球のフィラメントが点火し、その5分後に作動するタイマーリレーの接点でパワーリレーを制御し、B電源用トランスの1次側に通電する。
当然のことであるが、タイマーリレー自身の接点をパワーラインのON/OFFに使ってはならない。
その接点の容量が、電圧・電流ともに満足していても使わない。
タイマーリレーは、いわゆる「接点渡し」と呼ばれる、被制御機器を制御するための接点を与えるためのものである。
つまり、相手側のリレーを制御したり、半導体スイッチのゲートを制御するなど、ごく軽い負荷を想定している。
誤った使い方をして、たとえば接点がスパークなどでONのまま貼り付いてしまった場合、次回の電源ONではフィラメントとB電源が同時にONになり、恐ろしいことになる。
タイマーリレーはパワーリレーに比べ、接点やバネが柔である。
「時計係り」には時間だけを計らせておけばよい。
当然であるが、パワーリレーは元来パワーラインをON/FFするためのものであり、電力の開閉に関する信頼性は非常に高い。
信頼性と安全性、それに長期安定性のための設計とはこういうものだ、とは、本機を製作した円通寺坂工房からの受け売りである。

<写真15:本機のタイマーリレーとパワーリレー付近の工作>
**左の白いのがタイマーリレー(定番のOMRON製)。右側の黒いのがパワーリレー。工作はプロ用機器のレベル**
水銀蒸気整流管のための電源部の仕様
水銀蒸気整流管に関連して、本機の電源部の仕様を簡単に紹介させていただきたい。
B電源用トランスは、フィラメント用トランスと分離独立。
またB電源用トランスの2次巻線は、初段用と出力段用と分離独立させている(私の要求は、トランスごと分離独立であったが、筐体の大きさと重量などから断念せざるを得なかった)。
B電源用トランスの仕様は、「AC100V 容量550W」。
初段801A用2次巻線「中点タップ付き450V・650V 80mA」。
出力段211用2次巻線「中点タップ付き1000V・1100V 200mA」。
こういった仕様のものを作ってもらった。
整流部、平滑部とも、初段用と出力段用とは分離独立である。
整流管は初段用に83を1本、出力段用に872Aを2本使う。
いずれも水銀蒸気整流管であり、内部電圧降下が大変小さく、電流の変化による変動も少ない。
平滑部はどちらもチョークインプットである(図1の③部分)。
水銀蒸気整流管を使う場合には必須の条件である。
チョークインプットはフィルターとしての性能が優れているとともに、整流管の耐逆電圧を低くしたり、B電源ON時の突入電流の抑制にも大きな効果がある。
使用するチョークの仕様は、初段801A用に「10H+10Hの50mA」、出力段211用に「10H+10Hの150mA」である。
どちらも可能なかぎり直流抵抗が低いものを作る必要がある。
平滑用のすべてのコンデンサーはフィルム系を採用し、電解コンデンサーは使っていない。
電解コンデンサーは、801Aと211のフィラメントの直流点火用電源に使っているだけである。
平滑用のすべてのコンデンサーをフィルム系としたのは、音質面と長期安定性からの選択である。
「パワーアンプの音質は、電源の音を聴いていると思うべし」。
また、真空管アンプにおける整流管を使った基本的な整流平滑回路の場合、平滑用コンデンサーの容量をむやみに大容量にすると、音質を損なう結果になる、との先達の教えも遵守しなければならない。
なぜそうなのか、私には明確に説明することができないが、電源ON時の突入電流をなるべく小さく短時間に抑え、整流管の過度的な過負荷を軽減する意味からも、容量は必要十分な範囲で最小限に止めておくべきである。

<図1:本機の電源部の全回路図(再掲)>
**①はタイマーリレー部。②は安全設計のための挿入抵抗。③はチョークインプット部分。フィルター入り口のコンデンサーの容量をむやみに大きくすることは厳禁。整流管の寿命に影響する**
家庭用機器として安全・安心・安定設計
本機のような1000Vを扱い、かつ大きな発熱を伴う機器を家庭に持ち込むには、十二分な安全設計を行うことが、すべてに優先される。
また、機器を扱う人には一定の知識が必要であり、家人にも必要最低限のことを話して教えておくべきである。
特に幼児や小さい子供がいる家庭では、絶対に手を触れることができないような対策を講じる必要がある。
本機を取り扱うための必要最低限の知識を持たない人にとって、本機は危険である。
家庭での1000Vの安全対策
温度の次は1000Vの電圧である。これはもっと怖い。事故の状況によっては命にかかわる可能性がある。
幸い私は、まだ1000Vの電撃を喰らったことはないが恐ろしい。
恐れなければならない。
そして少しでも安心できるよう、万全の手を打たねばならない。
特に幼児には厳重な注意が必要である。
いたずらは彼らの仕事であり、それを阻止できない。
彼らがどう知恵をまわしても絶対に手が(スプーンを持った手も)届かないようにすべきである。
872Aの光やアノードキャップなどが興味の対象になってしまった悪夢を考えると血の気が引く。
高圧部の配線の引き回しや線材、端子の処理、半田付けのノウハウなど、高圧を扱うにはかなり専門的な知識が必要になる。
高圧がかかる半田付けの箇所から、先の尖ったヒゲが出ていれば、どのような現象が起こるのか。
電線の被覆に関し、材質・厚み・耐圧の関係はどうなのか。
「プレート電圧1000V」の場合、回路各部の最大ピーク電圧は、どの部分に何ボルトかかるのか。
電源ON時(B電源ON時)、OFF時には、過渡現象によるどのような電圧が、どこに発生するのか。
その他にも、高電圧を取り扱うために必要な知識は種々あると思うが、私はこの方面の専門知識に詳しくなく、これ以上の話ができない。
とにかく使う人はもちろん、その家族も1000Vの怖さを知っておく必要がある。
本物の高圧を扱う人から見れば、1000V程度は高圧のうちに入らないが、ものが一般家庭用娯楽機器のオーディオアンプだけに、やはり1000Vは特別であり危険である。
電源部が要(かなめ)
信号増幅部のクオリティーが上がり、ピュアになればなるほど、聞こえてくるのは「電源の音」である。
つまりメインアンプから出てくる音の源は「電源部」にある。
言い換えれば、メインアンプの音質は「電源部」に支配されている。
このことから、信号増幅部に投入する物量(クオリティーの意味)以上のものを、まず電源部に投下すべきである。
このことは多分、間違ってはいないと思う。
おそらく正しい。
そのことは本機「最終アンプ」が20年、変わりなく元気に歌い続けて体現している。
(最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) おわり)
甦れ(5回)8X コンデンサースピーカー構造の詳細と修復手順 [甦れSTAX ELS-8X コンデンサースピーカ]
比類ない再生音が2つ
STAX ELS-8Xの比類のない再生音。
その秘密は、世界に類のない精緻な作りの発音ユニットと、分厚い木材でがっしりと作られた、広い面積の平面バッフルとの組み合わせにあります。
当時の経営者の、コンデンサースピーカーに懸けた情熱を一身に受けて成長した、本当にすばらしい、まるで嘘のような「作品」です。
当時から8Xは、そのような稀有な存在であったのではないかと思います。
その8Xが2式。
このような事態になろうとは、昨年の今頃は夢にも思わなかったことでした。
製造から30年近く経た今も、まったく健全そのものの姿で朗々と鳴り響く1台と、ほとんどの発音ユニットがダメになり、当ブログに綴っている修復を受けて甦り、オリジナルを凌ぐほどの音を響かせるようになった1台。
それが我が家にあるなど、本当に何が起こったのか不思議な気持ちです。
家内の認可を受けた唯一の機器8X
今年も、はや師走。
昨年の今頃、「瀕死の8X」は狭い納戸に捨て置かれたまま、その存在すら忘れられていました。
家内と一緒に、池袋のサンシャイン60ビルの向かいのマンションの一室にあった、STAXのショールームに出向き、8Xその他を試聴させてもらった思い出のスピーカーです。
後にも先にもオーディオ機器の中で、家内の認可を受けたものは、この時の8Xただ一つです。
そんな思い入れの8Xであり、「いつかは修理して・・」と思いつつも、現実的には無理だろうな、と、ほとんど諦めていました。
それがどうなって、いま現在のような「8Xが2台」の奇跡が起こったのか、私自身も理解できないほどの急展開の1年でした。

<写真1:私の8Xの対ニャン子ディフェンス網>
**家庭の諸般の事情により、だいたい19時から24時頃にかけて、重要機器類が収められている我がオーディオ部屋のセキュリティーは、5匹のニャン子の侵入を阻止できない状況にある。とりわけニャン子の攻撃に弱いのは、トーンアーム系とスピーカー系である。これらがやられては国家の存亡にかかわる。そこで8Xは、少しゆるいが、多少の効果はあるディフェンス「網」を構築した。写真のように、下半分を「虫除けアミ戸」用の、目の粗いネットで、うまく覆った。いくらかは音に影響があると思うが、やむなし**
今日の日記
さて、今日の日記は前回に続き、分解して明らかになった8Xの発音ユニットの構造に、もう一歩迫ります。
さらにはその構造を基礎にして、発音ユニットを修復する工程の大筋を、図面と写真で公開します。
内外の各種のESL(コンデンサースピーカー)の修復や、ESLの研究、また、興味を持たれている方などに、何かの参考の一つにでもなれば幸いです。
8Xを超えるには
8Xの発音ユニットを分解すると、その「作り」が、他のESL(コンデンサースピーカー)と比べて突出して精巧・精密・入念であることが見て取れる。
この「入念な作り」は、かつてのスタックス工業株式会社が、長年にわたってコンデンサースピーカーの音を研究し尽くした「結果」が、形になったものだと思う。
発音ユニットは「こうしなければいい音は出ない」。
材質、形、構造、パンチングメタルの形状と加工、成極電圧、絶縁材と絶縁法、ダイアフラムの材質と導電剤の処理、その他諸々。
私は当時の経営者が「コンデンサー型」製品に懸けた情熱の「結論」を信じたい。
8Xを超えるものを作るには、その人以上の「情熱と年月」が必要である。
そうあるべきだと思う。
戻れない
久し振りに2台の8Xが同時に鳴った。
週末に帰った「かえる息子」が、バッハの教会カンタータなどを聴いている。
その全集のCD Boxの中古を安く買ってきたらしい。
めずらしくボリュームを上げているので、非防音のドアの外に、透き通ったテノールの響きが伝わってくる。
その声に誘われ部屋の中に入ると、そこには豊かな響きの教会の大きな空間が広がっていた。
思わず「いいな」、と声をかける。
「これ聴いたらもう戻れないよ」、と返す。
余談であるが、私がバッハの教会カンタータの魅力に目覚めたきっかけは、今もよく覚えている。
第199番、BWV199「わが心は血の海に泳ぐ」をFM放送で聴いたときである。
まだ学生の頃かもしれない。
ソプラノもオーボエも、旋律が美しい。
まるでオーボエ協奏曲のような部分もある。
それ以降、このジャンルでどれか一つ、といわれれば、今も即答でBWV199をあげる。

<写真2:もう1台の8X>
**「甦れSTAX ELS-8X」でしばしば登場する別の8X。「かえるの息子」が入手した完璧な状態のオリジナル8X。母親は「じゃまだから早く持っていけ」というが、彼のアパートには、もはや置けるスペースはない**
1週間ぶりの私の8X
鳴っていたもう一台は私の8Xである。
PCオーディオ用のパソコンを、新マシン、新OS(といってもWindows7)に移行作業中であったため、ここしばらく、機器に灯が入らなかった。
それがこの週末、まだ不安定ながらも、ようやくPCのライブラリーや、ブルーレイ・ドライブによるCDが再生できるようになった。
Windowsは、VistaやWindows7以降、PCオーディオには問題が多かった従来のMME(オーディオやサウンドのカーネルミキサー)部分に変更が加えられたようである。
しかし周辺の諸々が、その変更に追いついてくるまで、今しばらく時間が必要であり、私の場合、従来のXPでのやり方を、7でも取り敢えず踏襲せざるを得なかった。
私のPCオーディオについては当ブログ「オーディオルームのコンポーネントたち」第2回の「私のPCオーディオと・・」をご訪問いただきたい。
8X修復の留意点
STAX ELS-8Xの発音ユニットは、そもそも修理できるようには作られていない。
その構造を知れば、故障したら修理するなどの考えが、設計当初からまったくなかったことがよく分かる。
なので他社のESLのように、ネジを外して分解し、不具合箇所を修理して、再び組み立てネジ止めして修理完了、といったことができない。
つまり8Xの発音ユニットに「修理マニュアル」は存在しない。
あるとすれば「修理」ではなく「製造マニュアル」であるが、それもないだろう。
製造には手工業的な部分が多く、それを文字にしたマニュアルの記述は困難であり、おそらく職人の口伝・直伝の世界に近かったのではなかったかと思われる。
といった状況なので、もし修復を試みる方がおられたら、まず手始めに1つの発音ユニットを分解し、それの各部の採寸から始めて、詳細な構造を徹底的に調べ上げることからスタートする必要がある。
とにかく、まずは分解だけを目的に、あれこれ試みることである。
修復の各工程には、それぞれ各自が工夫して解決しなければならない問題点が次々と出てくる。
ある問題をクリアするのに、何日も悩むことが何度もあった。
修理不可能なものを強引に修理するのであるから、とにかく一にも二にも「工夫」するしか手はない。
発音ユニットの構造の詳細
さて前回(第4回)の続きとして、発音ユニットの構造図を公開したい。
前回の図を含めてこれらの図から、発音ユニットの基本構造をよく読みとっていただきたい。

<写真3:「二枚おろし」にした発音ユニット(写真は全域・低域ユニット)>
**この写真は、たまたま完璧に半分に分割できた例**
この例では、運良く写真左側のように振動膜が破れずそのまま残った。
フィルムを指先で押してみると、想像を超えた大変強い張力で張られていることが分かった。
周辺のフレームにあけられた穴(2.5mmφ)は、表裏の位置がズレないように分割前にあけておく。
パンチングメタルの放電の痕に黒いサビ等が発生している。
振動膜の電極(銅箔)が左端手前に見える。
また、写真11・12・13で見られる「導通ガイドライン(黒い線)」のオリジナル(フレーム上の白い線)を確認することができる。
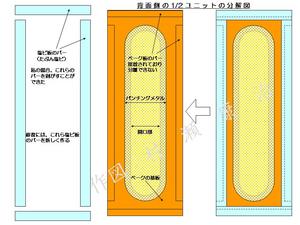
<図1:背面側1/2の分解図>
**前回(第4回)の「二枚おろし」の片側。振動膜の面で真半分に分割した背面側。写真3の右側にあたる。私の場合、水色のバー(1mm厚の塩ビ。色は透明)のみ、図のように剥離できた。これは使い回しせず、塩ビ板から切り出して新しいバーを作る。私は数が多かったので業者に作ってもらった**
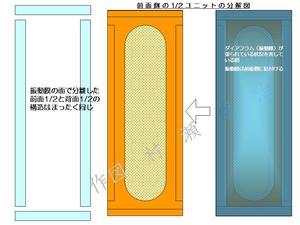
<図2:前面側1/2の分解図>
**写真3の左側にあたる。**
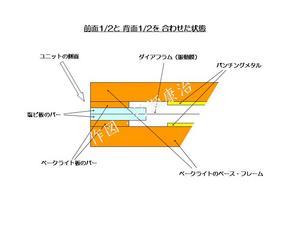
<図3:表裏両面を合わせた状態。>
**元のユニットは、このような状態で各層が接着され、一体になっている。接着剤はたぶんエポキシ系**
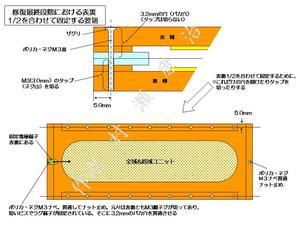
<図4:発音ユニットの修復が完了した後の完成ユニット>
**元のユニットのように接着剤で固定すると、やり直しができないため、図のようにビス止めをする。表裏にあらかじめ2.5mmmの穴をあけてあるので、図のようにそれぞれバカ穴とタッピングを施す。金属のビスは厳禁。ポリカ・ネジを使う。**
さて、これらの図から、発音ユニットの基本構造を読み取ることができたとして、次はユニット修復の作業工程の話に移りたい。
使用した材料や消耗品、使い方、入手法などは、後日の日記で綴ろうと思う。
なお、ユニットの穴あけにはボール盤が必要である。
私はホビー・模型用の卓上ボール盤を使って、すべての作業を行った。
精度不足であるが、そこは技(?)で補い、まあ十分役に立った。
作業工程(大工程)
工程1:二枚おろし
ユニット側面の蝋は除去。
分割前に図4の位置に2.5mmのガイド穴をあけておく。
透明な塩ビのバーの面での剥離を試みて、写真3の状態に分割する。
塩ビのバーは再使用しないので破損してもよい。
パンチングメタルは、その後の作業の前に、マスキングテープで養生しておく。
接着剤等の残留物は、ていねいに取り除き、接着面に凸凹がないように処理をする。
工程2:新しい塩ビ・バーの接着
分割されたユニットはソリが出るので、写真10・12・13にあるような治具(私の場合はアルミチャンネルを利用
)を用意しておく(ユニット両端を治具にビス止めしてソリを防ぐ)。
そのあと、あらかじめ寸法に合わせて作っておいた塩ビ・バーを元のように接着する。
工程3:枠にあけた穴の処理
ユニットの分割前にあけた穴を、片側は3.2mmのバカ穴をあけてサグリ。
もう一方はM3のタップを切る。

<写真4:3.2mmのバカ穴とザグリ>
**本体の表側に当たる1/2ユニットの穴の処理。パンチングメタルやその周囲の蝋コーティングを保護するために、マスキングテープでしっかり養生しておく(重要)。高電圧がかかるので、ゴミ、埃、異物などの混入はあってはならない**
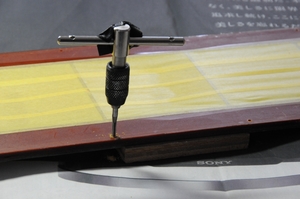
<写真5:裏側ユニットのM3タッピング>
**穴の数が多く、大変しんどい作業になるが、がんばるしかない**
工程4:ダイアフラムを大枠に張る
私の場合は3ミクロン厚のポリエステルフィルムを使った。
写真のように木枠を作り、布テープでコーティングしておく(フィルムとの馴染みがよい)。
適当にフィルムを張った後、張力が全方向に均等にかかるよう、セロハンテープで徐々に張り締めていく。
この張り締めを十分な張力に達するまで数回繰り返す。

<写真6:大きめの木枠の準備>
**しっかりした木材で、がっちりとしたフレームを作る。角は金具で補強する。フレームは布テープでコーティングしておくと、フィルム張りの作業に都合がよい**

<写真7:あまりシワが寄らないようにフィルムをそーっと置いていく>
**写真のように、マスキングテープをうまく活用する**

<写真8:フィルムを張り締めていく最初の状態>
**まだ張力はかかっていない**

<写真9:フィルム張り締め完了>
**全方向均等に張り締めていく。数cmに切ったセロハンテープで、マスキングテープ上を次々と引っ張って張り締めていく。感覚としては、破断1.5歩手前でよい。最初に一度、破断するまで実地検証することをお勧めします**
工程5:フィルムへの導電剤コーティング
この工程がもっとも神経を使う緊張の場面となる。
すばやく、ていねいに、むらなく、確実に作業しなければならない。
極力埃の少ない部屋での作業が望まれる。
本来はクリーンルームで行う作業である。
私は風呂場で行った。
写真の撮影どころではないので写真なし。
すみません。
材料や手順の詳細は後日の日記で。
工程6:木枠フィルムをユニット枠へ接着
ユニット側をかさ上げして、木枠が「宙ぶらりん」になるように準備をしておいてから接着する。
鋭利な突起物でもないかぎり、木枠の重みでフィルムが破れることはない。
切り離しはカッターナイフか半田ごてで行う。

<写真10:ユニットの枠に木枠のフィルムを接着>
**不織布ワイパーをたたみ、接着面を押さえて確実に接着させる。その後は木枠の重みで自然に圧着させておき、乾燥を待つ。不織布ワイパーは、入手が容易な写真6にある「BEMCOT M-3Ⅱ」を使った(フィルムへの導電剤コーティングの作業にも、これを使う)**
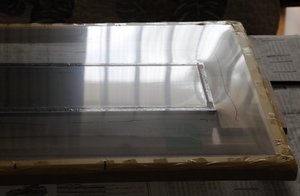
<写真11:ユニットの枠に木枠のフィルムを接着のアップ>
**フィルム全面の電荷が均等になるように、導電塗料で導通ガイドラインをフレームに描いた(黒い線)。セロハンテープで張り締めの様子も見える**
工程7:導通ガイドラインをフレームに描き、端子を接着
フィルム全面の電荷が均等になるように、導電塗料を枠の四辺に「井桁」状に書き、振動膜の端子を付ける(習字の筆を使った)。
端子は導通性粘着剤の銅箔テープを使った。

<写真12:振動膜フィルムの貼り付け作業完了>
**フィルムで塞がれたフレームの穴の部分は、半田ごての先端であけておく**
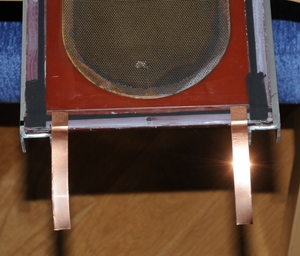
<写真13:振動膜の端子を付ける>
**このユニットを本体のどこに取り付けるか決めてなかったので、端子を両端に出したが、無駄な放電可能性の存在は好ましくない。片側のみに設けるべきである。**
工程8:表裏1/2のユニットを合わせ、ポリカ・ビスで固定
ユニット表面にビスの突起があると、本体への固定の際の障害になる(短辺のビスとナットは問題ない)。
組み立て後、防塵用のネット(洗剤で洗った後、使いまわし)を接着する。

<写真14:組み立て終わったユニット(上)と、次に修復を受けるユニット(下)>
**修復後の外観はこのようになる**
工程9:四辺の側面に絶縁テープを巻く
オリジナルのユニットのその部分は、蝋でコーティングされている。
最終的には蝋で処理したいが、当面は絶縁テープで代用して、しばらく(1年間ほどか)様子をみる。
調べてみたが、蝋の種類やその入手法が分からない。
このあとは本体に取り付けて、音出しテストとなる。
手作業品の修復は、一にも二にも「工夫」あるのみ
これらの写真を見るだけでも、8Xの元の発音ユニットが、いかに手工業的に作られていたかが分かると思います。
さらに修復には、新品の組み立て作業にはないような、厄介な問題があちこちに発生します。
それらを「工夫」によって一つひとつ解決していかねばなりません。
でもまあ、ユニットの修復も、3つ目か4つ目になると、工程や手順もいろいろ修正され、あとはもう「その道の職人」になったような調子で作業できるようになるものです。
そこまで行けば、手間と、やたらと時間のかかる作業を、ルーチンワーク的にやるだけになりますが、それほど根気が続くものでもありません。
そしてやってみて分かった大事なことを一つ。
たとえば10個ほどのユニットを修復するには、マスキングテープ(幅は各種)、セロハンテープ、不織布ワイパー、絶縁テープ(布製、ゴム系各種)、接着剤、アルコール(無水エタノール)、ティッシュペーパーなどを、大量に消費します。
これらを惜しみなく、湯水のごとく使わなければ、いい仕上がりになりません。
またこれらを含めて、一切の材料や消耗品は、必ず一流メーカー品を使うことをお勧めします。
接着剤を使うために時間に追われ、また息を止めて一発勝負でやる作業もあり、粗悪品でモタモタしている場合ではありません。
オーディオ道楽だから、また深い想い入れのある8Xだからこそやれた、そうでなければやってられない、面倒この上もない、しんどくも楽しい作業でした。
次回の日記は、振動膜への導電剤の塗布を中心に綴ろうかと思います。
ドキドキしてスリル満点の作業です。
(甦れ8X(5)構造と修復の核心部公開 おわり)
STAX ELS-8Xの比類のない再生音。
その秘密は、世界に類のない精緻な作りの発音ユニットと、分厚い木材でがっしりと作られた、広い面積の平面バッフルとの組み合わせにあります。
当時の経営者の、コンデンサースピーカーに懸けた情熱を一身に受けて成長した、本当にすばらしい、まるで嘘のような「作品」です。
当時から8Xは、そのような稀有な存在であったのではないかと思います。
その8Xが2式。
このような事態になろうとは、昨年の今頃は夢にも思わなかったことでした。
製造から30年近く経た今も、まったく健全そのものの姿で朗々と鳴り響く1台と、ほとんどの発音ユニットがダメになり、当ブログに綴っている修復を受けて甦り、オリジナルを凌ぐほどの音を響かせるようになった1台。
それが我が家にあるなど、本当に何が起こったのか不思議な気持ちです。
家内の認可を受けた唯一の機器8X
今年も、はや師走。
昨年の今頃、「瀕死の8X」は狭い納戸に捨て置かれたまま、その存在すら忘れられていました。
家内と一緒に、池袋のサンシャイン60ビルの向かいのマンションの一室にあった、STAXのショールームに出向き、8Xその他を試聴させてもらった思い出のスピーカーです。
後にも先にもオーディオ機器の中で、家内の認可を受けたものは、この時の8Xただ一つです。
そんな思い入れの8Xであり、「いつかは修理して・・」と思いつつも、現実的には無理だろうな、と、ほとんど諦めていました。
それがどうなって、いま現在のような「8Xが2台」の奇跡が起こったのか、私自身も理解できないほどの急展開の1年でした。

<写真1:私の8Xの対ニャン子ディフェンス網>
**家庭の諸般の事情により、だいたい19時から24時頃にかけて、重要機器類が収められている我がオーディオ部屋のセキュリティーは、5匹のニャン子の侵入を阻止できない状況にある。とりわけニャン子の攻撃に弱いのは、トーンアーム系とスピーカー系である。これらがやられては国家の存亡にかかわる。そこで8Xは、少しゆるいが、多少の効果はあるディフェンス「網」を構築した。写真のように、下半分を「虫除けアミ戸」用の、目の粗いネットで、うまく覆った。いくらかは音に影響があると思うが、やむなし**
今日の日記
さて、今日の日記は前回に続き、分解して明らかになった8Xの発音ユニットの構造に、もう一歩迫ります。
さらにはその構造を基礎にして、発音ユニットを修復する工程の大筋を、図面と写真で公開します。
内外の各種のESL(コンデンサースピーカー)の修復や、ESLの研究、また、興味を持たれている方などに、何かの参考の一つにでもなれば幸いです。
8Xを超えるには
8Xの発音ユニットを分解すると、その「作り」が、他のESL(コンデンサースピーカー)と比べて突出して精巧・精密・入念であることが見て取れる。
この「入念な作り」は、かつてのスタックス工業株式会社が、長年にわたってコンデンサースピーカーの音を研究し尽くした「結果」が、形になったものだと思う。
発音ユニットは「こうしなければいい音は出ない」。
材質、形、構造、パンチングメタルの形状と加工、成極電圧、絶縁材と絶縁法、ダイアフラムの材質と導電剤の処理、その他諸々。
私は当時の経営者が「コンデンサー型」製品に懸けた情熱の「結論」を信じたい。
8Xを超えるものを作るには、その人以上の「情熱と年月」が必要である。
そうあるべきだと思う。
戻れない
久し振りに2台の8Xが同時に鳴った。
週末に帰った「かえる息子」が、バッハの教会カンタータなどを聴いている。
その全集のCD Boxの中古を安く買ってきたらしい。
めずらしくボリュームを上げているので、非防音のドアの外に、透き通ったテノールの響きが伝わってくる。
その声に誘われ部屋の中に入ると、そこには豊かな響きの教会の大きな空間が広がっていた。
思わず「いいな」、と声をかける。
「これ聴いたらもう戻れないよ」、と返す。
余談であるが、私がバッハの教会カンタータの魅力に目覚めたきっかけは、今もよく覚えている。
第199番、BWV199「わが心は血の海に泳ぐ」をFM放送で聴いたときである。
まだ学生の頃かもしれない。
ソプラノもオーボエも、旋律が美しい。
まるでオーボエ協奏曲のような部分もある。
それ以降、このジャンルでどれか一つ、といわれれば、今も即答でBWV199をあげる。

<写真2:もう1台の8X>
**「甦れSTAX ELS-8X」でしばしば登場する別の8X。「かえるの息子」が入手した完璧な状態のオリジナル8X。母親は「じゃまだから早く持っていけ」というが、彼のアパートには、もはや置けるスペースはない**
1週間ぶりの私の8X
鳴っていたもう一台は私の8Xである。
PCオーディオ用のパソコンを、新マシン、新OS(といってもWindows7)に移行作業中であったため、ここしばらく、機器に灯が入らなかった。
それがこの週末、まだ不安定ながらも、ようやくPCのライブラリーや、ブルーレイ・ドライブによるCDが再生できるようになった。
Windowsは、VistaやWindows7以降、PCオーディオには問題が多かった従来のMME(オーディオやサウンドのカーネルミキサー)部分に変更が加えられたようである。
しかし周辺の諸々が、その変更に追いついてくるまで、今しばらく時間が必要であり、私の場合、従来のXPでのやり方を、7でも取り敢えず踏襲せざるを得なかった。
私のPCオーディオについては当ブログ「オーディオルームのコンポーネントたち」第2回の「私のPCオーディオと・・」をご訪問いただきたい。
8X修復の留意点
STAX ELS-8Xの発音ユニットは、そもそも修理できるようには作られていない。
その構造を知れば、故障したら修理するなどの考えが、設計当初からまったくなかったことがよく分かる。
なので他社のESLのように、ネジを外して分解し、不具合箇所を修理して、再び組み立てネジ止めして修理完了、といったことができない。
つまり8Xの発音ユニットに「修理マニュアル」は存在しない。
あるとすれば「修理」ではなく「製造マニュアル」であるが、それもないだろう。
製造には手工業的な部分が多く、それを文字にしたマニュアルの記述は困難であり、おそらく職人の口伝・直伝の世界に近かったのではなかったかと思われる。
といった状況なので、もし修復を試みる方がおられたら、まず手始めに1つの発音ユニットを分解し、それの各部の採寸から始めて、詳細な構造を徹底的に調べ上げることからスタートする必要がある。
とにかく、まずは分解だけを目的に、あれこれ試みることである。
修復の各工程には、それぞれ各自が工夫して解決しなければならない問題点が次々と出てくる。
ある問題をクリアするのに、何日も悩むことが何度もあった。
修理不可能なものを強引に修理するのであるから、とにかく一にも二にも「工夫」するしか手はない。
発音ユニットの構造の詳細
さて前回(第4回)の続きとして、発音ユニットの構造図を公開したい。
前回の図を含めてこれらの図から、発音ユニットの基本構造をよく読みとっていただきたい。

<写真3:「二枚おろし」にした発音ユニット(写真は全域・低域ユニット)>
**この写真は、たまたま完璧に半分に分割できた例**
この例では、運良く写真左側のように振動膜が破れずそのまま残った。
フィルムを指先で押してみると、想像を超えた大変強い張力で張られていることが分かった。
周辺のフレームにあけられた穴(2.5mmφ)は、表裏の位置がズレないように分割前にあけておく。
パンチングメタルの放電の痕に黒いサビ等が発生している。
振動膜の電極(銅箔)が左端手前に見える。
また、写真11・12・13で見られる「導通ガイドライン(黒い線)」のオリジナル(フレーム上の白い線)を確認することができる。
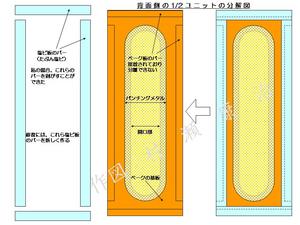
<図1:背面側1/2の分解図>
**前回(第4回)の「二枚おろし」の片側。振動膜の面で真半分に分割した背面側。写真3の右側にあたる。私の場合、水色のバー(1mm厚の塩ビ。色は透明)のみ、図のように剥離できた。これは使い回しせず、塩ビ板から切り出して新しいバーを作る。私は数が多かったので業者に作ってもらった**
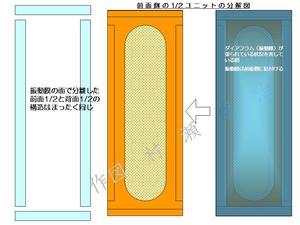
<図2:前面側1/2の分解図>
**写真3の左側にあたる。**
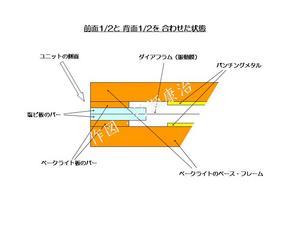
<図3:表裏両面を合わせた状態。>
**元のユニットは、このような状態で各層が接着され、一体になっている。接着剤はたぶんエポキシ系**
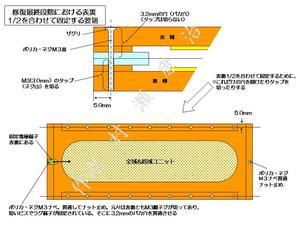
<図4:発音ユニットの修復が完了した後の完成ユニット>
**元のユニットのように接着剤で固定すると、やり直しができないため、図のようにビス止めをする。表裏にあらかじめ2.5mmmの穴をあけてあるので、図のようにそれぞれバカ穴とタッピングを施す。金属のビスは厳禁。ポリカ・ネジを使う。**
さて、これらの図から、発音ユニットの基本構造を読み取ることができたとして、次はユニット修復の作業工程の話に移りたい。
使用した材料や消耗品、使い方、入手法などは、後日の日記で綴ろうと思う。
なお、ユニットの穴あけにはボール盤が必要である。
私はホビー・模型用の卓上ボール盤を使って、すべての作業を行った。
精度不足であるが、そこは技(?)で補い、まあ十分役に立った。
作業工程(大工程)
工程1:二枚おろし
ユニット側面の蝋は除去。
分割前に図4の位置に2.5mmのガイド穴をあけておく。
透明な塩ビのバーの面での剥離を試みて、写真3の状態に分割する。
塩ビのバーは再使用しないので破損してもよい。
パンチングメタルは、その後の作業の前に、マスキングテープで養生しておく。
接着剤等の残留物は、ていねいに取り除き、接着面に凸凹がないように処理をする。
工程2:新しい塩ビ・バーの接着
分割されたユニットはソリが出るので、写真10・12・13にあるような治具(私の場合はアルミチャンネルを利用
)を用意しておく(ユニット両端を治具にビス止めしてソリを防ぐ)。
そのあと、あらかじめ寸法に合わせて作っておいた塩ビ・バーを元のように接着する。
工程3:枠にあけた穴の処理
ユニットの分割前にあけた穴を、片側は3.2mmのバカ穴をあけてサグリ。
もう一方はM3のタップを切る。

<写真4:3.2mmのバカ穴とザグリ>
**本体の表側に当たる1/2ユニットの穴の処理。パンチングメタルやその周囲の蝋コーティングを保護するために、マスキングテープでしっかり養生しておく(重要)。高電圧がかかるので、ゴミ、埃、異物などの混入はあってはならない**
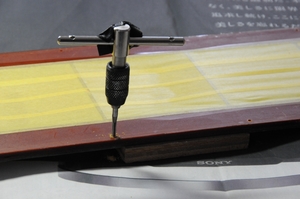
<写真5:裏側ユニットのM3タッピング>
**穴の数が多く、大変しんどい作業になるが、がんばるしかない**
工程4:ダイアフラムを大枠に張る
私の場合は3ミクロン厚のポリエステルフィルムを使った。
写真のように木枠を作り、布テープでコーティングしておく(フィルムとの馴染みがよい)。
適当にフィルムを張った後、張力が全方向に均等にかかるよう、セロハンテープで徐々に張り締めていく。
この張り締めを十分な張力に達するまで数回繰り返す。

<写真6:大きめの木枠の準備>
**しっかりした木材で、がっちりとしたフレームを作る。角は金具で補強する。フレームは布テープでコーティングしておくと、フィルム張りの作業に都合がよい**

<写真7:あまりシワが寄らないようにフィルムをそーっと置いていく>
**写真のように、マスキングテープをうまく活用する**

<写真8:フィルムを張り締めていく最初の状態>
**まだ張力はかかっていない**

<写真9:フィルム張り締め完了>
**全方向均等に張り締めていく。数cmに切ったセロハンテープで、マスキングテープ上を次々と引っ張って張り締めていく。感覚としては、破断1.5歩手前でよい。最初に一度、破断するまで実地検証することをお勧めします**
工程5:フィルムへの導電剤コーティング
この工程がもっとも神経を使う緊張の場面となる。
すばやく、ていねいに、むらなく、確実に作業しなければならない。
極力埃の少ない部屋での作業が望まれる。
本来はクリーンルームで行う作業である。
私は風呂場で行った。
写真の撮影どころではないので写真なし。
すみません。
材料や手順の詳細は後日の日記で。
工程6:木枠フィルムをユニット枠へ接着
ユニット側をかさ上げして、木枠が「宙ぶらりん」になるように準備をしておいてから接着する。
鋭利な突起物でもないかぎり、木枠の重みでフィルムが破れることはない。
切り離しはカッターナイフか半田ごてで行う。

<写真10:ユニットの枠に木枠のフィルムを接着>
**不織布ワイパーをたたみ、接着面を押さえて確実に接着させる。その後は木枠の重みで自然に圧着させておき、乾燥を待つ。不織布ワイパーは、入手が容易な写真6にある「BEMCOT M-3Ⅱ」を使った(フィルムへの導電剤コーティングの作業にも、これを使う)**
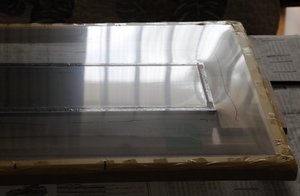
<写真11:ユニットの枠に木枠のフィルムを接着のアップ>
**フィルム全面の電荷が均等になるように、導電塗料で導通ガイドラインをフレームに描いた(黒い線)。セロハンテープで張り締めの様子も見える**
工程7:導通ガイドラインをフレームに描き、端子を接着
フィルム全面の電荷が均等になるように、導電塗料を枠の四辺に「井桁」状に書き、振動膜の端子を付ける(習字の筆を使った)。
端子は導通性粘着剤の銅箔テープを使った。

<写真12:振動膜フィルムの貼り付け作業完了>
**フィルムで塞がれたフレームの穴の部分は、半田ごての先端であけておく**
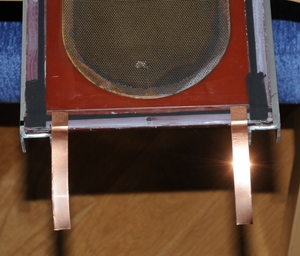
<写真13:振動膜の端子を付ける>
**このユニットを本体のどこに取り付けるか決めてなかったので、端子を両端に出したが、無駄な放電可能性の存在は好ましくない。片側のみに設けるべきである。**
工程8:表裏1/2のユニットを合わせ、ポリカ・ビスで固定
ユニット表面にビスの突起があると、本体への固定の際の障害になる(短辺のビスとナットは問題ない)。
組み立て後、防塵用のネット(洗剤で洗った後、使いまわし)を接着する。

<写真14:組み立て終わったユニット(上)と、次に修復を受けるユニット(下)>
**修復後の外観はこのようになる**
工程9:四辺の側面に絶縁テープを巻く
オリジナルのユニットのその部分は、蝋でコーティングされている。
最終的には蝋で処理したいが、当面は絶縁テープで代用して、しばらく(1年間ほどか)様子をみる。
調べてみたが、蝋の種類やその入手法が分からない。
このあとは本体に取り付けて、音出しテストとなる。
手作業品の修復は、一にも二にも「工夫」あるのみ
これらの写真を見るだけでも、8Xの元の発音ユニットが、いかに手工業的に作られていたかが分かると思います。
さらに修復には、新品の組み立て作業にはないような、厄介な問題があちこちに発生します。
それらを「工夫」によって一つひとつ解決していかねばなりません。
でもまあ、ユニットの修復も、3つ目か4つ目になると、工程や手順もいろいろ修正され、あとはもう「その道の職人」になったような調子で作業できるようになるものです。
そこまで行けば、手間と、やたらと時間のかかる作業を、ルーチンワーク的にやるだけになりますが、それほど根気が続くものでもありません。
そしてやってみて分かった大事なことを一つ。
たとえば10個ほどのユニットを修復するには、マスキングテープ(幅は各種)、セロハンテープ、不織布ワイパー、絶縁テープ(布製、ゴム系各種)、接着剤、アルコール(無水エタノール)、ティッシュペーパーなどを、大量に消費します。
これらを惜しみなく、湯水のごとく使わなければ、いい仕上がりになりません。
またこれらを含めて、一切の材料や消耗品は、必ず一流メーカー品を使うことをお勧めします。
接着剤を使うために時間に追われ、また息を止めて一発勝負でやる作業もあり、粗悪品でモタモタしている場合ではありません。
オーディオ道楽だから、また深い想い入れのある8Xだからこそやれた、そうでなければやってられない、面倒この上もない、しんどくも楽しい作業でした。
次回の日記は、振動膜への導電剤の塗布を中心に綴ろうかと思います。
ドキドキしてスリル満点の作業です。
(甦れ8X(5)構造と修復の核心部公開 おわり)
コンポ(2)私のPCオーディオと青春デンデケデケデケ [オーディオルームのコンポーネントたち]
今回の日記は、「PCオーディオ」について綴ります。
「アナログよりもアナクロだね」といわれている私ですが、一応、PCオーディオも、PCのUSBポートなどが普及する以前から細々ながらやっていました(^-^)。
そもそも「PCオーディオ」とはなんでしょう。
私のイメージでは「パソコンを利用してピュアオーディオをやること」ぐらいに考えています。
と、その前に「ピュアオーディオ」って言葉もよく分かりませんね。
この言葉、私の解釈は「純粋オーディオ」といった感じではありません。
私の感覚では、
「ピュアオーディオ」とは、「オーディオを真面目に、熱心に追求すること」。
だと思います。
つまり「オーディオに真摯に向き合う」
だから映像に付随するサウンドトラックの音も「ピュアオーディオ」の対象です。
MP3に代表されるような、データー圧縮も「ピュアオーディオ」の対象です。
そういったものを排除するよりも、取り込んだ方が、ずっと面白くなると思います。
48Kbpsの最低のビットレートでも人は感動できる
私のPCオーディオのライブラリーに、2012年の2月に録音した、平原綾香が歌う「あいたくて」が収まっています。
NHKのラジオ深夜便の「深夜便の歌」(2012年2月時の)を、ネット配信ラジオ「らじるらじる」から別アプリでダウンロードしたものです。
「らじるらじる」の配信ビットレートは48Kbpsであり、「もう最低」といえるほどの低いレートですが、これをメインシステムできちんと聴くと、
感動します。
48Kbpsでも、人の心を激しく動かすことができる、という一例です。
さて私のPCオーディオですが、現在は、CDを直接聴く場合も、プレーヤーソフトの「WINAMP」を起動して、PCに装備されているブルーレイ・ドライブで再生しています。
その方が現有の3台のCDプレーヤーより、一段上の音がします(もちろん同一のD/Aコンバータを使って)。
また、いわゆる「my favourite music」は、PCにデジタルアーカイブされつつあり、普段はたいてい、PCのライブラリーから「WINAMP」で聴いています。
PC上の再生ソフトは、foobar2000を始め、いくつかを遍歴しましたが、いつも落ち着き先は、結局、総合的な観点からWINAMPに帰ります。
デジタルアーカイブの作業中にお宝テープを発見
そしてもう一つの、PCオーディオに関係するお話。
過去、FM放送や衛星PCM放送などを録り溜めた、何百本ものDATテープの中から発見した「青春デンデケデケデケ」です。
DATをPCにデジタルアーカイブする作業中に見つけました。
1991年の直木賞に輝いた同名の青春小説の著者、「芦原すなお」をゲストに招いたNHK FM午後の人気番組、1993年4月21日放送「ポップスステーション」のエアチェックテープです。

<写真1:「青春デンデケデケデケ」の文庫本と映画のDVD、それとDATテープ>
**本は、直木賞本(元原稿の短縮版)と、ノーカット版とがある。写真はもちろんノーカット版。映画の監督は大林宣彦。**

<写真2:著者の「芦原すなお」をゲストに招いたNHK FM「ポップスステーション」の録音テープ(DAT)。番組内容はFM誌「FMfan」の番組表の切り抜き。最下段に「芦原すなお」の名がある>

<写真3:DVDのパッケージ裏表紙>
**興味を持たれた方々、たぶんベンチャーズ世代の方々の参考までに**
「青春デンデケデケデケ」は、ベンチャーズ世代や、あまたのベンチャーズバンドを結成している面々にはよく知られた直木賞本であり映画でした。
私もその世代の一人です。
しかしその当時、著者をゲストに迎えたFMの2時間番組を聴いた方は、そう多くはないでしょう。
聴いたとしても、たぶん覚えていないでしょう。
ましてや、それを完全エアチェックしたDATテープが現存するなど、私自身もまったく覚えがない、うそのような話です。
発見以来、この録音は何回も聴いていますが、60年代にラジオ関西の電話リクエストで育ったOldiesファンの私は、聴くたびにたまらなく嬉しくなります。
本の内容にまつわる曲を、ベンチャーズの「パイプライン」に始まり、再度シャンティーズの「パイプライン」で締めくくるまでの13曲を、DJの宮本啓と著者との掛合いとともに、2時間たっぷり楽しめます。
と、このように「青春デンデケデケデケ」を発見することになった作業中のデジタルアーカイブが、今日の日記のもう一つの話です。
※(衛星PCM放送のミュージックバードは、数年前にサービス終了になってしまった)
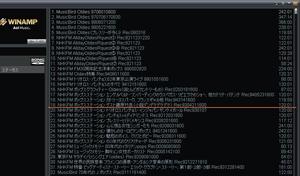 <PC画面1:WINAMPで開いたライブラリの「洋楽ポップス」のリストの一部>
<PC画面1:WINAMPで開いたライブラリの「洋楽ポップス」のリストの一部>
**DATテープをデジタルアーカイブした中の、ジャンル「洋楽ポップス」の一部。「青春デンデケデケデケ」は1993年4月21日の16:00時に録音したもので、録音長120分との情報を付けてある。「ゲスト藤原竹良」とは著者の本名。このリストの聴きたいものをダブルクリックすると、WINAMPによる再生が始まる**
録り溜めた放送音源を聴きたい
さて、20年以上も前から録り溜めたDAT(digital audio tape)のカセットを詰め込んだダンボール箱が数個ある。
こんなに沢山、何を思って録ったのか、今思えば後悔している。
もっと的を絞って録ればよかった。
たぶん現役を引退して暇になったら聴こう、などと甘く考えていたのだと思う。
ひたすら録っていた頃も、「全部聴くのは無理だろう」とは薄々感じていた。
しかし「音楽放送」には、CDやレコードでは絶対に真似のできないところがある。
たとえば、NHK FMで毎週月~金の19:30から始まるベストオブクラシック。
NHK ONLINEのページにあるこの番組の能書きには「世界中の上質な演奏会をじっくり堪能する本格派クラシック番組」とある。
演奏会のライブ録音は、CDなど他のメディアでも珍しいことではない。
しかし、演奏家や音楽関係者などのゲストを呼んで話を聞いたり、音楽放送作家が要領よくまとめた原稿を番組司会者が上手に語ったり、こういったところは、「放送」の独壇場である。
なによりも実況録音は、会場の拍手やざわめきなど、場の雰囲気の録り方がまったく異なり、臨場感がすばらしい(音質のことではない)。
逆にそれがウザイ、などと思う方もおられると思うが、音楽のジャンルにかかわらず、そういった放送の場における話は、他では聞けない興味ある内容であることが多い。
テープの山、分別しなければゴミの山
さて、自適生活になって分かったが、ダンボールに詰め込まれたDATカセットを一つひとつ取り出しては聴く、などと悠長なことをやってるほどの暇はない。
時間はたっぷりある、と思っていたが、なぜか暇はさほどない。
そこでテープの内容が分かっているものから、優先順位をつけて(つまり自分好みの順に)、どんどんデジタルアーカイブ化していこう、と決心した。
そうでもしないと、整理かつかない。
とにかく「整理」しないと聴くどころではなく、手がつけられない。
家庭ゴミ、分別すれば「資源」、しなければただの「ゴミ」。
それと同じである。
デジタルライブラリーの構築に、最近のパソコンは大変な威力がある。
HDユニットの容量も、1T(テラバイト)2Tは当たり前になった。
処理速度が高速なので、音楽データの編集も、なんのストレスもなくサクサクできる。
PCオーディオ環境を充実させるための各種のソフトも豊富になった。
まあ、なにはともあれ「ゴミ」からの脱却が先決である。
そこで昨年の暮れあたりから、猛然とDATテープのデジタルアーカイブ化を開始した。
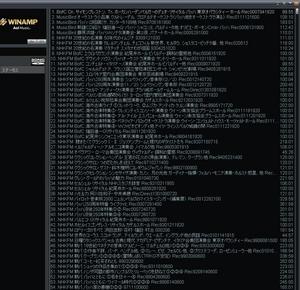
<PC画面2:WINAMPで開いたライブラリの「クラシック」のリストの一部>
**このリスト上では、1992年録音が一番古い。「Bof C」は「ベストオブクラシック」、「朝バ」はFMの長寿番組「朝のバロック」のこと。録り溜めた中では「朝バ」のテープがダントツに多い。右端の欄は録音時間長**
私の「PCオーディオ」黎明期
私がPCでオーディオ的なことをやり始めたのは、まだUSBが普及する以前、iPod、iTunesが登場する前の時代であった。
当時、PCで「音」を扱うには、大抵の場合、「サウンドボード(カード)」が必要であった。
PCのマザーボードには、デジタル入出力の端子など付いていなかった。
CDプレイヤーの光出力や、その他の音源のデジタルデーターなどをPCに取り込むには、光入力端子などのデジタル入力端子が付いたサウンドカードを必要とした。
ところがこれが曲者であり、ほとんどのサウンドカードは(そのドライバーとも絡むが)、デジタルの入力データを、そのバイナリコードの変化なしにPCに取り込むことができなかった。
出力も同じであった。
それを反映して当時のネットでは、音源のデジタルデータをいかにして「1対1」、「100%同じ」、「1ビットの変化もなしに」、PCに取り込み、またそれを出力するか、のノウハウについての記事で賑わっていた。
サウンドカードの改造や、自作もしなければならなかった。
そういった時代であった。
PCオーディオの絶対条件「1ビットたりとも変化なし」
今現在でもPCオーディオの世界において、ユーザーの意識から「抜け落ちている」のではないかと危惧される、たいへん重要なことがある。
外部の音源のデジタルデータを、「1ビットの変化もなしに」PCに取り込み、また、取り込んだデジタルデーターを、「1ビットの変化もなしに」PCから出力する。
という当たり前のことが、実はWindowsマシンでは、そう簡単にできない。
何をいっているのかと驚くほどの「とんでもない話」であるが事実である。
デジタルオーディオにおいて、データーの意識的な操作や加工は別として(ミキサーソフトで音を操作したり、MP3などで圧縮したりなどは別として)、何かの装置を通ったらデーターが変化した、などは論外である。
データーの欠損が発生したとか、化けたとか、データーが壊れたといったことではない(それは障害、故障、設備不良の範疇)。
変化したデーターを復調して(D/A変換して)、その音をちょっと聞いただけでは分からないデジタルデータの変化である。
データー的には矛盾が発生したわけではない。
具体的には、音量の変化とか、音質調整のイコライザーが入ったとか、サンプリングレート・コンバーターが介在したとか、そういった意味でのデーターの変化である。
ところがこの点に無頓着な方が意外に多い。
多分、デジタルだからそのようなことは起こらない、と頭から信じているのだろう。
それは無理もないことだと思う。
しかしWindowsのPC上で、一般的な入出力デバイスとサウンドソフトを使う場合、よほどその点に留意しないと「データーの同一性」は保障の限りではない。
PCオーディオの黎明期、PCを十分なクオリティーでオーディオに利用しようとしていた挑戦者たちの第一の目標は、この「データーの同一性」の実現に集中していた。
そこが保障されなければ、PCオーディオの成立などあり得ない。
そこがPCオーディオの基本中の基本であるはずだ。
これほどの最重要課題であるにもかかわらず、Windowsマシンでは、特別な細工をしなければ実現できないのである。
少なくともWindows xpまではそうであった。
それ以降はまだ調べてもいないし、検証もしていない。
(今現在、私のPCオーディオ環境を、Windows7へ移行するために、PCとも更新作業中です)
ASIOが解決した「データーの同一性」
「ASIO」(アジオ:Audio Stream Input Output)とは、ここではとりあえず、WindowsのMME(Multi Media Extension:オーディオデバイスのドライバ・インタフェース)をバイパスする仕掛け、と考えておけばいいと思う。
ASIOを適応した場合、「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」などのサウンドやオーディオに関するソフトは、そのレベルコントロールをはじめ、左右のバランス、音質を変えるイコライザーなど、各種の調整が無効になる。
その代わりに、Windows内で、データーの変化は起こらない。
またDTM(デスクトップミュージック)の世界では、「レイテンシー」と呼ばれる「音声信号の入出力の命令を出してから、それが実行されるまでのタイムラグ」が大きな問題になる。
そのレイテンシーを短縮するためにもASIOは必須の機能である。
ASIOによってPCオーディオが成立する
WindowsマシンによるPCオーディオは、「ASIO」の登場によって、ようやく成立したといえる。
ASIOを導入することにより、従来ほど苦労をすることなくPCオーディオの実現が可能になった。
私が最初に使ったUSBオーディオインターフェースは、YAMAHAの「UW10」である。
これには従来の通常のドライバーと、ASIO対応ドライバーとが提供されており、必要であればASIO対応USBインターフェースとして動作させることができる。
UW10の電源は、USBポートから供給を受けるようになっているが、私はこれをAC100Vで使えるように電源部を組み込み、さらに光対応のみであった入出力に、コアキシャル出力を追加して、アルミダイキャストのケースに入れる改造を行った。
この「UW10改」は、現在、外部からのS/PDIF形式のデジタルデータをPCに取り込む際に使っている。
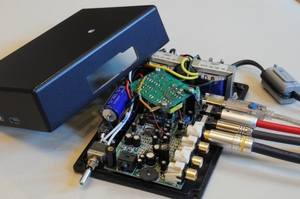
<写真4:改造版YAMAHA UW10 USBオーディオインターフェース>
**AC100V用電源と、同軸出力部を組み込み、アルミダイキャストのケースに入れた**
ASIO化後の高音質に驚く
このUW10改、最初のうちは通常のドライバーで動作させていた。
そしてiTunesのライブラリーなどを再生していたが、ASIO化に向けてのお勉強などをしながら準備して、その見通しがついた時点でASIO化を試みた。
再生プレーヤーは数ある中でも大手老舗のWINAMPを使っていたが、それをASIO化した。
UW10はYAMAHA純正のASIOドライバーが提供されている。
あれこれやったあげく、USBインターフェースと、再生プレーヤーのASIO化は成功した。
いよいよASIOを導入したPCの最初の音出しである。
こういった時には、試聴用の私の定番のCD(PC内にリッピング済み)がある。
音が出た。
ボリュームを上げる。
興奮するほど驚いた。
覆っていた膜が剥がれたように鮮明な響きである。
ASIO化による音質向上が明白であった。
当時はまだまだ「ASIO」について知っている人は少なかった。
オーディオ友達も、このことを知らなかった。
声を弾ませてASIOの成果を語ったことが懐かしい。
USBインターフェースで音が変わる
ASIOの導入により、PCとのデジタルデータの入出力には「1ビットの変化もない」はずである。
それでも音はデジタル機器によって変わる。
2年ほど前であろうか。
当ブログの「甦れSTAX ELS-8X」にちょっと登場した「かえるの息子」が、自分のシステム用にUSBオーディオインターフェースが必要になった。
いろいろ吟味した結果、Phasemationの「UDIF7」というUSB D/Dコンバータ基板を購入して自作するという。
どうも評判がいいらしい。
そこで私の分も買ってもらい、格好よくアルミダイキャストのケースに収めたのを2個一緒に作ってやった。
5V電源はバッテリー駆動にした(理由は音質ではなく、電源装置を組み込むのが面倒だったから)。
このUSB D/Dコンバータの音、これには本当に(またまた)驚いた。
CDの音がこれほどのものとは思っていなかった。
そう思うほどすばらしい音が出る。
ちなみに「UDIF7」はASIO対応であり、そのドライバーには「ASIO4ALL」を使う。
そしてこの「UDIF7」のウリはいくつかあるが、代表的にはクロック同期系が「アイソクロナス・アシンクロナス(Isochronous Asynchronous)方式」であることだろう。

<写真5:Phasemation「UDIF7」USB D/Dコンバータ>
**バッテリ駆動なので電圧計を付けた。リチウムイオン電池のすごい性能がよく分かる。最終段階近くまで電圧がほとんど変化しない(動作時の電流が小さいこともあるが)。電池から本体への電源ケーブル(写真の場合はUSBケーブルを使って自作した)は、電源とアースラインが十分に太いものを選ぶほうがよい。この電源ケーブルにより、音質がかなり変わることを確認した(原因は不明)**
データーは100%同じでも音は変わる
これらのUSBインターフェースは、「D/Dコンバーター」と呼ばれるように、音源のデジタルデータの「ある形式」を、「別の形式」のデジタルデータに変換する部分である。
具体的にはUW10もUDIF7も、USB規格のデーターフォーマットを、CDプレーヤーなどの光や同軸出力でお馴染みの「S/PDIFフォーマット」に変換する。
UW10はその逆の変換もする。
これらの「データー形式変換器」が介在することによる音源のバイナリデーターは、1ビットの変化もない。
それはASIO対応で保障されているし、実際に検証もした(フリーソフトのバイナリデータ比較ソフトがいくつか入手できる)。
それでもデジタル機器による音の違いは明確に存在する。
デジタルオーディオの根底に潜むこの原因については、今、解明されつつある段階と思っているが、その一つのヒントが、先の「UDIF7」のウリであるクロック同期系の「アイソクロナス・アシンクロナス方式」にあるにだろう。
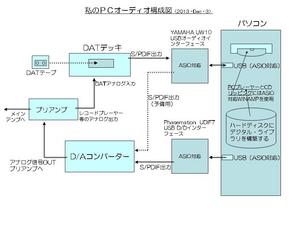
<写真6:現状の私のPCオーディオ基本構成図>
**この簡単な図を描いてみて、改めて思うのは、「PCオーディオは、USB D/DインターフェースとASIOが肝」ということを痛感する**
PCでデジタルライブラリーを構築
アナログが好きでも、デジタルの進化はありがたい。
実にありがたい。
PC内に、音源のデジタルライブラリーを、いくらでも(容量的に)、構築することができる。
みみっちく、WAV形式をMP3形式に圧縮して・・などと思い悩むこともない。
CDであれば16ビット 44.1KHz、DATであれば16ビット 48KHz(44.1KHzや32KHzも可能)のPCMを、そのままの形式で、遠慮なくどんどんアーカーブしていくことができる。
昔なら届かぬ夢であった。
音源をうまく整理してデジタルアーカイブしておけば、そのライブラリは、聴きたいものを探し出す時のストレス、イライラを解消してくれる。
いま、その夢のような時代になった。
驚異のFPGAデバイス
デジタルによるブレークスルーがやってくる予感
私が好きであったFM放送の情報誌が店頭から姿を消して久しい。
FMレコパル (1995年休刊)
FM STATION (1998年3 月休刊)
FM fan (2001年12月休刊)
「エアチェック」という言葉。
若者は知らないだろうし、もう誰も必要としない。
ところが1年ほど前、先進デジタル技術でFMチュナーを実現した基板を入手した。
何処からか、「かえるの息子」が完成品とキットとの2種類を購入してきた。
「FPGA FM STEREO TUNER」なるものである。
FPGAとはfield programmable gate arrayのことであり、FMチュナーを実現しようと思えば、このデバイスのプログラミングにより、FMチュナーに化けさせることができる。
バラック建てでNHK FMを受信してみる(受信はプログラミングによるプリセットで固定される)。
唖然として言葉にならない。
私がDATにせっせとエアチェックした時に使ったチュナーは、当時のYAMAHAの最高級機「TX-2000」である。
今も現用機であるが、これがまるで激安ラジカセの音のように思える。
音の締りがまったく異なる。
本当に凄い!。
FPGA恐るべし。
デジタルの進化には、こういうことも起こる。
いつかはオーディオの世界にも、思いもよらなかったブレークスルーが襲ってくるかもしれない。

<写真7:ついに、ようやく、PCオーディオのPCとOSを更新中>
**オーディオアンプと混同して、筐体は大きくて堅牢、電源はめいっぱい大容量。ちょっとやりすぎて後悔です。なさけなくも「かえるの息子」に組んでもらっている**
アナログはたまらなく好きですが、今後のデジタルに大きな期待を寄せるアナクロの私でもあります。
(コンポ(2)私のPCオーディオと青春デンデケデケデケ おわり)
「アナログよりもアナクロだね」といわれている私ですが、一応、PCオーディオも、PCのUSBポートなどが普及する以前から細々ながらやっていました(^-^)。
そもそも「PCオーディオ」とはなんでしょう。
私のイメージでは「パソコンを利用してピュアオーディオをやること」ぐらいに考えています。
と、その前に「ピュアオーディオ」って言葉もよく分かりませんね。
この言葉、私の解釈は「純粋オーディオ」といった感じではありません。
私の感覚では、
「ピュアオーディオ」とは、「オーディオを真面目に、熱心に追求すること」。
だと思います。
つまり「オーディオに真摯に向き合う」
だから映像に付随するサウンドトラックの音も「ピュアオーディオ」の対象です。
MP3に代表されるような、データー圧縮も「ピュアオーディオ」の対象です。
そういったものを排除するよりも、取り込んだ方が、ずっと面白くなると思います。
48Kbpsの最低のビットレートでも人は感動できる
私のPCオーディオのライブラリーに、2012年の2月に録音した、平原綾香が歌う「あいたくて」が収まっています。
NHKのラジオ深夜便の「深夜便の歌」(2012年2月時の)を、ネット配信ラジオ「らじるらじる」から別アプリでダウンロードしたものです。
「らじるらじる」の配信ビットレートは48Kbpsであり、「もう最低」といえるほどの低いレートですが、これをメインシステムできちんと聴くと、
感動します。
48Kbpsでも、人の心を激しく動かすことができる、という一例です。
さて私のPCオーディオですが、現在は、CDを直接聴く場合も、プレーヤーソフトの「WINAMP」を起動して、PCに装備されているブルーレイ・ドライブで再生しています。
その方が現有の3台のCDプレーヤーより、一段上の音がします(もちろん同一のD/Aコンバータを使って)。
また、いわゆる「my favourite music」は、PCにデジタルアーカイブされつつあり、普段はたいてい、PCのライブラリーから「WINAMP」で聴いています。
PC上の再生ソフトは、foobar2000を始め、いくつかを遍歴しましたが、いつも落ち着き先は、結局、総合的な観点からWINAMPに帰ります。
デジタルアーカイブの作業中にお宝テープを発見
そしてもう一つの、PCオーディオに関係するお話。
過去、FM放送や衛星PCM放送などを録り溜めた、何百本ものDATテープの中から発見した「青春デンデケデケデケ」です。
DATをPCにデジタルアーカイブする作業中に見つけました。
1991年の直木賞に輝いた同名の青春小説の著者、「芦原すなお」をゲストに招いたNHK FM午後の人気番組、1993年4月21日放送「ポップスステーション」のエアチェックテープです。

<写真1:「青春デンデケデケデケ」の文庫本と映画のDVD、それとDATテープ>
**本は、直木賞本(元原稿の短縮版)と、ノーカット版とがある。写真はもちろんノーカット版。映画の監督は大林宣彦。**

<写真2:著者の「芦原すなお」をゲストに招いたNHK FM「ポップスステーション」の録音テープ(DAT)。番組内容はFM誌「FMfan」の番組表の切り抜き。最下段に「芦原すなお」の名がある>

<写真3:DVDのパッケージ裏表紙>
**興味を持たれた方々、たぶんベンチャーズ世代の方々の参考までに**
「青春デンデケデケデケ」は、ベンチャーズ世代や、あまたのベンチャーズバンドを結成している面々にはよく知られた直木賞本であり映画でした。
私もその世代の一人です。
しかしその当時、著者をゲストに迎えたFMの2時間番組を聴いた方は、そう多くはないでしょう。
聴いたとしても、たぶん覚えていないでしょう。
ましてや、それを完全エアチェックしたDATテープが現存するなど、私自身もまったく覚えがない、うそのような話です。
発見以来、この録音は何回も聴いていますが、60年代にラジオ関西の電話リクエストで育ったOldiesファンの私は、聴くたびにたまらなく嬉しくなります。
本の内容にまつわる曲を、ベンチャーズの「パイプライン」に始まり、再度シャンティーズの「パイプライン」で締めくくるまでの13曲を、DJの宮本啓と著者との掛合いとともに、2時間たっぷり楽しめます。
と、このように「青春デンデケデケデケ」を発見することになった作業中のデジタルアーカイブが、今日の日記のもう一つの話です。
※(衛星PCM放送のミュージックバードは、数年前にサービス終了になってしまった)
**DATテープをデジタルアーカイブした中の、ジャンル「洋楽ポップス」の一部。「青春デンデケデケデケ」は1993年4月21日の16:00時に録音したもので、録音長120分との情報を付けてある。「ゲスト藤原竹良」とは著者の本名。このリストの聴きたいものをダブルクリックすると、WINAMPによる再生が始まる**
録り溜めた放送音源を聴きたい
さて、20年以上も前から録り溜めたDAT(digital audio tape)のカセットを詰め込んだダンボール箱が数個ある。
こんなに沢山、何を思って録ったのか、今思えば後悔している。
もっと的を絞って録ればよかった。
たぶん現役を引退して暇になったら聴こう、などと甘く考えていたのだと思う。
ひたすら録っていた頃も、「全部聴くのは無理だろう」とは薄々感じていた。
しかし「音楽放送」には、CDやレコードでは絶対に真似のできないところがある。
たとえば、NHK FMで毎週月~金の19:30から始まるベストオブクラシック。
NHK ONLINEのページにあるこの番組の能書きには「世界中の上質な演奏会をじっくり堪能する本格派クラシック番組」とある。
演奏会のライブ録音は、CDなど他のメディアでも珍しいことではない。
しかし、演奏家や音楽関係者などのゲストを呼んで話を聞いたり、音楽放送作家が要領よくまとめた原稿を番組司会者が上手に語ったり、こういったところは、「放送」の独壇場である。
なによりも実況録音は、会場の拍手やざわめきなど、場の雰囲気の録り方がまったく異なり、臨場感がすばらしい(音質のことではない)。
逆にそれがウザイ、などと思う方もおられると思うが、音楽のジャンルにかかわらず、そういった放送の場における話は、他では聞けない興味ある内容であることが多い。
テープの山、分別しなければゴミの山
さて、自適生活になって分かったが、ダンボールに詰め込まれたDATカセットを一つひとつ取り出しては聴く、などと悠長なことをやってるほどの暇はない。
時間はたっぷりある、と思っていたが、なぜか暇はさほどない。
そこでテープの内容が分かっているものから、優先順位をつけて(つまり自分好みの順に)、どんどんデジタルアーカイブ化していこう、と決心した。
そうでもしないと、整理かつかない。
とにかく「整理」しないと聴くどころではなく、手がつけられない。
家庭ゴミ、分別すれば「資源」、しなければただの「ゴミ」。
それと同じである。
デジタルライブラリーの構築に、最近のパソコンは大変な威力がある。
HDユニットの容量も、1T(テラバイト)2Tは当たり前になった。
処理速度が高速なので、音楽データの編集も、なんのストレスもなくサクサクできる。
PCオーディオ環境を充実させるための各種のソフトも豊富になった。
まあ、なにはともあれ「ゴミ」からの脱却が先決である。
そこで昨年の暮れあたりから、猛然とDATテープのデジタルアーカイブ化を開始した。
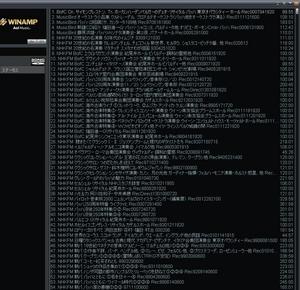
<PC画面2:WINAMPで開いたライブラリの「クラシック」のリストの一部>
**このリスト上では、1992年録音が一番古い。「Bof C」は「ベストオブクラシック」、「朝バ」はFMの長寿番組「朝のバロック」のこと。録り溜めた中では「朝バ」のテープがダントツに多い。右端の欄は録音時間長**
私の「PCオーディオ」黎明期
私がPCでオーディオ的なことをやり始めたのは、まだUSBが普及する以前、iPod、iTunesが登場する前の時代であった。
当時、PCで「音」を扱うには、大抵の場合、「サウンドボード(カード)」が必要であった。
PCのマザーボードには、デジタル入出力の端子など付いていなかった。
CDプレイヤーの光出力や、その他の音源のデジタルデーターなどをPCに取り込むには、光入力端子などのデジタル入力端子が付いたサウンドカードを必要とした。
ところがこれが曲者であり、ほとんどのサウンドカードは(そのドライバーとも絡むが)、デジタルの入力データを、そのバイナリコードの変化なしにPCに取り込むことができなかった。
出力も同じであった。
それを反映して当時のネットでは、音源のデジタルデータをいかにして「1対1」、「100%同じ」、「1ビットの変化もなしに」、PCに取り込み、またそれを出力するか、のノウハウについての記事で賑わっていた。
サウンドカードの改造や、自作もしなければならなかった。
そういった時代であった。
PCオーディオの絶対条件「1ビットたりとも変化なし」
今現在でもPCオーディオの世界において、ユーザーの意識から「抜け落ちている」のではないかと危惧される、たいへん重要なことがある。
外部の音源のデジタルデータを、「1ビットの変化もなしに」PCに取り込み、また、取り込んだデジタルデーターを、「1ビットの変化もなしに」PCから出力する。
という当たり前のことが、実はWindowsマシンでは、そう簡単にできない。
何をいっているのかと驚くほどの「とんでもない話」であるが事実である。
デジタルオーディオにおいて、データーの意識的な操作や加工は別として(ミキサーソフトで音を操作したり、MP3などで圧縮したりなどは別として)、何かの装置を通ったらデーターが変化した、などは論外である。
データーの欠損が発生したとか、化けたとか、データーが壊れたといったことではない(それは障害、故障、設備不良の範疇)。
変化したデーターを復調して(D/A変換して)、その音をちょっと聞いただけでは分からないデジタルデータの変化である。
データー的には矛盾が発生したわけではない。
具体的には、音量の変化とか、音質調整のイコライザーが入ったとか、サンプリングレート・コンバーターが介在したとか、そういった意味でのデーターの変化である。
ところがこの点に無頓着な方が意外に多い。
多分、デジタルだからそのようなことは起こらない、と頭から信じているのだろう。
それは無理もないことだと思う。
しかしWindowsのPC上で、一般的な入出力デバイスとサウンドソフトを使う場合、よほどその点に留意しないと「データーの同一性」は保障の限りではない。
PCオーディオの黎明期、PCを十分なクオリティーでオーディオに利用しようとしていた挑戦者たちの第一の目標は、この「データーの同一性」の実現に集中していた。
そこが保障されなければ、PCオーディオの成立などあり得ない。
そこがPCオーディオの基本中の基本であるはずだ。
これほどの最重要課題であるにもかかわらず、Windowsマシンでは、特別な細工をしなければ実現できないのである。
少なくともWindows xpまではそうであった。
それ以降はまだ調べてもいないし、検証もしていない。
(今現在、私のPCオーディオ環境を、Windows7へ移行するために、PCとも更新作業中です)
ASIOが解決した「データーの同一性」
「ASIO」(アジオ:Audio Stream Input Output)とは、ここではとりあえず、WindowsのMME(Multi Media Extension:オーディオデバイスのドライバ・インタフェース)をバイパスする仕掛け、と考えておけばいいと思う。
ASIOを適応した場合、「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」などのサウンドやオーディオに関するソフトは、そのレベルコントロールをはじめ、左右のバランス、音質を変えるイコライザーなど、各種の調整が無効になる。
その代わりに、Windows内で、データーの変化は起こらない。
またDTM(デスクトップミュージック)の世界では、「レイテンシー」と呼ばれる「音声信号の入出力の命令を出してから、それが実行されるまでのタイムラグ」が大きな問題になる。
そのレイテンシーを短縮するためにもASIOは必須の機能である。
ASIOによってPCオーディオが成立する
WindowsマシンによるPCオーディオは、「ASIO」の登場によって、ようやく成立したといえる。
ASIOを導入することにより、従来ほど苦労をすることなくPCオーディオの実現が可能になった。
私が最初に使ったUSBオーディオインターフェースは、YAMAHAの「UW10」である。
これには従来の通常のドライバーと、ASIO対応ドライバーとが提供されており、必要であればASIO対応USBインターフェースとして動作させることができる。
UW10の電源は、USBポートから供給を受けるようになっているが、私はこれをAC100Vで使えるように電源部を組み込み、さらに光対応のみであった入出力に、コアキシャル出力を追加して、アルミダイキャストのケースに入れる改造を行った。
この「UW10改」は、現在、外部からのS/PDIF形式のデジタルデータをPCに取り込む際に使っている。
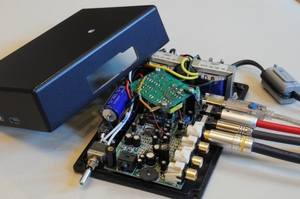
<写真4:改造版YAMAHA UW10 USBオーディオインターフェース>
**AC100V用電源と、同軸出力部を組み込み、アルミダイキャストのケースに入れた**
ASIO化後の高音質に驚く
このUW10改、最初のうちは通常のドライバーで動作させていた。
そしてiTunesのライブラリーなどを再生していたが、ASIO化に向けてのお勉強などをしながら準備して、その見通しがついた時点でASIO化を試みた。
再生プレーヤーは数ある中でも大手老舗のWINAMPを使っていたが、それをASIO化した。
UW10はYAMAHA純正のASIOドライバーが提供されている。
あれこれやったあげく、USBインターフェースと、再生プレーヤーのASIO化は成功した。
いよいよASIOを導入したPCの最初の音出しである。
こういった時には、試聴用の私の定番のCD(PC内にリッピング済み)がある。
音が出た。
ボリュームを上げる。
興奮するほど驚いた。
覆っていた膜が剥がれたように鮮明な響きである。
ASIO化による音質向上が明白であった。
当時はまだまだ「ASIO」について知っている人は少なかった。
オーディオ友達も、このことを知らなかった。
声を弾ませてASIOの成果を語ったことが懐かしい。
USBインターフェースで音が変わる
ASIOの導入により、PCとのデジタルデータの入出力には「1ビットの変化もない」はずである。
それでも音はデジタル機器によって変わる。
2年ほど前であろうか。
当ブログの「甦れSTAX ELS-8X」にちょっと登場した「かえるの息子」が、自分のシステム用にUSBオーディオインターフェースが必要になった。
いろいろ吟味した結果、Phasemationの「UDIF7」というUSB D/Dコンバータ基板を購入して自作するという。
どうも評判がいいらしい。
そこで私の分も買ってもらい、格好よくアルミダイキャストのケースに収めたのを2個一緒に作ってやった。
5V電源はバッテリー駆動にした(理由は音質ではなく、電源装置を組み込むのが面倒だったから)。
このUSB D/Dコンバータの音、これには本当に(またまた)驚いた。
CDの音がこれほどのものとは思っていなかった。
そう思うほどすばらしい音が出る。
ちなみに「UDIF7」はASIO対応であり、そのドライバーには「ASIO4ALL」を使う。
そしてこの「UDIF7」のウリはいくつかあるが、代表的にはクロック同期系が「アイソクロナス・アシンクロナス(Isochronous Asynchronous)方式」であることだろう。

<写真5:Phasemation「UDIF7」USB D/Dコンバータ>
**バッテリ駆動なので電圧計を付けた。リチウムイオン電池のすごい性能がよく分かる。最終段階近くまで電圧がほとんど変化しない(動作時の電流が小さいこともあるが)。電池から本体への電源ケーブル(写真の場合はUSBケーブルを使って自作した)は、電源とアースラインが十分に太いものを選ぶほうがよい。この電源ケーブルにより、音質がかなり変わることを確認した(原因は不明)**
データーは100%同じでも音は変わる
これらのUSBインターフェースは、「D/Dコンバーター」と呼ばれるように、音源のデジタルデータの「ある形式」を、「別の形式」のデジタルデータに変換する部分である。
具体的にはUW10もUDIF7も、USB規格のデーターフォーマットを、CDプレーヤーなどの光や同軸出力でお馴染みの「S/PDIFフォーマット」に変換する。
UW10はその逆の変換もする。
これらの「データー形式変換器」が介在することによる音源のバイナリデーターは、1ビットの変化もない。
それはASIO対応で保障されているし、実際に検証もした(フリーソフトのバイナリデータ比較ソフトがいくつか入手できる)。
それでもデジタル機器による音の違いは明確に存在する。
デジタルオーディオの根底に潜むこの原因については、今、解明されつつある段階と思っているが、その一つのヒントが、先の「UDIF7」のウリであるクロック同期系の「アイソクロナス・アシンクロナス方式」にあるにだろう。
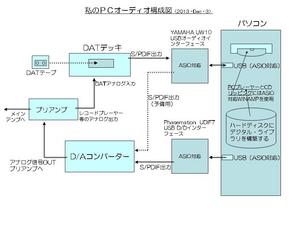
<写真6:現状の私のPCオーディオ基本構成図>
**この簡単な図を描いてみて、改めて思うのは、「PCオーディオは、USB D/DインターフェースとASIOが肝」ということを痛感する**
PCでデジタルライブラリーを構築
アナログが好きでも、デジタルの進化はありがたい。
実にありがたい。
PC内に、音源のデジタルライブラリーを、いくらでも(容量的に)、構築することができる。
みみっちく、WAV形式をMP3形式に圧縮して・・などと思い悩むこともない。
CDであれば16ビット 44.1KHz、DATであれば16ビット 48KHz(44.1KHzや32KHzも可能)のPCMを、そのままの形式で、遠慮なくどんどんアーカーブしていくことができる。
昔なら届かぬ夢であった。
音源をうまく整理してデジタルアーカイブしておけば、そのライブラリは、聴きたいものを探し出す時のストレス、イライラを解消してくれる。
いま、その夢のような時代になった。
驚異のFPGAデバイス
デジタルによるブレークスルーがやってくる予感
私が好きであったFM放送の情報誌が店頭から姿を消して久しい。
FMレコパル (1995年休刊)
FM STATION (1998年3 月休刊)
FM fan (2001年12月休刊)
「エアチェック」という言葉。
若者は知らないだろうし、もう誰も必要としない。
ところが1年ほど前、先進デジタル技術でFMチュナーを実現した基板を入手した。
何処からか、「かえるの息子」が完成品とキットとの2種類を購入してきた。
「FPGA FM STEREO TUNER」なるものである。
FPGAとはfield programmable gate arrayのことであり、FMチュナーを実現しようと思えば、このデバイスのプログラミングにより、FMチュナーに化けさせることができる。
バラック建てでNHK FMを受信してみる(受信はプログラミングによるプリセットで固定される)。
唖然として言葉にならない。
私がDATにせっせとエアチェックした時に使ったチュナーは、当時のYAMAHAの最高級機「TX-2000」である。
今も現用機であるが、これがまるで激安ラジカセの音のように思える。
音の締りがまったく異なる。
本当に凄い!。
FPGA恐るべし。
デジタルの進化には、こういうことも起こる。
いつかはオーディオの世界にも、思いもよらなかったブレークスルーが襲ってくるかもしれない。

<写真7:ついに、ようやく、PCオーディオのPCとOSを更新中>
**オーディオアンプと混同して、筐体は大きくて堅牢、電源はめいっぱい大容量。ちょっとやりすぎて後悔です。なさけなくも「かえるの息子」に組んでもらっている**
アナログはたまらなく好きですが、今後のデジタルに大きな期待を寄せるアナクロの私でもあります。
(コンポ(2)私のPCオーディオと青春デンデケデケデケ おわり)



